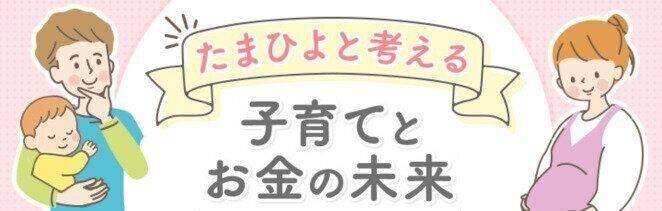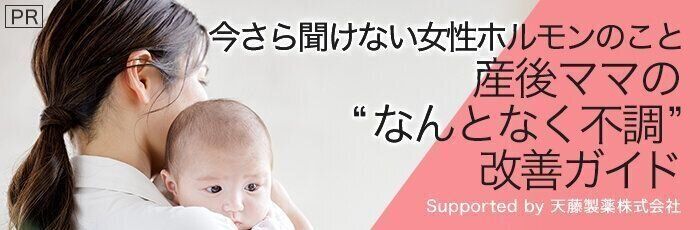『胚培養士ミズイロ』監修クリニックで働く不妊治療のプロ「胚培養士」に聞く!“大切なのは、受精卵ではなく人を見ること”
2022年4月から保険適用が始まった不妊治療。胚培養士は、その中心的な役割を担っていると言われていますが、具体的にはどのような仕事をしているか、ご存知でしょうか?
「生命の誕生に直接的にかかわれる非常に数少ない職種の一つなんです」そう話すのは、不妊治療専門施設・リプロダクションクリニックの培養部長で体外受精コーディネーターなどの資格を有する、水田真平さん。
詳しい仕事内容ややりがいなどについてお聞きしました。
胚培養士ってどんな仕事?

「伸びしろがあると感じた胚培養士の仕事は、自分にぴったりだと思いました」と水田さん。
もともとは臨床検査技師を目指していたそうですが、人と直接かかわる仕事に就きたいと思っていたことと、遺伝学に興味を持ったことが現職に就くきっかけだったそうです。
「生殖補助医療は日進月歩で、いろいろな治療方法や新しい技術、機器などが次々に誕生しています。ですが、それでもまだわからないことがいっぱいあるのが現状です。
私が胚培養士になった2005年ごろは、それ以上に未知で不確実な部分が多かったんです。その状況を知って“解明したい”と気持ちが掻き立てられましたね。元々、新しいことに取り組んで道を切り開きたいと強く思っていたので、“これだ!”と考えて現職に就きました」(水田さん)
胚培養士は、具体的にどのような仕事をしているのでしょう?
仕事は誕生に直接かかわるほぼすべてのこと
『胚培養士ミズイロ』の制作に協力した立役者の1人でもある水田さんに、胚培養士の仕事内容を尋ねると、
「人工授精(※1)や体外受精(※2)の精子の調整をはじめ、卵子の探索、体外受精や顕微授精(※3)の受精作業、受精卵の培養・凍結・融解、胚移植(※4)の準備や管理など、生命の誕生に直接かかわるほぼすべてのことを胚培養士が行っています」と話します。
施設によって仕事の内容は異なる場合がありますが、患者さんの診察や処置の介助、血液検査、治療の説明などを行うこともあるそうです。
「当院では2013年の大阪での開院から、胚培養士と患者さんが面談する時間を作り、培養結果などを説明しています」(水田さん)
胚培養士が患者さんと面談する理由とは?
不妊治療施設では、必要に応じて胚培養士が精子や卵子、受精卵の状態などを患者さんに説明する場合があります。
水田さんが勤務する施設では、すべての患者さんに胚培養士との面談が設けられ、精子や卵子、受精卵の状態などを説明すると言います。
これは、施設立ち上げメンバーでもある、水田さんの強い希望だったそうです。どうしてなのでしょう?
「治療への想いや希望は患者さんの数だけあると思うんです。だからこそ、しっかり説明して納得していただく必要があるんじゃないかと考えました。患者さんにとっても、精子や卵子などを扱っている胚培養士が説明したほうが、より具体的でわかりやすいかなと思う場合もあります。
たとえば“受精卵は●●に育ったからよかった、もしくは▲▲が原因で難しい結果になった”などと時間をとって詳しい説明ができますからね。
不妊治療は時間に限りがある上、治療を乗り越えれば必ず挙児(※5)を得られるという確約がないことが難しい問題です。そのような不安な状況だからこそ、できる限り納得のいく説明を受けた上で治療を受けられる方が、患者さんの精神衛生的にもよいかなと思います。受精卵を取り扱うプロフェッショナルとして、胚培養士がその適任者だと思っています」(水田さん)
面談は胚培養士にもいいことが!
「面談は患者さんの想いを実感できる場であり、胚培養士のモチベーションや気づきにつながる場でもあるんです」と水田さん。
いい結果もよくない結果も、患者さんと共有することで一緒に喜んだり、よりよい結果となるように熟考する。それが仕事の活力となり、考える力も養えると話します。
「ラボで患者さんから預かった受精卵などを扱うことは、胚培養士として最も重要な業務です。でも、その根底には必ず患者さんの想いがある。それを意識することが大切だと思っています。面談は今後も続けていきたいです」(水田さん)
生命の誕生のために…。次々に起こる課題に取り組む!
胚培養士のやりがいはどんなところにあるのでしょうか?
「自然妊娠なら、女性のおなかの中に精子が射精され、受精して、日々育って赤ちゃんになっていきますよね。
その様子はなかなか見られないことですが、胚培養士はもっともっと前の、まさに生命の誕生の瞬間が見られる数少ない職業だと思っています。
生命の誕生というとてつもなく神秘的な現場に身を置き、挙児につながるように、次々に起こる新たな課題に取り組めることは、この仕事のやりがいだと思います」(水田さん)
大事なのは“人を見ること”“タイミング”
胚培養士として水田さんが大切にしていることは2つあって、1つは“受精卵ではなく人を見ること”。
これは、精子や卵子、受精卵を治療しているのではなく、患者さんのために治療を行っていることを表し、胚培養士育成の場でも伝えているそうです。
そして、生命の誕生につながる精子、卵子、受精卵それぞれのタイミングに注視することも大事だと水田さん。
「精子が卵子の中に入る、受精が起こる、受精卵が子宮に着床するなどのベストタイミングは割と狭く、それにすべての治療を100%合わせるのは、なかなか難しいんです。
たとえば、顕微授精で精子を注入するタイミング。精子は、射精した段階では数千万〜1億個くらいあります。そのときは膨大な数なのですが、その中から最良だと考えられる方法でよい精子だけのグループを集めている間に、数万〜100万個くらいに減ってしまいます。さらに、残った中から1位を受精のベストタイミングで見つけられればいいのですが、なかなか困難で…。
そのため、できる限りよい精子のグループを効率的に集めることができる方法を日々模索し、各患者さんの精子の状態に合わせて使用しています。
精子は胚培養士が「選ぶ」ことができるので非常に重要な仕事の一つだと常に伝えています」
『胚培養士ミズイロ』に気づきあり! “目指していたのはコレ”
『胚培養士ミズイロ』のファンの1人でもある水田さん。作品を通じ、大きな気づきがあったと話します。
「患者さんの培養成績などは毎日しっかり確認していますが、“今日の午前中は●●さんの妊娠判定日だ!”といった日々の動きは十分に把握しきれていないこともあるんです。
ラボでは受精卵などの取り扱いに集中するのがベストです。でも、患者さんのよい結果はリアルタイムで知ったほうが胚培養士全員の士気があがるのも事実。“やった~!”ってみんなで喜ぶ瞬間があってもいいなと思ってはいたんです。
でも、日々の忙しさから、そういった理想になかなかたどり着けなくて…。
漫画には、医師が患者さんの妊娠判定結果を電子カルテに入力した瞬間、胚培養士全員がガッツポーズをするシーンがあるんですが、それを見たとき“目指してたのはこういうことだよな”と改めて思いました。
冷静で仕事はきっちりするけど、患者さんには深入りしないという胚培養士も漫画には登場するんですが、その考えも正しい。
でも、忙しさに流されず、患者さんの動向を気にかけながら仕事をするのも大事だなと実感しました」
取材・文/茶畑美治子
「不妊治療中の方、赤ちゃんが授からずに悩んでいる方は、不公平な想いや不安、不満をかかえながら、期待を持って治療に臨まれていると思います。でも、赤ちゃんになるずっと前の卵子や受精卵の様子などが見られるのは、治療を受けられた方だけです。これだけでは、不利益なことを埋められないかもしれませんが、非常に特別なことだと思っています」と水田さん。
赤ちゃんが生まれることは当たり前と思っている方もいらっしゃることでしょう。でも、生まれるまでの過程には、さまざまな予期せぬことが起こり得る現実があります。そう考えると、生命の誕生はまさに奇跡的なことなのかもしれませんね。
取材協力・写真、画像提供/リプロダクションクリニック大阪、小学館ビックコミックスピリッツ編集部
※1 人工授精/精子のみを体外で調整して女性の子宮に入れる治療方法。
※2 体外受精/精子と卵子を体外に取り出して受精させた後に女性の子宮に戻す治療方法の一連の総称、また体外で卵子に精子をふりかける受精方法を指す場合もある。
※3 顕微授精/顕微鏡で精子と卵子を観察しながら、ガラス製の専用針を使用して1つの精子を取り込んで卵子に注入する治療方法。(一般社団法人日本生殖医学会HP参照)
※4 胚移植/体外で受精させた受精卵を子宮に戻す方法。(一般社団法人日本生殖医学会HP参照)
胚培養士ミズイロ (ビッグコミックス)
2023年1月30日に単行本が発売。
水田真平さん リプロダクションクリニック大阪/東京 胚培養部長
日本卵子学会 生殖補助医療胚培養士。日本不妊カウンセリング学会 体外受精コーディネーター。日本臨床エンブリオロジスト学会 理事。日本卵子学会 代議員。日本不妊カウンセリング学会 評議員。臨床検査技師。
2003年3月藤田保健衛生大学衛生学部卒業後、同年4月藤田保健衛生大学大学院保健学研究科入学。2005年3月藤田保健衛生大学大学院保健学研究科 修了。英ウィメンズクリニック培養部門リーダーなどを経て、2013年1月リプロダクションクリニック大阪 開設担当部長に就任。同年9月リプロダクションクリニック大阪 胚培養室室長。2017年2月より現職。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い