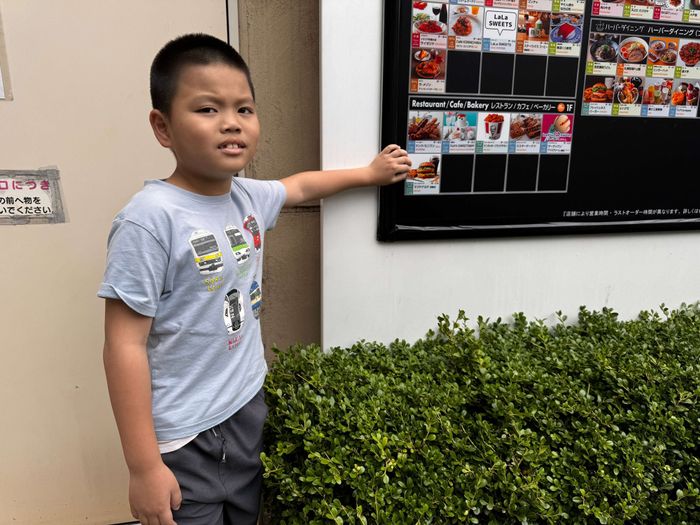4歳で軽度知的障害を伴う自閉スペクトラム症と診断された長男。かんしゃくやパニックに何度も限界を感じて・・・【体験談】
2025年4月から特別支援学校の小学4年生になるもっくんは、自閉スペクトラム症と軽度知的障害と診断されています。診断されたのは4歳になってからです。
YouTube「もっくん&かりんとう」で、もっくんと妹のかりんちゃんの日常を配信しているもっくんママに、自閉スペクトラム症と診断されたときのことや就学先選び、習い事について話を聞きました。
全2回インタビューの後編です。
妹が生まれても関心を示さない
もっくんに妹が生まれたのは、もっくんが2歳のときです。そのころもっくんママは、もっくんの様子に違和感を覚えながらも、「なんだろう?」と思っていました。妹のかりんちゃんが産院から退院してきたときも、もっくんママは、もっくんの様子にいくつかの気になることがあったそうです。
「赤ちゃんが生まれると、お世話をしたがったり、抱っこしたがったりする上の子は多いと思うのですが、もっくんは妹にまったく関心を示しませんでした。ベビーベッドにかりんが寝ていても、のぞき込んだり、触ったりしないんです。
また3歳ごろから、道の歩き方にこだわるようになり、まっすぐ歩道を歩けばいいのに、いつも同じところで反対側に行ったり、また戻ったりするんです。『もっくん、まっすぐ歩こうよ』と言うと、怒ってかんしゃくを起こして大変なので、しかたなくもっくんの言うとおりに不思議なルートで歩いていました」(もっくんママ)
他者への関心の弱さや、過度なこだわりの強さも自閉スペクトラム症の特性です。
医師から、妹ともっくんの行動の違いを説明され、もっくんの特性に気づいた
もっくんが自閉スペクトラム症と診断されたのは、4歳3カ月ごろです。
「もっくんは言葉の発達がゆっくりで、3歳ごろは『ジュース、飲む』など2語文で、自分のしたいことだけを伝えてきました。言葉の発達を促すために療育に通っていたのですが、療育で知り合ったママたちと療育手帳の話になり、『もっくんも、言葉が遅いからもらえるのかな? 手帳をもっていたほうが療育がスムーズかな?』と思い、大学病院で診てもらうことにしました。
診察を受ける前に、病院から同じ問診票を2枚渡されて『夫婦でそれぞれ書いてもらいたいのですが、話し合ったりしないで記入してください』と言われました。問診表は、子どもの気になる様子などをチェックしたり、記入したりするものでした。
病院には、2歳になった妹のかりんも連れて行ったのですが、医師はもっくんの様子などをしばらく見て『もっくんは自閉スペクトラム症である』と言ったんです。
医師からは『妹さんは、いろんなおもちゃで遊ぶでしょ? でも、もっくんは同じおもちゃでずっと遊んでいるよね? これも自閉スペクトラム症の特徴です』と説明されました。
確かに診察室に入ってからのかりんともっくんの行動はまったく違いました。
かりんは、私から離れません。しばらくすると『大丈夫』とわかったようで私から離れて、診察室に置いているおもちゃを見て『ママ、これで遊んでいい?』と聞いて、私が『いいよ』と言ってから遊び始めました。慣れてくると、いろいろなおもちゃに手を伸ばしました。
しかしもっくんは診察室に入るなり、警戒心を抱くこともなく、私や医師に許可をとることもなく、興味のあるおもちゃにまっしぐら。同じおもちゃでずっと遊んでいました。
医師の説明を聞いて『そういえば家庭でも、もっくんはいつも同じおもちゃでばかり遊んでいる。なんで私、もっと早く気づいてあげられなかったんだろう・・・』と思いました」(もっくんママ)
もっくんは自閉スペクトラム症と軽度の知的障害と診断されて、療育手帳が交付されることになりました。療育手帳とは、知的障害がある人に交付される障害者手帳です。
「診断されたあと、夫にすぐに電話をしました。夫は『そうなんだ・・・』と言って、言葉に詰まっていました。夫婦で別々に書くようにと言われた問診票の夫の分を、診察室でちらっと見たら、もっくんの興味があるものの記述が、私とほぼ同じで『夫も、しっかり見ていたんだ・・・』と思いました」(もっくんママ)
もっくんは、特別支援学校へ。視覚支援で苦手をサポート
もっくんは特別支援学校に通っています。2025年4月から4年生です。
「就学前に特別支援学校を見学したとき、見学ルートの表を見せながら先生が『次は、校庭に行くよ』などと教えてくれました。目で確認しながら、見通しがもてることで、もっくんは安心して見学していました。
また登校し始めてから感じたのは、スプーンやお茶腕の持ち方など、私がいくら注意しても直らなかったのに、特別支援学校に通ったら直ったんです。先生は、正しいスプーンの持ち方などを写真で見せて、うまく持てるとほめて根気よく教えてくれたようです。
特別支援学校に入るまでは、特別支援学級のほうがいいのかな?と悩んだのですが、今になってみると特別支援学校のほうがもっくんには合っていたと思います」(もっくんママ)
またもっくんは、幼稚園の年中からピアノ教室に通っています。
「もっくんは視覚と聴覚が優位なようで、耳で聴いた音をピアノで再現できるんです。譜面を見るのではなく、耳で聴いただけでかなり近いメロディーをピアノで表現できます。それに気づいたときにはとてもびっくりしました。今は、DVDで『アナ雪』を何度も見て、主題歌や挿入歌をピアノで弾こうとしています。気分が乗ると、自分で変調をしたり、自由にアレンジしたりもします。
私も子どものころからピアノを習っていましたが、もっくんはピアノが大好きです。しかも独自の方法で音を自分のものにしていっている感じです。
もっくんの将来のためにも、少しでも得意なことを伸ばしてあげられるといいのかなと考えています」(もっくんママ)
いろいろな人と出会い、もっくんを受け入れられた
もっくんママがYouTube「もっくん&かりんとう」を始めたのは、4年前です。
「自閉スペクトラム症と診断されて悩んでいたときに、YouTubeで自閉スペクトラム症の子どもとの日常を投稿しているママがいて、私はそれを見ていて心がとても救われました。そして私も、自分たちの経験をいかして、だれかの役に立ちたいと思うようになり、YouTubeを始めました。
でも実際に始めると、私のほうが学ばせてもらったり、励まされることが多いです。もっくんが手に負えなくなり、落ち込んでいたときも、もっくんを受け入れてくれるコメントをいただけて、ありがたかったです。あたたかいコメントを読みながら『私もこういう視点をもって、子育てができるようになりたい』と思ったりしています。
実は、もっくんの障害を私が受容するまでには時間がかかりました。4歳3カ月で診断されてすぐに受容できたわけではないんです。どうにか受け止めることができるようになったのは、もっくんが1年生になってからです。
なかには『診断されたら受容できるのでは?』『特別支援学校を選ぶということは、障害を受容しているからでは?』 と思うママ・パパもいるかもしれませんが、私は簡単には受容できませんでした。自閉スペクトラム症と頭ではわかっていても、『なんでそんなことするの!』とついもっくんを怒ってしまったり、『もう無理』と思って、クールダウンするために1人で外に出て、近所を歩いたこともあります。ちょっとしたことでかんしゃくを起こしたり、パニックになったするもっくんを見て、何度限界を感じたことか・・・。
でも特別支援学校の先生や、YouTubeで精神科医さわ先生などと出会えたことで、もっくんのことをやっと理解でき、かわいいと思えるようになったんです。もっくんがいるから、今の私があるとも思います」(もっくんママ)
【精神科医さわ先生より】子どもの特性を理解して、生きやすい環境を用意し、サポートすることが大切
もっくん、そしてもっくんママさんとはYouTubeのコラボ撮影をきっかけにそれ以来、仲よくさせてもらっています。もっくんママさんは、もっくんの特性をとてもよく理解されていて、その知識は専門家の私から見てもすごいなぁと思います。
神経発達症という疾患は、本人を治そうとするというよりは、本人の発達の特性を家族やまわりでサポートをする支援者が理解し、本人にとって生きやすい環境を用意しサポートすることがとても大切です。神経発達症の子育てはけして一筋縄ではいかない子育てだと思いますが、そのありのままの姿をYouTubeなどで発信されることで、多くの子育てに悩む親御さんたちが救われていると思います。もっくん、かりんちゃん、もっくんママさん、これからもぜひ笑顔あふれる毎日を過ごされてくださいね。
お話・写真提供/もっくんママ 監修/精神科医さわ先生 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部
4月2日は、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。日本では、4月2日~8日を発達障害啓発週間として、自閉症のシンボルカラーであるブルーを用いてライトアップなどを行います。ブルーの意味はいやし、希望です。イメージキャラクターは、セサミストリートです。セサミストリートの中には、ジュリアという自閉症の特性がある女の子がいます。この機会に、子どもとセサミストリートを見て、自閉症への理解を深めてみませんか。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。
精神科医さわ先生
PROFILE
児童精神科医。精神科専門医、精神保健指定医、公認心理師。1984年三重県生まれ。藤田医科大学医学部を卒業後、勤務医を経て2021年に名古屋で塩釜口こころクリニックを開院。開業直後から予約が殺到し、現在も毎月約400人の親子の診察を行っている。これまで延べ3万人以上の診察に携わってきた。
2人の娘を育てるシングルマザー。長女が不登校となり、発達障害と診断される。
●記事の内容は2025年3月の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い