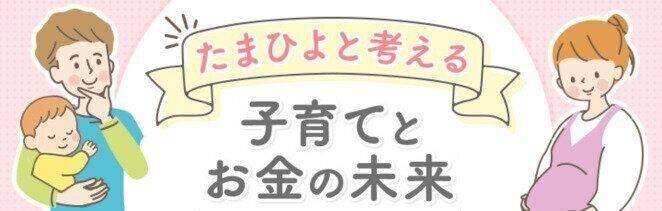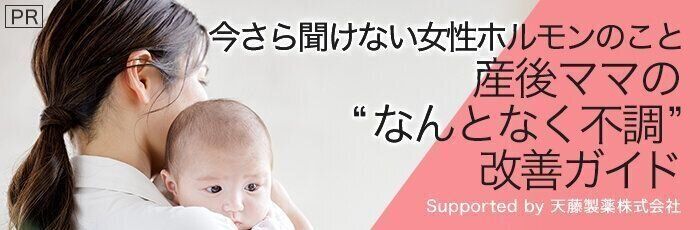【マンガで解説】不妊治療「タイミング法」ってどんなもの?排卵誘発も 不妊治療クリニック受診ガイドSTEP3[男女共通]
![【マンガで解説】検査後いよいよ治療へ…治療の流れを知ろう!不妊治療クリニック受診ガイドSTEP2[男女共通]](https://img.benesse-cms.jp/tamahiyo/item/image/normal/resized/resized_579ff237-cfec-4080-9d60-1dc1dade97e5.jpg?w=100&h=60&resize_type=cover&resize_mode=force)

妊活を始めたけれど…なかなか妊娠しない。そろそろクリニックに行ったほうがいい?
今回は、不妊治療【ステップ3】 タイミング法と排卵誘発について、齊藤英和先生に詳しく解説していただきました。
マンガでわかる!いつかのための不妊治療クリニック受診ガイド #5
※参考:「妊活たまごクラブ 2025-2026年版」
※この記事は、「妊活たまごクラブ2025-2026」からの抜粋です。
マンガに登場するのは…
もうじき結婚して2年になる玉田陽太とひな夫妻。同じ会社の同期で32歳。
サッカー観戦が共通の趣味で、毎日楽しく過ごしているけれど、友人たちからの妊娠報告にちょっとあせり始めたところ。
不妊治療マンガ「排卵のタイミングがわかる検査と排卵誘発」
※LHサージとは?=排卵を誘起する黄体形成ホルモン(LH)が脳の下垂体から大量に放出される現象のこと。尿からLHの急増が検出されると、一定時間後に排卵が起こるとされています。
不妊治療において排卵のタイミングを測ることは不可欠です。
クリニックでタイミング法を実施する場合、排卵していれば排卵の時期を正確に測り、排卵がうまくいっていなければ排卵誘発を行います。
正確に予測された排卵日に合わせてセックスするのがタイミング法
★自然妊娠の確率を高める方法
タイミング法は排卵日を予測し、医師から指示されたタイミングにセックスを行うことで、自然妊娠の確率を高める方法です。排卵は卵胞が直径20mm前後に成長したころに起こるため、女性が超音波検査を受けて卵胞の大きさから排卵日を医師が見定めます。さらに、排卵直前に値が急増するLHホルモンを尿検査で検出することで、セックスするタイミングがわかります。
うまく排卵していない場合は、排卵誘発剤を用いることも。排卵誘発剤には質の良い卵子を育て、排卵を促す効果があります。
その後、月経予定日を過ぎたら、尿検査や内診、超音波検査などを行い、妊娠したかどうかをチェックします。
★次のステップは人工授精
年齢によってタイミング法にトライする回数は変わります。ただし、検査結果で男性側の乏精子症(数が少ない)や精子無力症(動きが鈍い)がわかった場合や、女性側に精子の侵入を妨げる頸管粘液不全などのトラブルがある場合は、早い段階で人工授精に進みます。
タイミング法のプロセス
(1)検査で排卵日を予測する
排卵は卵胞が直径20mm前後に成長したころに起こるため、女性は超音波検査を数回受けます。卵胞の大きさを基に、さらに尿中LHホルモンを検出する排卵検査キットを併用して医師が排卵日を特定。セックスのタイミングが指導されます。
(2)排卵の有無と状態を確認する
セックス後に超音波検査によって排卵の有無を調べます。また、子宮内を着床しやすい状態に整える黄体ホルモンの分泌状態を調べ、足りない場合は補充します。
(3)妊娠判定検査を行う
月経予定日を過ぎたら、尿検査や内診、超音波検査などを行い、妊娠が成立したかどうかをチェックします。
ここまでの検査や治療にかかる費用は保険適用です
現在、不妊検査や治療には保険が適用されており、自費診療の場合の3割負担で受けられます。令和4年4月以前は、人工授精でも治療費が高いため、ステップアップを躊躇する人が多くいましたが、そのハードルはかなり下がったといえるでしょう。
保険適用になったことで、費用面のメリットだけでなく、不妊治療が一般的な“普通の”治療であるという見方が、世間一般にも示されたことになりました。早く治療を進めることが、より妊娠率を上げることにもつながるので、経済的にも精神的にも治療ステップアップへのハードルが下がることは良いことでしょう。
「いつかのための不妊治療クリニック受診ガイド」、次の記事は【STEP4&5 男女共通不妊治療の始めどきは「何人子どもが欲しい?」希望次第!人工授精・体外受精・顕微授精編】をお届けします。
ぜひ、ご覧ください!
■監修
■マンガ・イラスト/小森うに
5年半の妊活・不妊治療を経験。自身の不妊治療体験の漫画をSNSやブログで発信中。また、不妊症・不育症ピアサポーターとして不妊治療中のかたの相談を受けるなどの活動をしている。
■構成・文/関川香織
※記事掲載の内容は2025年2月21日現在のものです。以降変更されることもありますので、ご了承ください。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い