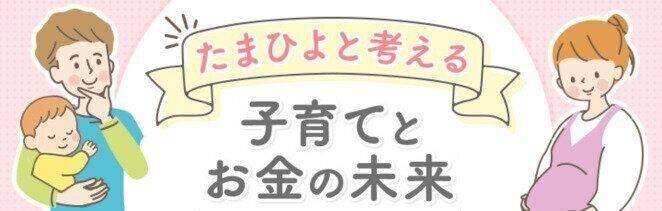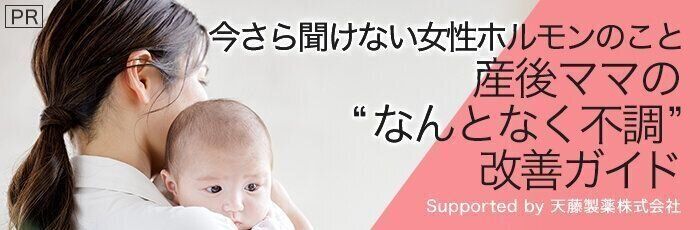まずは基礎知識! 妊活のはじめ方【医師監修】
 赤ちゃんが欲しいと「妊活」を意識し始めたけれど、妊娠のしくみや男女の体のこと、卵子や精子のことについて意外と知らないこともあるのでは?
赤ちゃんが欲しいと「妊活」を意識し始めたけれど、妊娠のしくみや男女の体のこと、卵子や精子のことについて意外と知らないこともあるのでは?
男女の身体の基礎知識や女性の生理周期、排卵や妊娠のステップについて、竹内正人先生にお話を聞きました。
男女の体の基本知識を知ろう
妊娠のしくみ、男女の体のこと、卵子や精子のことについて知っていますか?実は意外に知らない「妊娠のしくみ」と自分たちの「体」のこと、この機会に2人でおさらいをしましょう。
妊活を通して将来設計をすり合わせるよいチャンスです。
女性は、生まれたときから卵子を持って誕生
女性は胎児のときに、卵巣に一生分の卵子になる細胞のもとを700万個ほど持っており、生まれる前から、次の世代を育む準備をして生まれてきます。思春期には生理が始まり、体が出産のための準備を始めますが、こうした働きは、すべて女性ホルモンによるものです。
女性の体 ~女性性器(正面)~
正面から見ると…
下腹部にあるのが子宮です。大きさは鶏の卵ぐらいで、妊娠すると赤ちゃんがここで育ちます。子宮の両側から伸びているのが卵管で、その先端に卵管采があり、卵巣から飛びだした卵子をキャッチします。
卵巣からは毎月1個、卵子が排卵され、卵管膨大部で受精すると受精卵は子宮に運ばれます。子宮や卵巣は、これらを固定する靭帯(じんたい)や胎児に栄養などを届ける血管と一緒に、骨盤内に収まっています。
女性の体 ~女性性器(横)~
横から見ると…
膀胱(ぼうこう)と腸の間にあるのが子宮で、やや前傾しています。
受精卵が着床し、妊娠の経過が進むと、赤ちゃんとともに子宮もどんどん大きくなります。
妊娠にはタイムリミットがある
一般的に、女性の体が妊娠できるのは、10代半ばから40代半ばまでの約30年間。初潮後数年は、周期も不安定で、毎回排卵があるわけではありません。30代になると婦人科系のトラブルも増え、35才を過ぎれば、妊娠の確率が低くなります。40代になると出産に結びつく卵子が減り、50才前後の閉経後は、排卵がないので自然妊娠はできません。
男性は日常生活のストレスが体にも影響しやすい
女性とはまったく異なった構造を持つのが男性の体。そのしくみは意外とデリケートで、心とも密接な関係があると言われています。
思春期になり、第二次性徴を迎えると、男性ホルモンの影響で、体形、体毛、声など、見た目にもさまざまな変化が見られるようになります。精巣では毎日約1億個の精子がつくられるようになります。男性の体もデリケート。日々のストレスで勃起障害(ED)になることもあります。
男性の体 ~男性性器(横)~
横から見ると…
男性は思春期を迎えると、男性ホルモンの働きで、2つの精巣(睾丸)では、毎日1億個ほどの精子がつくられるようになります。性的興奮が起きると陰茎(ペニス)が勃起し、射精が行われると、1~3億個ほどの精子が体外に出されます。射精されなかった精子は、体内で吸収されて消えてしまいます。
妊娠に必要な4つの生理周期とは?
生理(月経)には4つの周期があり、女性にとって妊娠するために必要不可欠な体の働きです。まず、脳から女性ホルモンに卵巣を刺激するように指令が出されると、卵巣の中で毎月20個程度の卵胞が成長していきます。次の排卵期で、卵巣からたった1個の卵子が出され、卵管で受精に備えます。そして黄体期になると、子宮の内膜が最も厚くなり着床の準備をします。
ここで受精が成立しないと、卵子は消滅し、子宮内膜も剥がれ落ちて月経となります。毎月のことなので面倒に思われがちですが、生理は「今月も、赤ちゃんを迎える用意をしていましたよ」という大事なサインなのです。
生理のバイオリズムには4つの周期があります
生理には、月経、卵胞期、排卵期、黄体期の4つの周期があります。女性ホルモンの働きによって、女性の体が妊娠できるように整えています。生理の周期は25〜38日、月経は3〜7日間続きます。
| ●周期1: 月経 | 妊娠が成立しなかったために、子宮内膜が剝がれ落ちて、血液と一緒に体外に出てくるのが月経です。月経の期間には個人差があります。 |
| ●周期2: 卵胞期 | 卵巣で毎月20個程度の卵胞が成長し、最終的にそのうちの1個が成熟し排卵します。同時に子宮内膜も厚くなります。卵胞期は6~7日間程度で、生理周期の中でもいちばん体調のよい時期。 |
| ●周期3: 排卵期 | 卵巣で成熟したたった1個の卵子が卵巣から飛び出し、排卵します。卵子は卵管にとらえられて受精に備えます。排卵期は排卵の前後4~5日間くらいのことをいいます。 |
| ●周期4: 黄体期 | 子宮内膜が最も厚くなる時期です。排卵によって女性ホルモンのバランスが変化し、便秘や肌荒れ、イライラが起こる人も。 |
生理にまつわるトラブルが起こる場合も
PMS
生理前の黄体期に、女性ホルモンの変化が原因で、便秘や肌荒れ、イライラなどの症状が出ることをPMS(月経前症候群)といいます。
個人差がありますが、生理後も症状が続く場合は、別の病気の可能性もあるので医師に相談を。
生理痛
下腹部が重くなったり痛みが出たり、生理中はだれでも多少の違和感があるもの。
ただし、寝込んだり貧血を起こす場合は子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因の場合も。症状がひどくなった場合は、早めに受診しましょう。
生理不順
月経の間隔が25日未満、もしくは39日以上の場合を生理不順といいます。生理不順は不妊の初期原因の一つ。適切な周期で生理が来ない場合は、排卵が起こっていない可能性もあります。
短かすぎても長すぎても婦人科に相談を。
不正出血
生理中以外の出血は、排卵がうまく行われていなかったり、子宮内膜症や子宮筋腫、卵巣や子宮にトラブルがある可能性も。排卵期に起きる少量の出血など病気ではないものもありますが、自己判断せず婦人科で検査をしましょう。
“おりもの” や “かゆみ”
おりものは無色透明で、下着についても薄い黄色程度。濃い黄色や褐色だったり、かゆみや痛みがある場合は、細菌性腟炎やクラミジアなどの疑いも。
放置していると不妊につながる場合もあるので、早めに治療をしましょう。
女性ホルモンの変化で生理が起こります
女性ホルモンのうち卵胞ホルモン(エストロゲン)は子宮内膜を厚くし、黄体ホルモン(プロゲステロン)は子宮内膜を着床しやすく整えます。生理は、この2つのホルモンが入れ替わり働いて起こります。
婦人科のかかりつけ医を持とう
生理のトラブルや排卵しているかどうかなど、何か心配事がある場合には、ためらわずに婦人科を受診しましょう。自治体の無料クーポンを利用したり、子宮がんや卵巣がんの検診も定期的に受けると安心です。この先、閉経までには更年期障害など、女性の体には、一生を通じていろいろな変化やトラブルが発生する可能性があります。
いつでも相談できる婦人科のかかりつけ医を持って!
卵子は老化する? 排卵と妊娠率について
卵子のもとになる卵胞は、女性が胎児のときにすでに体内でつくられています。卵胞の数は、妊娠6ヶ月のときの胎児のころがピークとなり、その後どんどん減っていきます。
思春期になるとホルモンの働きで、この原始卵胞が目覚め始め、卵巣の中で半年ほどの期間をかけて成長し、毎月その中のたった1個だけが成熟期を迎えて排卵されます。それが生理(月経)です。
女性の一生で排卵される卵子は約480個。それ以外の原始卵胞は、1日30~40個、日々消滅していき、閉経前には残り1000個程度になります。
卵子の数は減少していき、1000個程度になると閉経に
卵子のもとである卵胞は、20週の胎児のときがピークで700万個程度。
出生時には約200万個に減ります。さらに日々減り続け、初潮を迎えるころには20~30万個に。
1回の月経周期で約1000個減るともいわれ、卵子の残りが1000個程度になると閉経します。また卵子の質も30代になると落ち、妊娠のしやすさにも関係してきます。
排卵とセックス、年齢別の妊娠率について
妊娠するためには、排卵された卵子が卵管にとどまっている間に、精子と受精して、受精卵となって子宮に着床する必要があります。卵子の寿命は約24時間、精子の寿命は約72時間といわれ、3日に1回以上セックスをしていれば、自然に妊娠をする可能性が高くなります。
最も妊娠しやすいのは、排卵日の2~1日前のセックスというデータもありますが、男性の心身もデリケート。セックスを義務にせず、自然な性生活を。
「卵子の老化」は妊娠率の低下につながります
以前、TV番組でクローズアップされた「卵子の老化」という言葉。卵子が老化するなんて知らなかった!と大きな話題に。人間の体自体が老化するのと同様、卵巣の中の卵子も老化します。具体的にはDNAに損傷が起きたり、うまく細胞分裂ができなくなったり、卵子そのものの数も減っていくので、最終的には妊娠率の低下につながります。
健康な卵子は、内部の核やミトコンドリアが活発な動きをしています。
年齢が高くなると、これらの機能が次第に悪くなり、細胞分裂がうまくできなくなったり、妊娠のしやすさにも影響が出てきます。
どうやって妊娠するの? 大切な3つのステップ
妊娠するためには大きく分けると3つのステップが必要です。
1つ目は、女性の卵巣から健康な卵子が排卵されること。
2つ目は、その卵子が男性の体から射精された健康な精子と出会って受精して受精卵となること。
3つ目は、受精卵が子宮の内側に着床して順調に育つこと。
このどれか一つが欠けても、妊娠することはできません。
妊娠とは、排卵(射精)・受精・着床という一連の流れが、女性の体の中で起こるということ。まさに妊娠は、生命が持つ神秘的な働きなのです。
●妊娠のステップ1(女性):排卵
〇子宮 … 受精卵が着床し、赤ちゃんが育つ場所。子宮も伸びて大きくなります。
〇卵管 … 受精卵を子宮に送る管。受精をし、受精卵が発育する場所でも。
〇卵管采 … 卵巣から排卵された卵子をキャッチして卵管に運びます。
〇卵巣 … 2~3cmの楕円形。出生時に約200万個の原始卵胞があり、卵子に成長します。
月に1回、成熟した卵胞のうち1個の卵子だけが卵巣の壁を破って外に飛び出します。その卵子を卵管の先にある卵管采がキャッチして、卵管に卵子が入ります。卵子がここで生きられるのは24時間ぐらいといわれています。
●妊娠のステップ1(男性):射精
〇精子 … 腟内で射精された精子は、子宮・卵管を通り、卵管膨大部へ。
〇卵管膨大部 … 精子が卵管膨大部に到達すると、卵子を取り囲みます。
〇膣 … 子宮と外側をつなぐ場所。出産時には産道にもなるところです。
1回の射精で、精液に含まれる精子は約1~3億個。卵子と出会える卵管膨大部にたどり着くまでには数十分から1~2時間かかり、その間に精子の数は100~1000個に減ります。精子は3日間程度、受精能力を維持できます。
●妊娠のステップ2:受精
卵管にたどり着いた数百個の精子が、卵子を囲み、卵子の殻である「透明帯」を溶かす酵素を出します。そして、1個の精子が卵子の核に入り、卵子と受精します。
するとほかの精子は中に入ってこられなくなり、死滅します。受精卵は、その後細胞分裂を繰り返しながら卵管から子宮へと移動していきます。
●妊娠のステップ3:着床
受精卵は細胞分裂をしながら、5~7日かけて、子宮にたどり着きます。そのころには受精卵を覆う膜を破って孵化(ふか)をしています。孵化した受精卵が子宮の内側にくっつき、着床できると、妊娠が成立します。
月経周期が28日の人は、最終月経開始日を妊娠0週0日と数えます。約2週間後に排卵日を迎え、受精後5~7日で受精卵は子宮内膜に着床し妊娠が成立すると、このとき妊娠週数は3週に。本来の次の生理予定日には妊娠4週に。
「受精卵」はどうなっていくの?
受精卵は、受精直後から細胞分裂を始めます。約30時間で2つに、約40時間で4分割に、約60時間で8分割に。
卵管を移動しながら受精卵は分裂を繰り返し、受精後5日後ぐらいには、分裂した細胞がお互いにくっつき、胎児や胎盤になる部分ができてきます。
着床後の胎児の大きさは?
〇妊娠1ヶ月 … 0.1mmくらいの大きさ。「胎芽(たいが)」と呼ばれる時期です。
〇妊娠3ヶ月 … いちごくらい。骨が形成され、3頭身になり胎児らしい形になります。
〇妊娠5ヶ月 … りんごくらい。髪の毛や産毛が生え、胎動を感じるようになります。
〇妊娠7ヶ月 … メロンくらい。目、耳、鼻、舌などの器官が完成します。五感も発達。
〇妊娠10ヶ月 … スイカくらい。4頭身で皮下脂肪もつき、いつ生まれてもいい状態に。
35歳以上の妊娠は流産率が上がります
自然流産率の低い20代後半~30代前半でも、10人に1人は流産する可能性があります。35才以上になると一気に流産の確率が跳ね上がり、40才以上の妊娠では約41%が流産するというデータも。
妊娠は「当たり前」ではなく、「奇跡」なのだという認識を持ちましょう。
要チェック!妊活前に知っておきたい検査・知識
いざ、子どもが欲しい!と思ってもすぐに望みどおりにはならないことも。妊娠しにくくなることの原因への対策で今からできることはぜひ取り組んでおいて!
主に女性(一部男性)がしておくべきこと
【女性向け】トキソプラズマの検査
妊娠中は加熱が不十分な肉などには注意をして
加熱処理の不十分な肉や、土やネコのふんなどから感染。免疫が正常に働いている健康な人は、感染しても無症状の人がほとんどで、一度感染すると抗体ができます。
しかし妊娠中に初めて感染すると、赤ちゃんに悪影響が出ることも。血液検査で抗体のチェックを。
【男女どちらも】風疹の検査など
パートナーや周囲にも協力をしてもらいましょう
妊娠初期に母体が風疹にかかると、おなかの中の赤ちゃんに障害が出たり、発達に問題が起こる可能性があることがわかっています。
妊娠中は、風疹の予防接種が受けられないので、妊娠を考えだしたら、パートナーとともに風疹の抗体検査を受けるのがおすすめ。
【女性向け】卵巣の検査など
若い人にもトラブルが増えています
卵巣は、卵子を保存して育てる大切な器官です。卵巣機能不全、卵巣のう腫、卵巣がんなど、以前は40代以降に多かった病気も、最近では若い人にも増えている傾向があります。
生理時の出血が増えたり、生理痛がひどいようなら、早めに医師に相談しましょう。
【女性向け】子宮のトラブルなど
【子宮頸がん】
定期的な健診を受けておくと安心
子宮内膜ががんになるのが「子宮体がん」、産道の一部のがんが「子宮頸がん」。子宮体がんは初期でも不正出血がありますが、子宮頸がんは自覚症状がありません。進行すると子宮摘出や生命にかかわります。早期発見なら完治可能なので、定期健診を忘れずに。
【子宮筋腫】
不妊の原因にもなるので検査と適切な治療を
子宮内にできる子宮筋腫は良性の腫瘍ですが、大きくなったり数が増えたりすると、受精卵が着床しにくくなり不妊の原因にも。
生理時の出血が増えたり、下腹部痛、腰痛、頻尿、便秘、貧血などの症状が出る場合には注意が必要です。ひどくなると腫瘍摘出手術をすることもあります。
【子宮内膜症】
排卵トラブルの原因にもなるので要注意!
子宮の内側にある子宮内膜が、子宮以外の周辺の組織で増殖する病気です。卵管や卵巣の近くにできると、排卵が正しく行われにくくなります。30代以降の女性に多く、激しい生理痛を伴うのが特徴です。放置すると血液が卵巣にたまり、手術が必要になることも。
男女2人で知っておくべきこととは?
妊娠中や赤ちゃんが生まれたあとのことを考えて、調べておくといいこと、今やっておくといいことをぜひパートナーと一緒に知っておきましょう。
出生前診断
パートナーとよく相談をしてから決断を
赤ちゃんの先天性疾患の一部(染色体異常や形態異常など)を調べることができる検査。
超音波検査、クアトロテスト(母体血清マーカー検査)、NIPT(血液検査でわかる新型出生前診断)、羊水検査、絨毛検査などがありますが、母体への負担や、費用、結果をどう受け止めるかなど事前にパートナーとよく考えておいて。
年代別妊娠率
年齢が上がるほどに妊娠率が下がります
統計的に、結婚年齢が20~24才では、子どもを授からない率が5.7%ですが、25~29才で9.3%、30~34才では15.5%、35~39才では29.9%、40~44才では64.5%になります。
体外受精などの不妊治療1回あたりの出産率も30代を過ぎると下がり、45才過ぎの妊娠・出産は稀になるというデータが出ています。
(「女性の結婚年齢別に見た非妊娠率」出典:Menken et al.,Science,1986を改変)
産後の働き方
フレキシブルな考え方で準備をしておくと◎
妊娠して出産をしたら、女性だけでなく男性も育休を取るのか、育児に専念したあとに再就職をするのか…。
住んでいる地域によって保育園の入所倍率なども大きく異なるため、最近は妊娠中から保育園探しを始めることも常識になっています。自分の希望するキャリア、世帯収入や将来設計についても、妊活中にパートナーとよく話して!
産後うつ
どういう状態になるのかを妊娠前から知っておけば安心
近年「産後うつ」が社会問題になっています。産後はホルモンバランスが崩れ、精神的にも不安定な状態に。さらに初めての出産、慣れない育児、授乳やおむつ替えなどで夜も眠れないといった物理的なことも加わり、育児に自信が持てなくなります。
1人で抱え込まず、医師に相談すべき症状であることを知っておきましょう。
体重管理のこと
太りすぎにもやせすぎにも注意が必要!
臨月には子宮や乳房、羊水や胎盤、赤ちゃん、さらに脂肪も増えるので10kg~13kgの体重増加が目安。しかし近年、やせすぎの女性も多く、妊婦の栄養不足が低出生体重児の増加につながることが問題に。低出生体重児は、将来の生活習慣病のリスクが高いことがわかっています。逆に太りすぎると出産時に難産になりやすい傾向も。
なかなか妊娠しないとき
不妊治療をはじめさまざまな選択肢が
不妊治療に進むという選択肢もあります。2022年からは、不妊治療への保険適用がスタートしたので、治療へのハードルが低くなりました。また、里親や養子縁組という選択も。こちらは公的機関がサポートを行っています。
さらに子どもを持たないという選択をしているカップルもたくさんいるので、2人で話をしながら今後について考えてみましょう。
監修/竹内正人先生
イラスト/山本あゆみ 取材・文/長谷川華
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
▼『妊活たまごクラブ』は、妊活に役立つ情報が一冊に詰まった妊活スタートブック



 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い