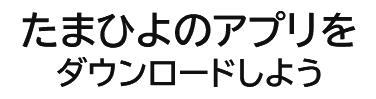「自分はなぜ養子になったんだろう」自分の生い立ちに葛藤する子どもたちを連れてアメリカへ【鮫島医師インタビュー】
生みの親が、特別な事情で育てることのできない子どもを、育ての親が引き取り、法的な親子関係を結んで実子として迎え入れる制度――特別養子縁組。制度がスタートした1988年から支援を始め、現在は全国の産婦人科施設が連携して特別養子縁組支援を行う「あんしん母と子の産婦人科連絡協議会」(以下あんさん協)の代表として、さまざまな支援活動を続ける鮫島浩二先生。
先生は支援のなかで初めて養子当事者である子どもたちの、アメリカホームステイ留学「スターキッズプロジェクト」を企画、実施。
企画した背景や先生の思い、実現までの道のりや子どもたちの様子について聞きました。
子どもたちが一生抱えていく悩み“養子”。枠をはずすにはどうしたらいいか
――「スターキッズプロジェクト」を企画したきっかけを教えてください。
鮫島先生(以下敬称略) “あんさん協”では、どうしても赤ちゃんを育てることができない女性と生まれてきた赤ちゃん、子どもを育てたい夫婦をつなぐお手伝いをしてきました。支援した特別養子縁組の家庭は全国に150組ぐらいいます。その養親さんたちが「星の子の会」という会を作り、年3回程度子どもたちも一緒に集まって交流しています。コロナ禍で集まれない年は“zoom”で顔を合わせたりして、関係を続けてきました。
そうしたなかで、養子の子どもたちが成長して思春期へとさしかかり、心身の変化や悩みが出てくるわけです。誤った情報に触れてしまう前に、産婦人科医としてできることはないかと、数年前から小学校5年生以上を対象に“zoom”女子会で正しい性の知識を伝えてきました。大きな目的は性教育でしたが、見えてきたのは“養子”という自分の生い立ちに悩み、葛藤する姿でした。
親子の間では、養子であることの告知はされていて、両親から愛情深く育てられていても、親から「ほかの人には話さないで」と言われているケースもあります。友だちや仲間、自分の好きな人に養子であることを伝えられない。伝えたらどう思われるだろう。自分はなぜ養子になったのだろう。成長の過程でさまざまな疑問や悩みが沸き起こり、それは一生抱えていくものです。
「星の子の会」で、同じ境遇の子どもたちが小さいときから集まって交流しているけれども、こうした悩みの枠をはずすことは、養子縁組や養子が少ない日本では難しいのではないかと思ったんです。だったら、養子家族がごく自然といるアメリカに行ってみるといいんじゃないかと。養子である自分に向き合って、何か広い視点でとらえられるいい機会になるんじゃないかと考えました。
――思い立ってから、どのようにして実現したのでしょうか。
鮫島 「星の子の会」の子どもたちをアメリカに連れていきたいと考えていたころ、ちょうど大きな病気で入院をしました。復帰してから、この夢はやり残せないと、ある友人に話したんです。そうしたら、その友人から、ユタ州のセントジョージで日本からホームステイを受け入れる仕事をしている方を紹介されました。旅行会社も入ってもらわないとなので、旅行会社に勤めていた友人に50年ぶりくらいに連絡してみたんです。すると、引退しているけれども手伝ってくれるというのでお願いして。次は通訳も必要だな、となったとき、福祉の勉強をしたいとハワイの大学で学生をしている知人が、夏休みに私のクリニックで研修をさせてくれないかと電話してきたので、この子だ!と(笑)。それからも、手伝うよと声をかけてくれる人が集まり、どうやらできそうだとなりました。
――いろんな縁で、とんとん拍子に進んだんですね。子どもたちはどのように募集したのですか?
鮫島 子どもたちには“zoom”でプロジェクトのことを話していて「行きたい人いる?」と聞いたら、どんどん手が挙がって、あわてていたんですよ。企画して1年で実現までこぎつけるとは思っていませんでした。本当に不思議な縁、手助けが次々出てきて…。資金に関しても、支援を申し出てくれる方はいましたが、特定の人に頼るわけにはいかないと思いましたし、単発で終わりにせず、続けていけるしくみにしたいと考えていたので、まずはクラウドファンディングで渡航費の支援を募りました。500万円の目標金額に対し、集まった支援総額は870万円。円安が進みひやひやしましたが、多くの方の支援に救われ、中学生から20代の男女合わせて9人の子どもたちをアメリカへ連れていくことがかないました。
人種の違う子どもがたくさんいる家族のなかで過ごす8日間
――子どもたちはアメリカでどのようなことをしてきたのでしょうか?
鮫島 ホームステイ先として選んだのは、ユタ州のセントジョージという街。私も大学時代、別の街ですがユタ州で留学した経験があり、治安と環境のよさ、そしてクリスチャンが多く、ボランティア精神にあふれ、家庭を大切にする風土はぴったりだと思っていました。
1家庭に2~3人のグループでホームステイ。どの家庭も養子を迎え入れています。人種が違ういろんな子どもがいて、みんな一緒に生活しているんです。しかも養子が1人や2人ではない。自分の子どももいるけど、養子も3人いるよ、という感じ。まず、そうした環境に入って、子どもたちは相当驚いたと思います。
アメリカは、本人や家族、周囲の人々も養子であることにオープンで、自然に打ち解けられています。子どもはみんな神様の子、というキリスト教がベースとなった感覚が普通にあるのでしょう。日本とは大きく違うなと痛切に感じました。
滞在中は、無料で使える教会の施設や大学で英語の授業を受けたり、バスで市内観光をしたり。途中、現地の養子たちも交えて、自分の生い立ちを英語で話し、討論をするフォーラムも開催しました。ほぼ英語で過ごす生活を送ったわけですけれども、出発までの1年近くは、みんな週2回、外国人の宣教師さんのもとで英会話を勉強してきたので、ある程度は準備できていましたね。
帰国して成田に着いても、みんななかなか帰ろうとしなかったですよ。親が迎えに来ているのに、3時間くらい待たせてね(笑)。朝起きたら、ホストファミリーに「おはよう」とハグされる毎日を過ごしてきて、別れ際はみんなハグしていましたよね。家庭の中で過ごすというのはいい選択だったなと思っています。
――違う国の、同じ境遇の子どもとの交流は、かなりインパクトがあるように思います。子どもたちは今回の体験をどのように感じているのでしょう?
鮫島 アメリカでいろんな気づきを得てほしいというのが大きな目的で、支援もしてもらっています。お礼や報告もしたいので、子どもたちには感想文を書いてもらったんだけれども、まあ楽しいことだらけで(笑)。もうちょっと書くことがあるでしょうと、ダメ出しをしているところです。
ただ、今回のアメリカの旅を振り返ってみて、自分の生い立ちについて話す場で、話せなかった子が何人かいたんですよね。みんな同じ立場の人たちなんだけれども、話せない。それだけ、養子であるということは当事者にとって重いテーマなんだなと、感じました。
最後の日はラスベガスのホテルで過ごしたんですが、ホテルのロビーでみんな遅くまで話をしたらしいです。いろんな内輪の話も出てきて、そこでやっと本音が話せたという子もいたようですけれどね…。
アメリカに行く前と比べて、子どもたちの気持ちはずいぶん変わっただろうと思います。それでも、なかなか、うまく表現して書けないんでしょう。
私ももう、あせってすぐに完結することじゃないと、子どもたちがこの先の人生で振り返ったとき何か財産になっているんだろうと、感想文は、ある程度まとまったらで、支援してくださった方々には勘弁してもらおうと思っています。
縁組のそのあとのサポートまで考えてほしい
――養子の子どもたちが、自然な形で自分の気持ちを素直に伝えられる場があるといいなと感じました。
鮫島 私が特別養子縁組に関わるようになって、37年たちます。初期のころと比べると制度は整い、養子縁組のしかたのガイドラインも固まってきました。しかし、養子縁組したあとのケアはまだまだといわざるを得ません。国の援助で、養親さんや養子の子どもたちが交流できる場は少なく、あっても機能していないケースもあります。子どもたちが成長して多感な時期を迎えたとき、本人や家族をサポートする公のしくみも残念ながらありません。
縁組を成立させて終わり、ではなく、次の子育て世代となる養子の子どもたちの成長まで見据えて、国が支援してくれたらと願います。
今回アメリカに行った子どものほかに、私が縁組に関わった子どもはまだ150人います。この子たちの将来を支えるところまで関わることが私の使命だと思っていますし、「スターキッズプロジェクト」が、すべての養子の子どもたちの道を開く支援体制の礎になるようにしたい。2回、3回と今後も続けていきたいですね。
監修・写真提供/鮫島浩二先生 取材・文/茂木奈穂子、たまひよONLINE編集部
「スターキッズプロジェクト」に参加した子どもたちは、帰国後も“LINE”グループでつながり、絆(きずな)を深めているそうです。子どもたちの抱える悩みは単純なものではなく、簡単に解決できるものではないかもしれません。けれど、この旅で「楽しかった」だけではない、生きる糧のようなものを感じ取っているのではないでしょうか。
鮫島浩二先生
PROFILE
産婦人科医。さめじまボンディングクリニック院長。1981年東京医科大学卒業。中山産婦人科クリニック副院長などを経て、2006年さめじまボンディングクリニックを開業。2013年「あんしん母と子の産婦人科連絡協議会」を設立、代表を務める。
●掲載している情報は2024年9月現在のものです。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い