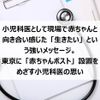赤ちゃんポストに預けられた男の子。「かわいいに決まっとるったい!」の一つ返事で迎え入れたご両親との絆【体験談】
「“ゆりかご”なしで僕の人生は語れないかなと思っています」こう話すのは、“こうのとりのゆりかご(※1)に預けられた子だと公表した宮津航一さん(19歳)。
3歳のときに里子(※2)として宮津家に迎え入れられ、現在は大学生活と並行して、自身の経験を活かした活動やボランティア活動など、充実した毎日を過ごしています。
航一さんは、自らの生い立ちとどのように向き合い、宮津家で家族の絆を築いていったのでしょう?
普通養子縁組(※3)して戸籍上も親子になった父親の美光さん、母親のみどりさんも交え、“ゆりかご”に預けられたころから小学時代までの経緯や印象的なエピソードなどをお聞きしました。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。
航一さんとご両親との出会い
“赤ちゃんポスト”と呼ばれることが多いですが、正しくは“こうのとりのゆりかご”。熊本県の慈恵病院内に設置された“ゆりかご”は、うねりのある細い通路を進むとたどり着きます。
開設初日の2007年5月10日。航一さんは産みの母親の親戚に連れられてここに来ました。
持ち物は靴と数点の衣類のみ。身元がわかるものは何1つありませんでした。
「名前も生年月日も何もわからなかったので、当時の市長に“航一”と命名していただき、戸籍をつくってもらいました。
当時のことはほとんど覚えていませんが、“ゆりかご”の扉は今も記憶にあります。
病院側は赤ちゃんの預け入れを想定していたようで、僕がベッドにちょこんと座っていたことに驚いたみたいです」(航一さん)
その後、航一さんは児童相談所で数ヶ月過ごし、宮津家に迎え入れられます。
ボランティア活動に熱心な宮津家
航一さんのご両親の宮津美光さんとみどりさんご夫婦は、学生時代からボランティア活動を行い、結婚後5人の息子さんに恵まれました。お好み焼き店の経営と子育ての傍ら、生活が乱れた未成年者の自立支援などをしていたことが、里親(※4)になるきっかけでした。
「地域で子どもを見守るボランティアを15年くらいやっていました。そのとき、公園のベンチで寝るような生活をしていた16歳の男の子を保護して、4年間一緒に生活して支援したこともあったね。
あるとき、児童相談所の職員の方から、“里親になってみないか”と声をかけられて、その時に初めて里親制度というものを知りました。以前から自費で支援してたものだから、“あと3人くらい引き受けられるよ”って言いました(笑)」(美光さん)
子どもが5人も6人も一緒みたいな感覚だと笑顔で話す美光さんとみどりさん。航一さんを迎え入れる前も、生活に困っている未成年者を見かけたら自宅に呼び、サポートするのが宮津家の日常でした。
2007年に美光さんは専門里親(※5)、みどりさんは養育里親(※6)として登録します。
「里親登録して何ヶ月かしたころ、3歳の男の子を迎えないかと児童相談所から話が来たんです」(美光さん)
「かわいいに決まっとったい!」一つ返事で航一さんを迎え入れて
「中高生くらいの子を支援しようと張り切ってたものだから、3歳の男の子と聞いてびっくりはしました。でも、“かわいいに決まっとったい!”って一つ返事で引き受けたんです」(みどりさん)
航一さんと初対面したときの印象は、「クルクルの天然パーマで本当にかわいくて。“天使みたい”って思いました」と美光さんとみどりさん。
児童相談所のプレイルームで航一さんと初対面したときのエピソードを、美光さんはこう話します。
「足で漕いで動かす自動車に乗って遊んでいました。普段はほかの子がいるから遊べないようで、夢中になってましたね。
“来てごらん”って呼んで航一をひざの上に抱っこして、“心配せんでいいよ”って伝えて。そのとき“うちで養育するんだな”と覚悟のような気持ちが芽生えました」
美光さんとみどりさんに慣れるまでは、「抱っこしようか」と声をかけても応じず、転んでも泣かない子だったそうです。
「それまで我慢して強く振る舞っていたんでしょうね。初めのうちはとてもお利口さんで。甘えずに1人で頑張っている様子が健気でね。“痛かったら泣いていいんだよ”って声をかけていました」(みどりさん)
触れ合い遊びで親子の関係に変化が!
5人の息子さんの子育て経験から、美光さんとみどりさんは航一さんと一緒におふろに入り、川の字になって寝るという生活を大事にしました。
そして、遊び感覚で触れ合う機会をたくさんつくり、関係性を築いていったと言います。
「抱っこをすると自分が“守られている、大事にされている”ってことが、子どもに伝わると以前から感じていて。航一を1日3回抱っこするようにと息子たちにも伝えました。
妻のおっぱいをくわえさせたり、僕も自分のおっぱいもくわえさせたり(笑)。赤ちゃんみたいに哺乳びんで飲ませることもやったけど、航一はちょっと恥ずかしそうにしていたな」(美光さん)
宮津家に来て1ヶ月ほどすると、航一さんは甘えられるように。抱っこするとひざから降りなくなったそうです。
「エプロンの下で航一を抱っこして“もうすぐ生まれそうだ、生まれた~”なんて言いながら、抱き上げるととても喜んで。
もしかしたら、“ゆりかご”に預けられる前に経験しきれなかった“触れ合い”の楽しさが、この遊びで少し満たされたのかもしれませんね」(みどりさん)
親子の信頼関係が築かれてきた矢先、航一さんに気がかりな様子が表れます。
暗い場所は幼いころから苦手
幼いころの航一さんは、スーパーなどでベビーカーを押すお母さんを見かけるとその場で立ち止まり、“これがお母さんなんだ…”という様子でずっと見たり、暗いところが苦手だったそうです。
「大きくなっても暗い道は苦手です。小さいころの生い立ちが関係してるんじゃないかと両親は言ってるけど、僕もそうなのかなと。
孤独を感じる気がして、怖いなと思うんです。外が暗い時間帯に登下校するときは、いつも父に送迎してもらっていました。
でも、今は自分で車やバイクを運転するようになって、照明で明るくなるから1人で通れるようになりました(笑)」(航一さん)
事実は隠さず自然に伝えて
育ての親が迎え入れた子どもに対して、産みの親が別にいることなどを伝える真実告知。
自分を産んでくれた母親はどんな人で、どこで生まれたのか。赤ちゃんのころはどんな様子だったのか…。“ゆりかご”に預けられる前のことが何もわからなかった航一さんに、美光さんとみどりさんは、どのように真実告知をしたのでしょう?
「航一が4歳くらいのとき、“ゆりかご”のニュースが流れているテレビを観て“僕ここに行ったことがある”と言って。“ゆりかご”のことを覚えていたんです。
嘘はつくべきではないと思ってましたが、児童相談所に相談したり、大学の心理学の先生にアドバイスをもらいました。“嘘をついたら、親子関係が親密になったときに子どもは嘘を見抜く。だから嘘はつかないほうがいいんじゃないか”って。思った通りでした。
そこから、テレビのニュースや新聞で報道されるたびに“出てるよ”って伝えて。そのうち、自分で新聞の切り抜きを始めるようになりました」(美光さん)
テレビを観て“行ったことがある”と話す航一さんにみどりさんは、「“行ったことがあるの? ここで救ってもらったのよ、よかったね”」と声をかけたそうです。
質問するたびに、美光さんやみどりさんは航一さんに答えたと言います。
「血がつながっていないということは何となく気づいてました。改めて聞いたことはなかったんですが、疑問を感じたら質問するとすぐに答えてくれました」(航一さん)
悲しい思い出は生い立ちの授業
小学1年のとき、航一さんは自身の生い立ちをたどる授業で悲しい思いをします。
「赤ちゃんのころの写真がなくて、いちばん上の兄の写真を代用しました。“ゆりかご”より前のことは、両親と一緒に想像しながら綴って…。
周りの子は当たり前のようにあることが、自分だけは“ない”。生い立ちのことで悲しい思いをしたのは、その1つだけかなと記憶しています」(航一さん)
最後の手段として、子どもをゆりかごに預けようとしている方がいるとするなら、何か1つでも子どもに残るものを用意して欲しいと航一さん。
「生まれたときの写真でもいいし、名前の由来や誕生日などを書いたものでもいい。なぜ預けたのか、どんな人に育って欲しいか。そんな少しのメッセージでもあると子どもの気持ちは違うかなと思います」
産みの母親が判明!パズルのピースが埋まっていく…
小学2年のとき、児童相談所の協力で産みの母親のことが判明します。
「実母は僕が生後5ヶ月のとき、交通事故で亡くなっていたことがわかりました。お墓の場所も教えてもらい、父と2人でお墓参りに行って。お墓の周りにある敷石を形見としていくつか持ち帰り、半分は宮津家の納骨堂に納め、もう半分はいただいた実母の写真と一緒に今も自室に置いてあります」(航一さん)
航一さんは天国にいる産みの母親に宛てた手紙を、美光さんはたくさんのお線香を用意してお墓参りに行ったそうです。
「天国のお母さんに手紙がしっかり届くように、墓前にたくさんのお線香を手向けて焚き上げました」(美光さん)
みどりさんは、航一さんが綴った手紙にある計らいをしたそうです。
「航一が書いた手紙に、私が天国のお母さんに成り代わって返事を書いたんです。
“里親の宮津さんのところで元気にしています”と書かれた手紙なら、“よかったね”と返事をして…。
そんなやりとりを何度もしてから、お墓参りに出かけていました」(みどりさん)
産みの母親が事故に遭った場所がわかると、美光さんは居てもたってもいられず、すぐに航一さんを連れ、花を手向けに行ったこともあったそうです。
「ちょうど母の日に近い時期で。航一はその近くで買った、ガラス細工みたいな花を私にプレゼントしてくれて…。うれしかったですね」(みどりさん)
産みの母親のことがわかったとき、航一さんはどのような気持ちになったのでしょう?
「“ゆりかご”に預けられる前の3年間は、パズルで言えばピースが1つ埋まっていない感じでした。小2のとき、全部がわかったわけではなかったんですが、パズルのピースが埋まったと思った瞬間がありました。
これまで4回お墓参りをしてきて、地元の方などに実母の生活の様子などを聞くうちに、ピースはほぼ埋まったかなと思います。
何より、両親が積極的に情報収集する姿勢を見せてくれたり、サポートしてくれたことが大きかったなと。すべて出自(※7)はわかっていませんが、今はもう出自を求める気持ちはないです」
航一さんの気持ちを汲み取って、積極的にかかわってきた美光さんとみどりさん。
これまで航一さんや航一さんのお兄さんたち、30人超の里子とかかわってきた経験から、子育てで大事にしてきたことを伺うと、
「お子さんが小さいときは、ママもパパも楽しんで一緒に遊ぶのが、いちばんいいかもしれないなと感じます。小さいときに結んだ絆は、お互いにずっと続くんじゃないかなと。私自身、ずっと覚えていますから」とみどりさん。
忙しいと一緒に遊ぶ時間がつくれず、お子さんの寝顔に向かって“ごめんね”とつぶやく方もいらっしゃることでしょう。
そんなときは、寝起きや食事、おふろの時間など、生活しながら楽しくかかわるひとときを過ごしてみてもいいのかもしれませんね。
次回は中学時代以降の様子や、“こうのとりのゆりかご出身”と公表した理由などをお伝えします。
写真提供/宮津航一さん 取材・文/茶畑美治子
●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。
●記事の内容は2023年3月の情報で、現在と異なる場合があります。
こうのとりのゆりかご※1 どうしてもわが子を育てられないと悩む実親などが、その子の命と未来を守るために最終的な手段として子どもを預けられる施設。(熊本県・慈恵病院のHPを参照)
里子※2 さまざまな事情から、実親などが他者に預けて養育してもらう子どものこと。
普通養子縁組※3 親(育ての親)と養子の同意で成立する縁組。実親との法律上の関係は残る。(厚生労働省のHPを参照)
里親※4 さまざまな事情から、実親と暮らすことができない子どもを預かり、自宅に迎え入れて養育する人のこと。
専門里親※5 虐待を受けたり、非行などの問題を抱える子どもや、身体障害児や知的障害児など、専門的なケアが必要な子どもを預かり、養育する里親のこと。(公益財団法人全国里親会のHPを参照)
養育里親※6 養子縁組を目的とせずに、実親と暮らすことができない子どもを預かり、養育する里親のこと。(公益財団法人全国里親会のHPを参照)
出自(しゅつじ)※7 誰から生まれ、どこで育ったかなど、自分の出どころのこと。
ファミリーホーム※8 小規模住居型児童養育事業。さまざまな事情から、家庭的な環境で暮らせない子どもを養育経験が豊富な里親や児童養護施設職員などがその家庭に迎え入れて養育すること。5~6人まで受け入れ可能。(厚生労働省と日本ファミリーホーム協議会のHPを参照)
プロフィール
宮津航一さん
2003年11月5日生まれ。熊本県立大学2年生。ふるさと元気子ども食堂代表、熊本県警察本部長委嘱少年サポーター、熊本県立大学学生団体「PUKRUN」部長、熊本県ファミリーホーム協議会事務局・HP担当、ふるさと元気ドレッシングHP運用責任者。
宮津美光さん・みどりさん
学生時代から社会福祉にかかわるボランティア活動に従事。お好み焼き店経営を経て、2011年に宮津ファミリーホーム(※8)開設(熊本県内初)。現在までで30人超の里子を迎え入れる。少年の健全育成・自立支援などの活動を行うNPO法人シティエンジェルスくまもと(2020年解散)代表や熊本県里親協議会事務局長を経て、現在は熊本県ファミリーホーム協議会副会長、熊本県少年警察ボランティア連絡協議会副会長(熊本東地区同会会長)熊本県公安委員会委嘱少年指導委員 。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い