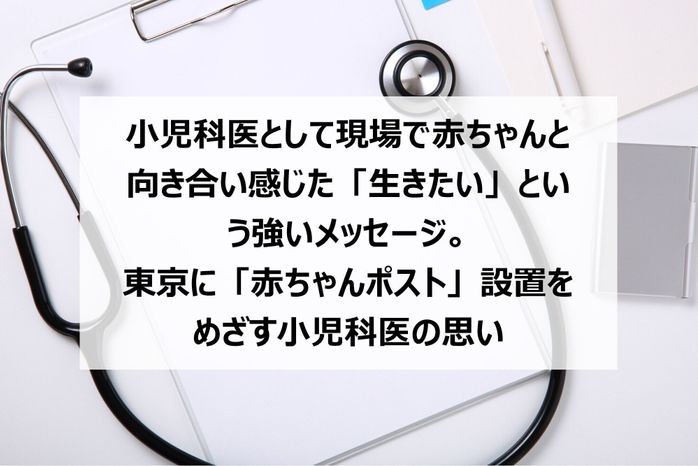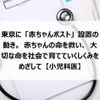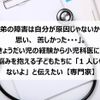小児科医として現場で赤ちゃんと向き合い感じた「生きたい」という強いメッセージ。東京に「赤ちゃんポスト」設置をめざす小児科医の思い
親が育てられない赤ちゃんを匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」。アメリカでは100カ所以上に「ベビーボックス」として設置されているそうです。日本では熊本の慈恵病院の施設「こうのとりのゆりかご」が知られていますが、東京でも設置に向けての動きがあります。都内の湾岸エリアにて5院、ベトナム・ハノイにて1院の合計6院を運営する医療法人社団「モルゲンロート」の小暮裕之理事長は2024年秋に産婦人科医院を開業予定であり、そこに「赤ちゃんポスト」を設置する考えです。2022年11月には、小池百合子都知事と面談し、赤ちゃんポスト事業を始めるにあたり、東京都への要望書を手渡しました。小暮先生に「赤ちゃんポスト」設置についての考えや課題について聞きました。
減少しない赤ちゃんの虐待死。赤ちゃんの生きる権利を守りたい
――「赤ちゃんポスト」を設置しようと考えた理由を教えてください。
小暮先生(以下敬称略) 私は10年ほど小児科医として現場で子どもたちの命と向き合ってきました。NICUに勤務していたときには、手のひらほどの500〜600gという小ささで生まれた赤ちゃんたちや、重い持病を持って生まれた赤ちゃんたちに出会いました。そこで学んだのは、彼らの生命力です。NICUでは残念ながらなくなってしまう赤ちゃんもいますが、どの赤ちゃんも必死に生きて、生きることをあきらめる赤ちゃんはいません。
小児科病棟に勤務していたときには、虐待を受けて、極度の栄養失調や脱水などでガリガリにやせ、“骨と皮”のような状態で救急に運ばれてくる子どものケアにも携わりました。彼らの治療に携わる中でも、子どもの生きたい気持ちの強さを感じました。
しかし、乳児の置き去りや虐待死、虐待を受ける子どもの数は、年々増加の一途をたどっています。とくに、生後0日で虐待死してしまう赤ちゃんは、毎月3人とも言われています(※)。15年前に、熊本の慈恵病院で「こうのとりのゆりかご」と呼ばれる保護施設ができ、これまでに約160人の赤ちゃんの命が救われてきました。小児科医として、虐待や置き去りによって亡くなってしまう赤ちゃんの命を、毎月1人でも2人でも助けたい。同時に母親も殺人犯にならなくてすむように「赤ちゃんポスト」が必要だと考えています。
重要なのは、養子縁組制度を広く認知してもらうこと
――「安易な育児放棄につながる」、「子どもの出自を知る権利が守られていない」、といった批判についてはどう考えますか。
小暮 これまで、子どもの虐待死の対策として2018年ころから「妊娠期から支援を必要とする養育者への支援の強化」が行われてきました。予期しない妊娠などの困りごとがある妊婦さんが相談できる機関や、特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが、とくに必要と認められる妊婦)の支援が行われてきましたが、赤ちゃんがトイレに置き去りにされたり、ゴミ箱に遺棄されてしまう、といった虐待死は減っていません。虐待死の数が減っていないのであれば、養育者の支援以外の対策を考える必要があると思います。
「出自を知る権利」とは、親が匿名で赤ちゃんを預けられるシステムのため、親の名前がわからないということですが・・・そもそも生きられなければ出自を知る権利もないだろう、と思うんです。僕は小児科医です。小児科医は子どもの気持ちの代弁者でもあります。なので、赤ちゃんの命を最優先に考えます。小児科医として多くの子どもに接してきた経験から、まだ言葉を話さず泣くだけの赤ちゃんですが、言わんとしていることをなんとなく感じ取るときがあります。それは「生きたい」というメッセージ。彼らの代弁者として、赤ちゃんたちが生きる権利をいちばん大切にしたいと考えています。
――「赤ちゃんポスト」で守られた赤ちゃんの命は、どのように育てられるのでしょうか。
小暮 乳児院で保護されたり、児童養護施設で育てられたり、特別養子縁組制度や里親制度によって家庭に迎え入れられたりします。私は赤ちゃんの虐待死を予防するために最も重要なのは、育ての親へつなげる特別養子縁組制度や里親制度を妊婦さんに認知してもらうことだと考えています。予期せず妊娠し、出産しても育てられない場合に悩むわけですから・・・。養子縁組制度が一般的になり、育ての親がなんとか見つかるしくみがもっと出来上がって支援がつながる社会に早くなってほしいと思います。それがあれば、「赤ちゃんポスト」に預けなくて済みます。現在はその段階まで社会が進んでいないので、赤ちゃんの命を1人でも多く守るためにも「赤ちゃんポスト」は必要だと考えています。
「安易な育児放棄につながる」という批判もありますが、養子縁組によって育てたい人と育てられない人をマッチングすれば、助かる命がある、そのことに大きな意味があると考えます。子どもができないけれどほしい場合に、近年は不妊治療を受ける人が増えています。同時に特別養子縁組の選択肢ももっと一般的になればいいと思います。そのためには、東京に「赤ちゃんポスト」が設置される前後からの官民連携での取り組みが必要だと考えています。
「赤ちゃんの命が助かる場所」の思いを込めて
――現在は、2024年秋の開設に向けて、どのようなことをしているのでしょうか?
小暮 「こうのとりのゆりかご」は熊本県の慈恵病院の名称なので、私たちはそこから多く学ばせていただきつつ、東京という地域に合った取組・施設を作り上げていきたいと考えています。私たちが設置を予定している「赤ちゃんポスト」の名称を2023年3月31日までホームページで募集しています。子どもの生命を守り、お母さんを守るための前向きな施設にするために、“赤ちゃんの命が助かる場所”とイメージがわくような名前になればと思っています。
お話・監修/小暮裕之先生 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
複雑な家庭環境や、経済的困窮があるなか、予期せぬ妊娠をしてしまった場合に、相談したり支援を受けられることを知らない人も多いのだとか。「『赤ちゃんポスト』は小さな命を守り、虐待によって母親を犯罪者にしないためにも必要な取り組み」と小暮先生は話します。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。
(※)厚生労働省「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第18次報告)」
小暮裕之先生(こぐれひろゆき)
PROFILE
医療法人社団「モルゲンロート」理事長。1978年、埼玉県春日部市生まれ。2003年に独協医科大学を卒業、千葉の総合病院や東京都内の国立病院で小児科医として勤務。10年に江東区内に小児科や内科などを有するクリニックを開業し、現在は都内の湾岸エリアにて5院、ベトナム・ハノイにて1院の合計6院を運営する。
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い