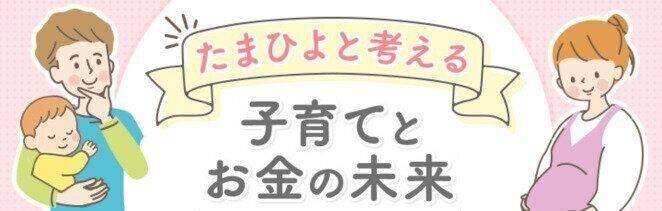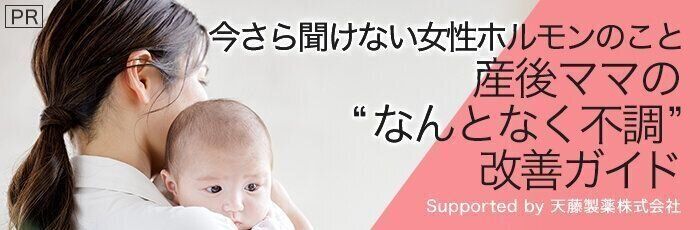不妊治療しても授かれない現実、あまりにも知られていない妊娠のリミットを産科医が語る
「もっと早く知っておきたかった」。
子どもを授かるには、どうしても年齢という壁があります。
たまひよは、産むと選択した女性も、産まないという選択をした女性も、どちらの選択も尊重したいと考えて記事を配信してきましたが、不妊の記事をとりあげるたびに「もっと早く知りたかった」という声が届きます。
「選択したつもりではなかった」「学校で教えてほしかった」「男性も知るべきと思った」。
いつか子どもを授かりたいお思った時のために、もっと前から知っておきたいことを特集としてお届けします。
特集「授かるチカラ」 連載「産科医・齊藤 英和 授かるチカラとは」第1回
ライフプランを考えるときに役立てて
みなさん、こんにちは。平成最後の3月から、梅ヶ丘産婦人科で不妊治療を行っている齊藤です。その前は国立成育医療研究センターで治療を行っていましたが、以前も今も、私が不妊治療で患者さんを診ているときに、多くの患者さんが「妊娠適齢期があることを知らなかった。それでも不妊治療を受ければ、絶対に妊娠するものだと思っていた。」という声を耳にします。
わたしも、いろいろなところで妊娠適齢期に関し情報発信してきましたが、依然、妊娠適齢期の知識を知らない方が多いと感じています。
そこで、今回、たまひよONLINEを通して、妊娠出産に関わる正しい知識・妊娠適齢期を知っていただき、ご自分のライフプランを考えるときに役立てていただきたいと思っています。
数字が語る、若いほど妊娠可能という現実
不妊治療を受けたら、誰でも必ず赤ちゃんを授かることができると思う方がいるかもしれませんが、現実には不妊治療を受けても、患者さん全員が妊娠することはできないのが現実です。私たち不妊治療医は患者の治療時点で、その患者さんが持っている最大限の妊孕性(にんようせい・妊娠する能力)を引き出せるように治療しますが、その妊孕力は年齢に伴い下がってきています。
20代の間でも、20代前半と比較するとすでに後半から少しずつ妊孕力が下がります。妊娠するには絶対的に年齢が若い方が有利ですし、また、不妊治療を受けたとしても、妊娠する確率は若いほど高いといえます。
この妊娠の確率が低下する一つの根拠として、この図1をみてください。
年齢とAMH値の図
これは女性の各年齢でのAMH値の年齢変化を示しています。AMHとは、アンチミューラリアンホルモンのことで、小さなサイズの卵胞から分泌されることから、貯蓄されている卵子の数に比例すると考えられています。この図では、各年齢のAMHの平均値と中央値が記載されています。つまり、平均値で見ると、やはり若い20代が高く、加齢とともに低下することがわかります。このことから、年齢が高くなると、卵子の数も減り、妊娠しにくくなるのもうなずけると思います。
高年齢でも妊娠できる。でも個人差が大きい
さらに、ここで注目していただきたいのは、標準偏差が大きい、つまり個人差が大きいということです。同じ25歳でも、標準偏差において下限にいる人の卵子の数は、47歳の人の平均値の数と同じ程度しかないことになります。また、44歳で標準偏差の上限の人だと、36歳の人と同じぐらいの卵子の数を持っていることになります。持っている卵子数は個人差が大きく、年齢だけでは推測できないということです。
たとえば、44歳で妊娠できた人がいたとしても、その人が44歳で妊娠したということであって、すべての44歳が妊娠できるのではないということです。妊娠できる人もいれば、そうでない人もいるということです。ですから、高齢の女性タレントが妊娠・出産したという話題が上がることがありますが、それを聞いた20~30代の女性が「自分も高齢出産で大丈夫」と思うのは、やや軽率だと言えるでしょう。
また、一般的に標準偏差というのは、標準偏差の上限より上、または標準偏差の下限より下に、それぞれ15%程度いると言われています。そのことを考慮すると、たとえば、20代の後半でも、かなり妊娠が厳しい人がいることが推測されます。つまり、人が持っている平均の卵子数は、年齢とともに減少しますが、その個人差は大きく、若くて少ない人もいれば、高齢でも数多く持っている人もいる、ということです。これは、ぜひ知っておいていただきたい大切なことです。そして、妊娠を望む方であれば、「妊娠するには、なるべく早く妊娠時期を計画するほうがよい」ということも頭に入れておくことも大切です。
妊娠経過や出産時のトラブルを知ってほしい
さて、ここまでお伝えした内容は、病気を持っていない健康な方が、加齢によって妊孕性(にんようせい)が低下するという説明です。これに病気が加わると、さらに妊孕性は低下する可能性があります。特に、生殖年齢における加齢にともなって増えてくる子宮内膜症は、大きく妊孕性に影響します。
もう一つ、妊娠する確率以外で、年齢が及ぼす大切な影響についてお話ししておきましょう。それは妊娠した後、すなわち妊娠中・出産時・子育て中に関する年齢が係るリスクです。
高齢になるほど妊娠中の流産、前置胎盤、妊娠高血圧症候群といった病気が増えます。妊娠中は、どの年代の人でもきちんと妊婦定期健診を受ける必要がありますが、特に年齢の高い人ほど、より自分や赤ちゃんの状態に気を配る必要があります。
出産時では、胎盤機能不全や胎児切迫仮死が起こりやすくなり、帝王切開術による分娩となることもあるので、年齢が高くなるほど母体や胎児の状態管理をしっかりしていくことが大切になります。
乳がん・子宮がんを回避して、元気に育児を
次から次へと追い立てるようになりますが、出産したあとの子育ての時期では親の健康や体力が重要となります。健康に関していえば、25歳を超えると急速に増えてくる癌があります。それは乳がん、子宮がんです。このような癌にかかりながら、妊娠し、子育てしていくことは大変になります。
女性の年齢別のがん患者数
図2のように、この病気の罹患確率は年齢とともに上昇しますが、他の胃がん・大腸がん・肺がんなどとは異なり、妊娠・出産・育児の適齢期初期から増加し始めるのです。これらの病気にかかる可能性が低い時期に妊娠・出産・育児をするのは、リスク回避の方法として、とても大切なことになります。
もちろん、高齢で妊娠・出産し、健康に子育てされている方もたくさんいます。この記事では、そういう方を非難するためではなく、あとから知った方の「もっと早く知りたかった」という声をなくしたいために、あえて厳しい数字を書いています。
いろいろな情報を知ってご自分の仕事や妊娠・出産・育児に関するライフプランニングしてみてはいかがでしょうか? (文/齊藤英和 撮影/古谷利幸 構成/関川香織)
齊藤英和(さいとう・ひでかず)
プロフィール
元国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 副センター長。現在梅が丘産婦人科ARTセンター長。長年、不妊治療の現場に携わっていく中で、初診される患者の年齢がどんどん上がってくることに危機感を抱き、大学などで加齢による妊娠力の低下や、高齢出産のリスクについての啓発活動を始める。
著書に「妊活バイブル」(共著・講談社)、「『産む』と『働く』の教科書」(共著・講談社)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い