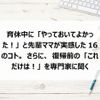4ヶ月の育休を取得した、MBSアナウンサー西 靖さんの“おそるおそる育休”で得た4つの気づき
男性の育休取得が奨励される中、「たまひよ」アプリユーザーは育休取得についてどう思っているのでしょう。アンケート結果とともに、MBS放送のアナウンサ―で、4ヶ月の育休を経験した西靖さんのお話をお届けします。
育休を取得してほしい? 取得してほしくない? そのホンネとは
ユーザーへ育休取得について聞いてみました。
Q:あなたは、パパ(ママ)に育休を取得してほしいと思いますか?
取得してほしい 56.4%
取得してほしくない 11.1%
どちらでもない 29.1%
その他 3.4%
「取得してほしい」が約60%で半数以上、「どちらでもない」が約30%となりました。
みんなのコメントを見てみると、初めての子育てへの不安や育休中に一緒に子育てできたことへの感謝の気持ちが見えてきました。
■夫がいないと回らない
「現在、夫に育休取得してもらっていますが、理由は2人じゃないと生活が回らないからです。ただ、夫の育休が明けた後の生活が不安です…」(たぬき)
■ずっと1人は不安
「1人でずっと子育てすると、余裕がなくなって子どもに優しくできなくなるのが怖いです。うちは1人目から子どもが家にいるときは、なるべく親が2人いるようにしています」(家ねこ)
■一緒に子育て
「パパに育休を取ってもらったことで、両親で一緒に子育てして、親になれたと思いました」(そふぃ~)
■3ヶ月の育休をとってくれた夫に感謝
「双子の育児はパパ無しでは大変でした。うちは3ヶ月の育休でしたが、本当はもっと欲しかったです。夫の会社は男社会で、理解が薄かったので3ヶ月だけでもとってくれた夫に感謝です」(ともきち)
■2人の育児には夫の協力は必須
「1人目のお世話をしながら2人目の子育てが大変になることが目に見えているので、2人目が産まれたら、できれば育休を取って欲しいです」(のん)
■夫の復帰後が心配
「1~2週間取得してもらいたいです。理由は、里帰りしないので、やはり少し慣れるまでは助けてもらいたいという気持ちがあります。でも夫に1年とか長く育休を取得してほしくはなくて、1年後復帰する際に生活リズムが上手く戻らず体調を壊さないか、職場で浦島太郎状態になって苦労しないか、という懸念があるためです」(やな)
■早く帰る努力を!
「稼いでほしいから育休取得しなくてもいいと思っています。ただ、早く帰る努力をしてほしいです」(しょーこ)
『休むぞ』ではなく『楽しくがんばるぞ』で育休に入ってほしい!
3人のお子さんのパパであり、4ヶ月の育休の経験を綴った『おそるおそる育休』の著者である西靖さんに、育休を取得したきっかけと、育休で得た気づきについてお話を伺いました。
「私は三男が生まれたときに初めて育児休業を取得しました。理由は大きく3つほど。『3人目』『コロナ禍』『仕事の踊り場』です。
三男が生まれるタイミングで4歳と2歳の2人の男の子がいました。ここに3人目が加わることを想像すると、これはちょっと妻1人ではしんどいのではないか、というのが1つめ。
三男誕生は2021年で、コロナ禍真っただ中。できるだけ人に会わないように、家から出ないように、という息苦しい時期でしたから、実家の両親に来てもらうとか、同級生のおうちに遊びに行く、といったことが気軽にできない空気が横溢していました。家族でなんとかしなくちゃならないなら、私が休むのがいいかな、というのが2つめ。
もう1つの理由は、自分の仕事のことです。ちょうど三男が生まれるまえに、自分が担当していた月~金のニュース番組が終了しました。ざっくり言うと、暇になったんです。アナウンサーとしては残念な状況であり、正念場でもありますが、『あ、休むなら今かも』というタイミングでもありました。アナウンサーとして30年近くがむしゃらに働いてきましたが、ちょっと違う経験を積むよい機会なのでは、という思いもありましたね。
妻は専業主婦なので、家のことは自分が責任をもってやり遂げたい、という思いを強くもっているようで、長男のときも次男のときも、私に仕事を休んでほしいとは言いませんでした。3人目が生まれるときも私の育休は頭になかったようで、『仕事を休もうと思う』と言うと、ちょっとびっくりしていました。『ありがたいけど…、休んで大丈夫なの?』という感じ。私の会社での立場とか、キャリアへの影響とか、収入とか、いろいろ気がかりだったんだと思います。
私の育休は、長男次男の幼稚園の夏休みとまるまる重なったので、その間は毎日のように虫取り網を持って、2人を連れて公園に蝉取りに出かけていました。コロナ禍でも子どもたちは外に遊びに行きたがるし、ずっと家族が家で顔を突き合わせていると、ぶつからなくてもいいことでぶつかってぎくしゃくするし、蝉取りは子どもの世話と夫婦の程よい距離間を生み出す、ちょうどいい着地点でしたね。50歳にもなって真っ黒に日焼けして蝉取りが上達するというのは、なかなか感慨深いことでした。
あと、キッチンでのスキルが多少は上がったと思います! お湯を沸かすくらいしかできなかったのに、育休期間以降はワンパターンとはいえ、朝ご飯は私が作るのが基本になっています。自分が作ったものを家族がパクパク食べてくれるって、すごくうれしいですね。逆に食べ残されたり、箸が進まない様子を見たりすると、すごく残念な気持ちになります。ご飯を作る人の気持ちがわかるようになっただけでも大収穫ですよ。
ただ、中には育休を「育児休暇」だと思っているパパたちがいるようですが、正確には「育児休業」。勤め仕事は休むけれど、休暇じゃありません。新生児を迎えた家のなかには、職場よりもっとたいへんなこともたくさんありますから、私もくたくたに疲れましたけど、たくさんの気づきを与えてくれた時間でもありました。せっかくいつもと違う役割をやれるのだから、『休むぞ』ではなく『楽しくがんばるぞ』で育休に入ってほしいと思います」(西靖さん)
西靖さんの“おそるおそる育休”で得たたくさんの気づきとは
●奮闘している妻への共感者としての役割
母親だけでは手が回らない状況への現実的な対応として、男性育休はすごく有効です。でも、私の場合、それと同等かそれ以上に、奮闘している妻への共感者としての役割が大きかったように思います。「しんどいね。よし、俺がやるよ」と「しんどいね。ちょっとお茶入れるからダラダラお話しよう」の両方が大事なんだなと。
●感情の逃げ場、やり過ごす知恵、親を休む時間、そんな工夫も大事
ユーザーの声で、『1人でずっと子育てすると、余裕がなくなって子どもに優しくできなくなるのが怖いです』というご意見がありますね。その怖さ、わかります! 親というのは無条件に子どもを愛するもの、というのを絶対的な前提にするような雰囲気が一部にあって、これがけっこう親を心理的に縛っちゃうんですよね。でも、親だって人間、たまにはイライラします。これは育休とは関係ありませんが、自分の子どもに対してネガティブな感情を持ってしまうことを自分で禁じてしまうと、自分を余計に追い込んでしまう気がします。「感情の逃げ場」「やり過ごす知恵」「親を休む時間」、そんな工夫も大事ですよね!
●普段感じていなかった自分の余裕のなさにドキッ
週末パパでいたときは、なんだかんだ言って、メンタル的には余裕があったように思います。子どもがおもちゃを片付けなくても、ご飯のときにずっとお話していてぜんぜん箸が動いてなくても、まあ、穏やかに諭すことができます。妻がイライラしていたら「まあそんなにきつく言わなくても」なんて言う。そんな私の余裕に、妻の方はよけいイライラするっていう感じ。
でも、育休をとって家族と一緒の時間が圧倒的に増えると、余裕がなくなって、私の方もやっぱりイライラしちゃうことがありました。我が子に対してイライラした感情を抱いている自分に、ドキッとしたのを覚えています。
●違う場所に身を置き、違う視点から物事を眺めることの大事さを実感
職場でもいろいろ変化はあります。「子どもが熱を出したようなので早退していいですか?」と部下に言われたとき、「仕事はなんとかするから、すぐに行ってあげて」ともちろん言うわけですけど、たぶん、以前とは「言い方」が違うと思います。なんか、熱を出して不安そうにしている子どもの顔が思い浮かぶんですよね。仕事でいろんなニュースを扱いますが、見え方、感じ方が変わったりもします。いったん違う場所に身を置き、違う視点から物事を眺めるって、すごく大事なんだと実感しています。
以前に比べ、育休取得に対するハードルが低くなりつつあるのかと感じています。男性の育休取得はもちろん、さらに子育てしやすい職場や社会環境になるといいですね。
(取材・文/メディア・ビュー 酒井範子)
西靖さん
PROFILE)
MBSアナウンサー。相愛大学客員教授。神戸女学院大学特別客員教授。6歳、4歳、1歳の3児のパパ。『ちちんぷいぷい』、報道番組『VOICE』、『ミント!』といった人気番組の司会やキャスターを務め、現在は同社アナウンスセンター長。テレビ『西乃風ブラン堂』ナレーション( https://www.mbs.jp/nishinokazebrand/ )、ラジオ『辺境ラジオ』(https://www.mbs1179.com/henkyo/)『厳選!月イチジャーナル』(https://www.mbs1179.com/ichi/)を担当。2021年に4ヶ月間の育児休業を取得。その日々を綴った書籍『おそるおそる育休』をミシマ社から2023年2月に刊行(https://mishimasha.com/books/9784909394828/)。他に『西靖の60日間世界一周旅の軌跡』(ぴあ)、『地球を一周! せかいのこども』(朝日新聞出版)など著書多数。

※文中のコメントは「たまひよ」アプリユーザーから集めた体験談を再編集したものです。
※調査は2023年1月実施の「まいにちのたまひよ」アプリユーザーに実施ししたものです(有効回答数443人)
※記事の内容は2023年5月の情報で、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い