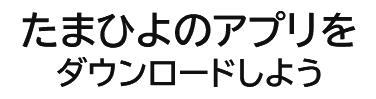母であり、医師であり、小説家。「女性だからと、やりたいことをあきらめなくていい」【小説家・南杏子】

編集者を経て医師となり、さらには小説家としても活躍する南杏子さん、1人の娘さんの母親でもあります。イギリスで出産後に日本で医学部に学士編入し医師免許を取り、現在は医師と小説家の二つで活躍をしています。たまひよONLINEでは、新刊「いのちの十字路」を出された南さんに、子育てのことや女性が働くということ、そして命について、読者に届けたい思いなどを聞きました。
医学部編入は、夫が背中を押してくれたことがきっかけ
――社会人のスタートは雑誌編集の仕事をしていたという南さん。医師の仕事に興味を持ったのはなぜでしょうか。
南さん(以下敬称略) 当時は育児雑誌の編集部で、赤ちゃんの離乳食、病気、たとえば弱視やおむつかぶれなどのテーマをよく担当していました。働いている中で、雑誌のイベントに参加されたお母さんたちから、病気のことについて質問を受けることがよくあったんです。そこできちんと答えられないもどかしさがあり、もっと詳しく知りたい、勉強したいという漠然とした気持ちがありました。子どものころから人のしくみなどに興味があって、人体図鑑がボロボロになるまでよく読んでいるようなところがあったので、気になっていたのかもしれません。でも医療職は自分とは縁のない世界だと思っていました。
――そこから実際に医師を志すきっかけになったことがあったのでしょうか?
南 結婚後、31歳のときに夫の留学についてイギリスに渡りました。妊娠して産休と育休を合わせて取得している間のことでした。そして、イギリスにいる間にアロマセラピストの資格を取るための勉強をしました。その課程に解剖生理学の授業があり、すごく面白いなと思ったんです。子どものころから興味があった人体の神秘に触れて、さらに学びたいと思うようになりました。これがきっかけだと思います。
そんな折、私が医学に興味があると知った夫が、日本で医学部の学士入学の制度ができたという日本の新聞記事を見つけ、「挑戦してみたら」と言ってくれました。学士入学とは、4年制大学を出た人が医学部の2年生から入れる制度です。学費もローンで支払えるし、試験科目も社会人向けの内容だったので、チャレンジしてみようと思いました。
イギリスでは30代、40代の大学生ってごく当たり前にいるんです。海外に住んだことで「社会に出てからも大学に入り直したり勉強をすることに年齢って関係ないんだ」と刺激を受けたこともあったと思います。
仕事と子育てをしながら、医学部編入受験の準備
――イギリスから帰国し、医学部受験の準備期間、仕事はどうしたんですか?
南 帰国したのは娘が1歳になるころで育休も終わる時期でした。医学部入試にチャレンジしても合格するかどうかわからないですから、落ちたら編集の仕事を続けようと思い、仕事をしながら準備しました。学士入学の試験科目は一般入試とは異なり、英語と日本語の論文、面接でした。面接で「世の中をよくしたい」ようなことを言ったら、試験官であった当時の医学部長に「そんな大所高所からのご意見ではねえ・・・」と言われて、きっと落ちたなと思ったんです(笑)。でも、運よく合格して33歳から医学生となりました。入学後、医学部で5年間学び、国家試験を受け、38歳で医師となりました。
――医師をめざして医学部に通い始めた南さんを、家族はどんなふうに応援してくれていましたか?
南 私の実家の隣に住んでいたので、困ったときの娘の世話は両親にも頼りました。父と母は、最初は「何をしでかしたんだろう、何を始めちゃったんだろう」くらいの感じで見ていたと思います。私の母は専業主婦で父はサラリーマンという、50年前の日本家庭を絵に描いたような夫婦でした。私のことも当然、専業主婦になって夫につくす女性に育てるつもりでいたんだと思います。だから私が大学を出て「働く」と言ったときにも「何を考えているんだ」という感じでびっくりしていました。腰かけ程度に働いてすぐ飽きるだろうと思っていたようです。だから次に「医学部に行く」と言ったときもかなり驚いていました。
私は両親が予想していた方向には進まなかったかもしれませんが、最終的にはおもしろがってくれていたように思います。娘のこともすごくかわいがってくれました。
女性だけが仕事と子育ての両立を問われるのは残念
――南さんは38歳で医師として働き始めてから、子育てを夫婦でどんなふうに分担していましたか?
南 できるほうがやる、という感じでした。娘が0歳のときから、イギリスでは当たり前のように利用されていた保育所を利用しましたし、どうしてもというときには実家の両親にお願いできたので恵まれた環境だったと思います。
ただ、このような取材で女性に仕事と子育ての両立が問われる世の中に、私はすごく違和感があります。結婚している男性に「仕事と子育ての両立」のような質問をするでしょうか。子育ては女性がするのが当然、という価値観が前提になっている感じがします。
アイスランドでは、育休制度は父親6カ月、母親6カ月、さらに父母共有の6週間が取得でき、その間は政府から給料の80%が支払われるそうです。ならば、子どもを作らなきゃ損、とばかりに出生率も上がってきたと聞きました。日本は、女性が働いていると見ればすぐに「子育てはどうしているか」と聞かれるのは、いまだに残念な状況だなと思います。
――南さんが子育てをしていた30年ほど前は、まだ「女性は家庭」という考え方が多かったかもしれませんが、南さんと夫は家事も子育ても一緒にしていたのでしょうか?
南 そうです。結婚相手としてそういう考え方ができない人は論外でした。夫とは大学時代のサークルで知り合ったんですが、夫の実家はシングルマザーだったんです。物心ついたときから外で働くのも家事をするのも母親1人という状況で育った夫は、家の中のことは家族全員で分担するという感覚だったんだと思います。だから自分が父親になっても、家事も育児もするのが当たり前のようでした。私が仕事をするのも当たり前と思っていたようで、結婚して私が「仕事を辞める」と言ったときには「なんで?」と言われました。当時の夫の勤務地である北海道に渡った際の会話です。すぐに夫は、私の転職先として地元の出版社を見つけてくれました。
夫は子育てに関してとりわけ熱意を見せてくれましたので、子どものケアは保育所も利用しながら、2人でやりくりしました。家事は得意なほうが得意なことをやればいいという考えでした。
医師として小説家として伝えたいこと
――南さんの医師としてのキャリアの最初は大学病院や市中病院で急性期医療に携わられ、その後、高齢者中心の病院に勤務されているそうです。違いはどんなことでしょうか。
南 急性期医療は、病気の治療やリハビリテーションによって社会復帰することをめざす考え方です。私が急性期医療に携わっているときは、人の病気やけがを治して、その人が1分1秒でも長く生きることをめざしていました。
でも、終末期医療に携わるようになって、そうじゃない医療の考え方に気づかされました。たとえば高齢者で足が弱ってきた人に厳しいリハビリをしたら、食欲をなくして食べられなくなってしまうこともあります。無理をして食物を気管につまらせて誤えん性肺炎にかかり、最悪の場合亡くなってしまう、そういうことも起こりえます。終末期医療は、その人がニコニコして穏やかに暮らして、心地よく生き、最後に向かう命を支える医療です。
――医師として働くなかで、どんなことにやりがいを感じていますか? また、どんな医師でありたいですか?
南 だれかの役に立つところ、「ありがとう」と言ってもらえるところにやりがいを感じます。それは今も変わっていません。
現在は高齢者中心の病院に勤務しているので、患者さん、とくに高齢者の人たちを笑顔にできるような、患者さんの家族にも「よかった」と思ってもらえるような医療をしたいと考えています。
――医師として、母として、いのちについてどのような思いを持っていますか?
南 かけがえのないものです。医師であろうとなかろうと、それは変わらないと思います。
――新刊「いのちの十字路」では、医師たちが患者をみるときにこんなにも熱意や優しさを持っていると伝わってきます。
南 私も子どもを産んだときは医師ではありませんでした。医師に対して誤解や偏見もあったし、ちょっとこわかったんです。「こんなこと聞いたら怒られるんじゃないか」と聞きたいことを遠慮したこともたくさんありました。
でも、医師になってみると実はそうじゃない、という発見がありました。自分が患者として受診する際には見えなかったことでした。両方の立場を知っている私だからこそ伝えられることがあると思うし、医師に向けられる誤解をといていきたいです。医師たちは患者や家族と一緒に、病気を真ん中にして闘っていくつもりでいるんだということを伝えたいです。
お話/南杏子さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
南さんの娘さんは眼科医となったそうです。「『ママにできるなら私もできる』と言われました」と笑う南さん。自分の人生も家族も大切にしてきた南さんの生き方は、働く親のロールモデルとなるのではないでしょうか。
●記事の内容は2023年5月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
南杏子さん(みなみきょうこ)
PROFILE
1961年徳島県生まれ。日本女子大学卒。出版社勤務を経て、東海大学医学部に学士編入し、卒業後、慶應義塾大学病院老年内科などで勤務する。2016年『サイレント・ブレス』でデビュー。
いのちの十字路
吉永小百合主演映画『いのちの停車場』原作続編。老老介護、ヤングケアラー、8050問題・・・それぞれの家庭の事情に寄り添おうと奮闘する訪問診療所の若き医師とその仲間たちの姿を描く。南杏子著/1650 円(幻冬舎)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い