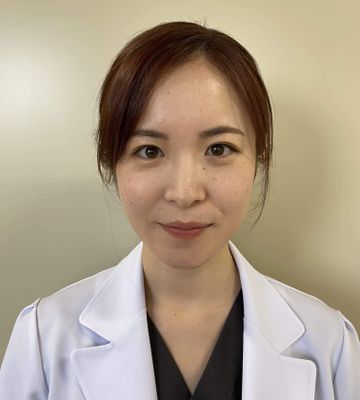妊娠35週、胎児の心拍が落ち緊急帝王切開で出産。直後に「染色体異常の可能性がある」と告げられる【プラダー・ウィリー症候群 】
プラダー・ウィリー症候群(以下、PWS)という、染色体異常の難病を知っていますか。肥満、糖尿病、低身長、性腺の機能不全、発達の遅れ、筋肉の低緊張などが見られ、発症率は出生児の約1万5000人に1人と考えられています。
長野県で3人の子どもを育てている綾さんの第1子、樹(いつき)くん(7歳・小学校2年生)は、生まれて4週間後にPWSと診断されました。
樹くんに寄り添ってきた7年間について、綾さんに聞きました。インタビューの前編です。
妊娠35週目の朝、「胎児の心拍が落ちているから」と、緊急で帝王切開に
結婚して1年目に樹くんを妊娠した綾さん。妊娠中はとくに変わったことはなく、順調だと感じていたそうです。
「初めての妊娠ですべてが初体験。健診で問題ないと言われているんだから、順調なんだと思っていました。2人目、3人目の妊娠を経験したあとで思い起こせば、1人目の樹のときは胎動を感じにくかったように思います。でも、当時は胎動を感じるのは初めてのこと。こういうものなんだろうと思ったし、ましてや胎児に大きな病気があるなんて、ほんの少しも考えていませんでした」(綾さん)
綾さんの穏やかな妊娠生活が激変したのは、妊娠8カ月、28週目のときでした。
「地元の総合病院で産むつもりで、健診に通っていました。そのときも普通に健診で受診したんです。ところが、『切迫早産になっているからこのまま入院してください』って先生に言われて、何が何だかわからないまま入院しました。2017年8月末のことです。
2週間安静にして様子を見ていたのですが、胎児の心拍が弱くなっているということで、長野県立こども病院(以下、こども病院)に緊急搬送されることになったんです。
『え?何がどうなっているの??』と、私はまたもやわけがわからないまま、救急車で搬送されました。救急車に乗ったのは初めての経験でした。
おなかの子に何かあったんだろうか、ちゃんと生まれてくるんだろうかと、不安でいっぱいに。総合病院からこども病院は車で10分くらいの距離ですが、とても長く感じました」(綾さん)
こども病院で診察を受けるも、心拍が弱くなる原因はわからず、胎児の心拍を注意深く観察することになりました。
「朝起きたらおなかにモニターを付け、赤ちゃんの心拍を確認してから朝食をとるのがルーティンで、同室のママたちもみんな同じようにしていました。
35週目だった10月6日の朝、私だけいつまでもモニターをはずしてもらえず、朝ごはんを食べられないまま。どうしたんだろうなあ、おなかがすいたなあと思っていたら、担当医が飛び込んできて、『おなかの赤ちゃんの心拍が落ちてしまうことが増えているので、今日、緊急帝王切開で出産します』って!
こども病院では『37週目までは頑張っておなかの中で育てよう』という説明を受けていて、11月になってから出産の予定でした。
『え?今から出産するの?!』と、私は今度も気持ちが追いつかないまま、緊急帝王切開で出産しました。
生まれてきた子は、泣き声をあまり上げませんでした。しかも対面させてもらったわが子は、体がむくんでいるのが私にもわかり、手足をだら~んとしています。でも、生まれたばかりの赤ちゃんを見るのは初めてだから、そういうものなのかなと思ったし、無事に生まれてきてくれたことの喜びと、帝王切開の疲れで、深くは考えていなかったんです」(綾さん)
絶望感で泣きはらしたあとPWSの子を育てる人のSNSを見つけ、希望の光が
綾さんが出産後の処置を受けていたころ、夫は医師からある説明を受けていました。
「夫は、筋緊張の低下は染色体異常の赤ちゃんに典型的な症状だということと、染色体に異常がある可能性があるから、すぐに検査するということを告げられたそうです。
やっとわが子に会え、一番うれしい日になるはずの出産当日に、異常があるかもしれないから検査をすると言われるなんて・・・。ショックが大きすぎて、夫が帰ったあと病室でずっと泣いていました」(綾さん)
綾さんは妊娠中、赤ちゃんの健康のために、いろいろなことに気をつけていたと言います。
「私はお酒を飲むのが大好きなんですが、お酒はもちろんやめましたし、妊娠中、生ものやカフェインも避けていました。胎児に悪い影響が出そうなものはできるだけ排除しようと、われながら頑張っていたんです。それなのに、生まれてきた息子は染色体に異常があるかもしれないなんて・・・。どうしようもない無力感に襲われました。
なぜうちの子にそんな病気があるの?悲しくてつらくて、涙がいつまでも止まりませんでした」(綾さん)
検査結果が出るのは4週間後でしたが、医師からPWSの可能性があることを告げられていました。
PWSは、新生児期の筋緊張低下と哺乳障害、幼児期からの過食と肥満、発達の遅れ、低身長、性腺の機能不全などを特徴する難病です。
「病室で泣きながら、PWSについてスマホで検索したら、すごく太った女の子の写真が最初に現れました。こんなふうになっちゃう病気なの!?と、ものすごくショックを受けました。調べれば調べるほど、不安になることしか出てこないんです。これ以上落ち込めないというほど落ち込みました」(綾さん)
もっと身近な情報がほしいと考えた綾さんは、PWSの子どもを育てている人のSNSを探してみました。
「PWSの小学生の男の子のママのインスタを見つけたんです。写真もたくさんアップされていて、普通の小学生の男の子でした。もちろんいろいろな努力をされていると思いますが、そのママが書かれている子育ての様子を読むにつれ、少しずつ前向きな気持ちになっていきました。
翌日、NICUにいる樹に会いに行ったとき、とても素直な気持ちで『かわいい』と思えました。そして、『この子と生きていこう、ずっと支えていこう』と、決心できました」(綾さん)
吸う力がすごく弱く、搾乳した母乳を鼻からチューブで流すケアが退院後も必要
4週間後に出た結果は、予想どおりPWSでした。
「樹は筋肉の低緊張に加えて、哺乳障害、停留精巣、目の色素が薄い、首の腫瘍などいろいろな心配事がありました。
乳首を吸う力がなく、哺乳びんでも飲めません。鼻から胃に挿入したチューブを使った経管栄養じゃないと栄養がとれないので、搾乳した母乳をチューブから流していました。
私は出産の9日後に退院したのですが、樹が退院できたのは11月28日。生まれてから1カ月半近くたってからです。その間、私は自宅で3時間おきに搾乳しては冷凍し、翌日に1日分の母乳を持って樹の元へ。これを毎日続けました」(綾さん)
退院後も経管栄養が必要だったため、樹くんの退院前に、綾さんは2日間入院して経管栄養の練習をしました。
「鼻からチューブを入れるケアを家族ができるようにならないと、樹は退院できないと、医師から説明を受けました。1日でも早く樹と一緒に暮らしたかったら、看護師さんから指導を受け、経管栄養のケアをスムーズにできるようになるために頑張りました。2日間の練習で合格をもらい、やっと樹を家に連れて帰ることができたときは、本当にうれしかったです。
看護師さんがいない中で行う経管栄養のケアは、毎回緊張の連続。夜も3~4時間ごとに母乳を流す必要があったので、まとまって眠れる時間はありませんでした。でも、樹が栄養をとるにはこの方法しかないので、必死になって毎日行っていました」(綾さん)
母乳がたくさん出ているのに、一度もおっぱいからは飲ませられなかった
哺乳びんで飲めるようになるためのリハビリを、樹くんは入院中から行っていました。
「生後すぐから、理学療法士さんの指導の下、口まわりを刺激するリハビリを行いました。母乳を湿らせた脱脂綿を樹の唇にちょんちょんと当てたり、私の指で樹の唇を刺激したり。そのおかげもあって、生後5カ月ごろ経管栄養を卒業して、哺乳びんで飲めるようになったんです!
それはとてもうれしいことなんですが、とうとう1回もおっぱいから直接授乳することはできませんでした。
私は母乳の出がよかったようで、樹は吸う力が弱いから、誤えんするリスクが高いと先生から言われたからです。しかたないことだと理解はしていましたが、やっぱりせつなかったです」(綾さん)
幼稚園でたくさんの刺激を受け、少しずつだけど着実に成長しているのを感じる
PWSの子どもは、歩行開始までの発達が遅めという特徴があります。
「樹は首がなかなかすわらず、首がすわったのは7カ月のとき。ほぼ同時に寝返りができるようになりました。はいはいはずりばいしかできず、つかまり立ちをしたのは1歳6カ月。最初の一歩が出たのは2歳になる直前でした。
一般的な成長のスピードから比べたらゆっくりですが、樹なりに成長すればいいと見守りました。
年少クラスで幼稚園に入園したとき、言葉はまだ単語をつなげて話す感じでしたが、園生活が始まったらあっという間に二語文に。同年代の子どもたちから受ける刺激ってすごい!と感激しました。
樹は筋力が弱いこともあり、年少クラスのときは、お友だちと同じようにできないことがいろいろありました。でも、先生方が樹のペースで身のまわりのことをこなすように促してくださったおかげで、年中・年長と学年が上がるに従い、みんなと同じようにできることが増えていきました。そんな樹の姿を見るのは、私にとって大きな喜びでした」(綾さん)
PWSの子どもは食べ過ぎると肥満になりやすく、糖尿病などのリスクが高まるため、食事の管理がとても重要になります。家庭での食事はもちろん、幼稚園や小学校の給食のカロリー制限も必要です。綾さんはさまざまな工夫でそれを乗り越えていきました。
【市川先生より】PWSの子どもの発達はゆっくりめだけれど、本人のペースでできることが増えていきます
PWSの症状は年齢ごとに異なります。乳児期早期は、筋緊張の低下や哺乳不良のために経管栄養が必要なことが多いですが、幼児期以降は食欲亢進が進んで過食が出現したり、過食がコントロールできなかったりすると肥満が進行します。
また、乳幼児期は言葉や運動の発達がゆっくりで、まわりと比べてあせってしまうこともありますが、必ず本人のペースでできることが増えていきます。PWSのお子さんはほめられることが大好きなので、「できた」という結果だけではなく、できなかったときも「頑張った」過程をたくさんほめて、成功体験を増やしていってもらいたいですね。
お話・写真提供/綾さん 監修/市川加波先生 取材・文/東裕美、たまひよONLINE編集部
ほんの少しの可能性も考えていなかった染色体異常の病気を告げられ、「むなしさと悲しみで心がいっぱいになった」と話す綾さん。たくさん泣いたあと、樹くんを支えていこうと気持ちを切り替えました。
インタビューの後編は、PWSの子どもにとってとても重要な食事の管理や、現在の生活などについてです。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。
市川加波先生(いちかわかなみ)
PROFILE
信州大学医学部卒業。信州大学小児医学教室 医員。内分泌グループ所属。同グループが2011年に発足した、PWSと診断されたお子さんを長期支援するためのPWSプロジェクトにて、PWS小児患者のフォローアップを担当。
●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。
●記事の内容は2025年9月の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い