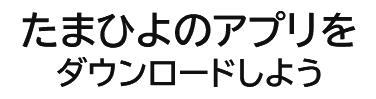ダウン症の娘の子育ては「笑わせたもん勝ち!」。毎日「お母さんは有香ちゃんが好きよ」と伝え続けた【アマチュア落語家・村上有香】
兵庫県に住む村上喜美子さん。ひとり娘の有香さんは、生後1カ月でダウン症候群(以下、ダウン症)と診断されました。現在25歳になった有香さんは、高齢者デイサービスで働くかたわら詩人、そしてアマチュア落語家としても活動しています。喜美子さんに、有香さんの出産時のことや乳幼児期の育児の様子について聞きました。全2回のインタビューの前編です。
羊水過多で入院後、37週で破水し出産に。産声を上げなかった娘
1999年、喜美子さんは結婚10年後に待望の赤ちゃんを授かりました。妊娠経過は順調でしたが、予定日の2カ月前の妊婦健診で羊水が多いことがわかります。早産にならないよう安静が必要だったため、健診に通っていた大学病院にそのまま入院することになりました。
「大学病院に入院して35週に入ったころ、医師から『羊水が多いことで1つ考えられるのは染色体異常。でも赤ちゃんに今のところ悪いところは見つかりません。すごく元気です。万一に備えて出産には小児科医も立ち会います』と話がありました。その夜、『染色体異常ってどんな病気になるのかな?』と考えたら少し不安になって泣けましたが、まさか現実になるとは考えていませんでした」(喜美子さん)
入院して安静に過ごしていた喜美子さんでしたが、予定日まであと3週間という11月中旬のある日、突然の出来事にみまわれます。
「病院のベッドで昼食をとっていたら、突然『バーン!』という何かが爆発したみたいな音と共に、体が浮くような衝撃を受けたんです。何が起こったのかわかりませんでした」(喜美子さん)
診察の結果は破水。急きょ出産することになり、2時間後に女の子の赤ちゃんが生まれました。
「赤ちゃんは産声を上げずに静かに生まれ、あわただしく処置室に連れて行かれました。赤ちゃんの顔をちらっと見せてもらったとき少し違和感があり、ダウン症のある子に似ているかも…と思いました」(喜美子さん)
分娩室の外で待っていた夫の雄一さん(仮名)は、赤ちゃんを取り上げた医師から「ダウン症の兆候があります」と告げられます。雄一さんは、驚き、ショックを受けましたが、出産直後の喜美子さんにはそのことは伝えませんでした。
「赤ちゃんと対面したのは、出産の翌日。赤ちゃんは保育器の中で眠っていました。首のうしろがむくんでいて、普通の赤ちゃんと違う感じがしました。
その一方、夫の両親や母が面会に来てくれて、写真を見て『おめでとう』『元気そうでよかった』と声をかけてくれました」(喜美子さん)
無意識のうちに偏見をもっていたことに気づいた
出産3日後の昼過ぎ、喜美子さん夫妻は、小児科の医師と看護師たちと面談し「詳しい検査結果を待ってみないとわかりませんが、ほぼダウン症でしょう」という話を聞きました。
「当時ダウン症のことをほとんど知らなかった私は大きなショックを受けました。どう育てていったらいいんだろう、一生懸命育ててもどんな人なのかわからないまま終わるのかな?結婚できないのかな?親亡きあとはどうなるんだろう?と、生まれたばかりなのに先の先まで考えてしまったのです」(喜美子さん)
ある日突然、赤ちゃんに障害がある、と聞いた喜美子さんは戸惑い、これまでの自分の過ごしてきた年月をふり返りました。
「有香を産むまで、私自身、障害に対して偏見がないと思っていました。でも出産3日後におそらくダウン症があると告知され『大変なことになった』と負の感情がわき上がってきたんです。それで、自分には偏見がなかったのではなく自分ごとでなかっただけだったと気づきました。
おなかの子が生まれたら、あんなことをしたい、こんなことをしたいと夢を描いていたことも、自分中心のことばかりだった、と反省しました。また、人の悲しみに無関心だったことも、いくつも思い出しました。
大変な生活になると思い込んだ私は夫に『望むなら離婚してもいい』と切り出しました。すると夫は『僕は逃げない。これからは本当に支え合ってやっていこう。明るく生活していこう』と言いました。これまでの自分の生き方を振り返り、考え方を見直した時期だったと思います」(喜美子さん)
喜美子さんは、出産後に多くの人に励ましを受けましたが、なかでも夫の母の言葉が心に残っていると言います。
「夫の母は私に『胸を張って堂々と生きるように!喜美ちゃんが1番大変だけど、私たちも側面からバックアップするから。今度、有香ちゃんの誕生祝いを盛大にしましょう!』と元気づけてくれました。その言葉に深い愛情を感じ『先を明るく見て頑張ろう!』と、心を入れ替えられたと思います。
『有香を授かったからこそ、このことを成せた』と言える人生にする、と自分自身に誓いました。友人たちも、有香の誕生を喜び温かい言葉をかけてくれ、周囲の人たちの優しさに支えられました」(喜美子さん)
検査の結果、ダウン症候群との診断。心臓の手術も受け・・・
生後2週間ほどで有香さんは退院。親子3人での生活が始まりました。
「夫と私は『有香を心の底から喜んで受け入れるために自分たちの価値観を変えていかなければならない』と話し合っていたのですが、そんな大げさな問題ではありませんでした。
気がついたら、ただのかわいいだけの赤ちゃんになっていました。私たちを変えたのは有香の力です」(喜美子さん)
検査の結果、正式に有香さんにダウン症があると診断されたのは、生後1カ月ごろのことでした。また、有香さんにはダウン症の合併症として、心室中隔欠損(しんしつちゅうかくけっそん)という病気がありました。
「有香は生まれてすぐに心臓に小さな穴が開いているとわかりましたが、自然にふさがることもあるから経過観察しましょう、とのことで退院になりました。1歳くらいになっても体が大きくならなかったので、こども病院で調べてもらうことになりました。すると、当初の診断より穴が大きいことと数が多いことがわかりすぐに手術したほうがいいということになりました。
有香は1歳半で手術を受け、無事成功。1週間ほどで退院し、その後は経過観察のために現在まで毎年診察を受けています」(喜美子さん)
生後2カ月から療育に通う。モットーは「笑わせたもん勝ち!」
喜美子さんは有香さんが生後2カ月になったころから、療育に通い始めます。
「地域の保健師さんの紹介で、こども家庭センターで開催されていた個別の親子教室に通い始めました。市内で生まれたダウン症のある赤ちゃんのほとんどはその教室に通います。こども家庭センターではそのほかに集団の親子教室や言語聴覚士による個別指導もありました。
親子教室に通い始めてまず最初に先生(専門医)から教わったのは『この子は“ダウン症の赤ちゃん”ではない。この子は村上有香で、彼女にはダウン症がある』という捉え方。そして育児は『笑わせたもん勝ち!』だということ。この言葉はそれ以来私の育児の指針になりました。教室では、ダウン症の赤ちゃんの子育てで気をつける基本的なことと自信をもたせる育て方などの指導を受けました。早い段階でこのように指導してもらえたことは、その後の有香の心と体の発達の両面でもとても大きかったと思います。また、私自身も親として多くの学びを得て、成長させてもらえました」(喜美子さん)
「教室では、赤ちゃんの発達の様子に合わせ、哺乳力(ミルクを吸う力)を高める口腔内マッサージや、抱っこのしかた、寝返りのしかたなどの指導を受けました。
おすわりができるようになると追視(目で物を追う)の練習、型はめの練習、色の識別など発達に合わせて課題が出されました。
私は先生の指導をヒントに、有香が遊びながらいろんなことに気づいたり、遊ぶことが訓練になるおもちゃをたくさん手作りしました」(喜美子さん)
有香さんはいろいろなおもちゃで遊びながら、少しずつ手の使い方などが上手になっていきました。
「たとえば、ペットボトルに棒をさして遊ぶおもちゃでは、最初はペットボトルを置いたまま片手でやっていてうまくさせませんでしたが、もう片方の手で持ったほうがさしやすいと気づき、さらに、ペットボトルを握った手の指先を口の部分に添えると簡単にさせると気づきました。遊びながら少しずつ手の使い方を覚え空間の認識ができるようになっていきました。そして、ペットボトルの口に入ったときには『はいった』、逆さまにして落としたときには『おちた』と声をかけていたら、有香も自分の行動に合わせて『はいった』『おちた』と言うようになりました。
『まんま』の次にしゃべるようになった意味のある言葉がこの2つです。
棒さしで遊ぶようになってしばらくたったある日、『ジュースのパックにさしてあるストローを抜いて自分でさしなおす』ということを何回も繰り返すようになりました。こんなに小さい穴にストローをさせるということに驚きました」(喜美子さん)
有香さんは2歳8カ月ごろから言語聴覚士による指導を受け、さらに言葉の力が伸びました。
「言語聴覚士の先生が有香の言葉の盤石な土台を作ってくださいました。先生の指導のおかげで、有香の言葉の力はとても伸びたと思います。また指導に付き添うことで私自身も『コミュニケーション』の大切さを学びました。コミュニケーションがなければ言葉は育ちません。また、子どもの学びには遊びの要素が欠かせないこと、発達に遅れのある子どもには、『遊びを教える必要がある』ということも学びました。
『否定しないことが大切』と赤ちゃん時代から教わっていましたが、否定とは大きなことではなく、日常のささいな言葉であることも学びました。
たとえば、有香が赤いものを指して『あお』と言ったとき、私は『青じゃない、赤』と言っていました。でも先生は『赤ね』と正しいことだけを伝えるのです。この『青じゃない』が否定と気づき、それ以後は余計な言葉をつけたさないように、肯定文で伝えることに取り組みました。
そして、私が子育てで何よりも大切にしていたのは『お母さんは有香ちゃんが好きよ』と日に何回も伝えることでした。『愛されている』と感じることで、自信をもち、人とかかわる楽しさを知ってほしかったからです」(喜美子さん)
お話・写真提供/村上喜美子さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
ダウン症のある子どもは一般的に言葉の発達がゆっくりと言われますが、有香さんは2歳ごろから言葉を話し始めたのだそうです。インタビューの後編では、有香さん自身がダウン症であることを自覚し受容する過程や、詩人やアマチュア落語家として活動する現在までのことについて聞きます。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。
●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。
●記事の内容は2025年11月当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
「弱いはつよい」
ダウン症の詩人・村上有香が9歳から20歳までにつづった詩66編を収録。素直でユニークな言葉が、読む人の心に優しく響く。絵はダウン症の画家・伊藤美憂が担当。村上有香・文、伊藤美憂・絵/1760円(風鳴舎)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い