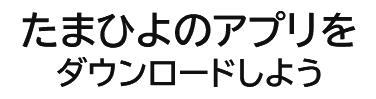第1子を病気でなくし、この子の分まで人生を生きるという思い。44歳で作家デビュー【直木賞作家・窪美澄】
『夜に星を放つ』(文藝春秋)で第167回直木賞を受賞した、作家の窪美澄さん(56)。2009年、40代で作家デビューした窪さんはデビュー前から「たまごクラブ」「ひよこクラブ」のライターとしても活躍していました。仕事と子育ての両立や自身の離婚も経験してきたという窪さんに、ライター時代のことや小説家デビューのきっかけなどについて話を聞きました。
子育てにとらわれていた私に友人が仕事をすすめてくれた
――小説家デビューする前はライターの仕事をしていたそうですが、始めたきっかけはどんなことでしたか?
窪 私は第1子を生後18日のとき病気でなくしてしまった経験があり、第2子の子育てがすごく怖かったんです。この子は健康で生きていかれるんだろうか、と不安を抱えながら、ささいなことも心配してばかりいました。その様子を見ていた友人が、私があまりにも子育てに集中しすぎているのを心配して、妊娠前に広告制作会社に勤めていた私に、「文章が書けるならライターをやってみない?」って声をかけてくれました。それで子どもが生後3カ月くらいから、少しずつライターの仕事を始めました。
経済的な事情ももちろんありましたが、友人の誘いに自分でも「子どもに集中し過ぎている」と気づかされ、仕事をしたほうがいいかもと思い始めました。それに、1人目の子が生きられなかった分の人生を生きなくちゃいけないな、という思いもありました。子育てと仕事と忙しくなるけど、ちょっと自分にハッパをかけて「両立してやってみよう」と思い直すきっかけを、その友人がくれたのだと思います。
それからの子育ては、とにかくこの子が生きていればOK!というスタンスでした。もちろん食事のマナーや人への態度などはうるさく言っていましたが、最終的には人に迷惑をかけなければある程度のことはいいでしょう、という感じで、子どもにあまり多くを求めなかったことが、息子の性格にもあっていたようです。
――「たまごクラブ」「ひよこクラブ」でもライターとして活躍していたそうですね。
窪 はい。「たまごクラブ」、「ひよこクラブ」、「たまひよムック」などの記事を書いていました。初めにたまごクラブのお仕事をするようになったのは、私が編集部に飛び込み営業に行ってからです。それまで雑誌のライターはしていなかったのですが、広告制作会社に勤務していたときに文章を書く仕事はしていたんですね。第2子出産後、妊娠中に通っていたマタニティスイミングの先生の本を作っているタイミングだったので、その本のゲラを編集部に持ち込んだんです。そしたら「じゃあ来週から取材に行ける?」と言われ、そこからライターとして仕事をするようになりました。
――「たまごクラブ」「ひよこクラブ」のライター時代、印象に残っているエピソードはありますか?
窪 ある企画で、産後に病院から実家に帰るまでの流れを紹介する記事がありました。赤ちゃんのお世話をしながら車に乗せて、家に帰るまでをリポートする内容で、実際に出産して退院する新米ママに密着取材をしたんです。ママと新生児ちゃんがママの実家についたら、お母さんがママのために食事を用意していたんですね。にんじんサラダと貝のお吸いものとのり巻きといった、産後の体にとても配慮されたメニューだったんですけど、それを私や撮影スタッフにも用意してくださっていたんです。メニューもそうですが味も忘れていません。私の人生のベスト3に入るくらいおいしい食事でした。産後のママのことを思いやるお母さんの気持ちがその料理に込められている気がして、涙が出るほど感動して、とても印象に残っています。
子どもの大学費用のために小説を書き始めた
――その後、44才で作家デビューしたきっかけは?
窪 『ミクマリ』で新潮社の女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞し、小説家デビューしたのは、子どもが中学3年生のときでした。その後、子どもが高校に入った年に夫と別居をし、後に離婚をしたんですが、そもそも私が小説家を目指したのは、息子を大学に行かせるお金が欲しかったからです。
彼の志望は理系の大学で文系より学費がかかるので、ライターの収入だけでは心もとないな、というのがあり、ライターの仕事をもっと増やすか、少し違うことを書いてみようかなと思って、小説を書き始めました。デビューしてから3年くらいは、ライターと小説家を兼業する状態が続きました。当時は本当に忙しかったです。2〜3時間のこま切れ睡眠で起きたら書く、という感じで。ライターと小説という異なるジャンルの文章を書いているので頭の中がぐちゃぐちゃでしたね。それでも、子どもの大学費用のためになんとか頑張っていました。
――「たまごクラブ」「ひよこクラブ」の取材を通して、小説の作品のテーマにしたいと考えるようなできごとはありましたか?
窪 取材を重ねるたびに、妊娠や出産は全然当たり前のことではなくて、正常な妊娠経過をたどり、健康な赤ちゃんが生まれるのは奇跡みたいなことなんだ、と確認させられていたと感じます。
どんなに子どもが欲しくても妊娠や出産に至らないケースも多々あります。ドクターや体験者の方からお話を聞いて、命は奇跡であることが身にしみました。小説において直接的にそのエピソードを書くことはありませんが、そんな命の奇跡を描いて行きたいな、という思いはあります。
デビュー作の『ミクマリ』は助産院が舞台なんですが、それは私自身の助産院での出産体験がベースになっています。
ママ・パパ・子どもだけではない、さまざまな家族の形を描きたい
――窪さんの作品にはいろんな形の家族が登場しますが、何か作品のモデルや、ヒントにしていることはありますか?
窪 とくにモデルにして書いたことはないです。作品のテーマはそのとき目についた情報や感じていることがもとになっていると思います。ただそんな情報の中でも「両親が2人いて子どもがいるのが正しい家族の形」みたいなイメージを目にしたときに、それに対して「それは違うでしょ」と反発心が生まれます。だから小説の中では、そうじゃない、いろんな家族の形を積極的に描きたい気持ちがあります。
――今後の作品でテーマにしたいと考えているのはどんなことですか?
窪 これまで妊娠・出産・子育てといった、女性のライフサイクルを書いてきたので、いずれは女性のライフステージの最後を飾る更年期の体と心について物語にできたらいいなと思っています。妊娠・出産にかかわってきたものとして、女性の体の最後までつき合いたいという思いがあります。
お話/窪美澄さん、写真提供/文藝春秋 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
自分の経験や仕事を通して、命の奇跡を実感してきたという窪さん。その思いがあるからこそ、今作で喪失を抱える主人公たちが1歩を踏み出し、未来を生きることへの希望が感じられるのでしょう。
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
窪美澄さん(くぼみすみ)
PROFILE
1965年東京都生まれ。フリーランスの編集ライターとして、女性の健康を主なテーマに書籍、雑誌等で活動。2009年『ミクマリ』で女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。受賞作を収録した『ふがいない僕は空を見た』で11年、山本周五郎賞受賞。12年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞、19年『トリニティ』で織田作之助賞を受賞。ほか、『水やりはいつも深夜だけど』『いる いない みらい』『朔が満ちる』など著書多数。
夜に星を放つ
かけがえのない人間関係を失い傷ついた者たちが、再び誰かと心を通わせることができるのかを問いかける短編集。第167回直木賞受賞作。窪美澄著/1540円(文藝春秋)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い