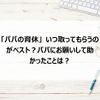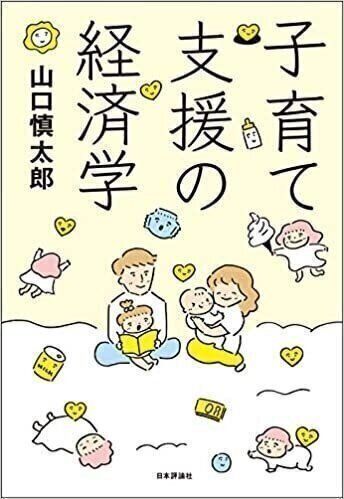妻の75.0%が満足 妻が妊娠したら夫がとるべき行動とは?【専門家】
世界の中でも充実しているといわれる日本の男性育休制度ですが、取得率も認知度もまだまだ低いのが現状です。国は2025年までに取得率30%をめざし、制度改正を検討しています。男性育休が広まると家族はどう変わるのか取材しました。
育休取得は経済面にも幸福度にも好影響
2020年月に公表した「たまひよ妊娠・出産白書2021」では、出産にあたり夫が休みを取った妻の75%は満足している、という結果が出ました。男性が育休取得をすることは、家族の将来にとって経済面や幸福度でもメリットがあるといわれます。家族の経済学を研究している東京大学大学院経済学研究科教授の山口慎太郎先生に聞きました。
「ある経済学の研究では、家族と一緒に過ごす時間の長さが幸福度に影響するとわかっています。内閣府の調査でも、昨年のステイホーム期間を通して家族の重要性を意識するようになった、という価値観の変化がわかりました」(山口先生)
男性が育休を取得し夫婦で一緒に子育てすることは、家族としてどのように生きるのが幸せなのかを考える、大きなチャンスになるといえるようです。育休は子どもが1才(場合によっては1才2カ月)になるまで取得可能です。「ぜひ今からでも取得してみるといいと思います。現行法では育休中の経済補償が100%ではないので、家計の不安を感じるかもしれませんが、男性育休が普及し、女性が正社員の職を離れずに済めば、離職した場合と比べ生涯年収で数千万円以上の差があることも。これは家計にとって大きなメリットです」(山口先生)
育休取得は人生を変え、出生率にも影響する
男性の育休取得が進むと出生率にも変化はあるのでしょうか。
「カナダのケベック州で実施された育休改革で、男性の育休取得率は21%から75%に上昇、平均育休期間も5週間に増加しました。その後の追跡調査では、育休取得の3年後にパパの家事・育児時間が15〜20分増えたとわかっています。約1カ月の育休がその後のパパの人生をも変えるとわかったことは非常に重要です。
また日本の厚生労働白書では、パパの家事・育児の時間が長い家族ほど、第2子以降の出生割合が高いという報告があります。ママが子どもを持つことに賛成しない多くの理由は、パパの家事負担割合が低いため。パパの育休取得でママの負担が軽減することが出生率上昇に寄与すると考えられます」(山口先生)
育児・介護休業法改正で、柔軟な取得が可能に
政府が検討している育休制度の見直し案は、実際どんな変化が考えられるのでしょうか。
「2022年度以降の施行が計画されている改正案では、妻の出産直後から夫が4分割して休みを取得できる、妻は2分割して取得できるなど、今よりも柔軟に休みの取得が可能になります。
また、職場での申請のしにくさや収入面の不安などから、休みの取得日数は数日から1週間程度という人が多いですが、育休制度改正により、仕事にも影響が出にくく、取得しやすくなるという利点があります」(山口先生)
北欧の例を見ても、上司や身近な人が取得するほど育休は広まったといいます。少しずつ子育てしやすい社会に向かう流れが、制度改正によって加速することが期待されます。
パパが育休を取ることはハードルが高いと感じることも多いかもしれません。しかし、パパの育休取得は、家族の幸福度アップにつながるようです。赤ちゃんが1才未満で、まだ育休取得をしていない人は、ぜひ制度を利用してみてはいかがでしょうか。
イラスト/福士陽香 文/早川奈緒子


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い