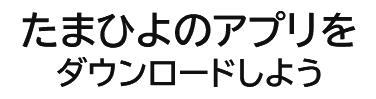第1子と生後18日で死別。子どもが健康に育つのは「奇跡の連続」だと…【直木賞作家・窪美澄】
『夜に星を放つ』(文藝春秋)で第167回直木賞を受賞した、作家の窪美澄さん(56)。2009年、40代で作家デビューした窪さんはデビュー前から「たまごクラブ」「ひよこクラブ」のライターとしても活躍していました。ライター、小説家として仕事をしながら、シングルマザーとして息子さんを育ててきた窪さんに、自身の子育て経験などについて話を聞きました。
1人目を喪失した経験で、2人目の子育てが不安でたまらなかった
――窪さん自身の子育ての経験について教えてください。
窪さん(以下敬称略) 私は26才で1人目の子どもを妊娠し、助産院で出産しました。その子は生まれたときには健康だったのですが、生後17日目に細菌性髄膜炎にかかり、生後18日に亡くなってしまいました。
それまで、妊娠をすれば子どもが生まれてくる、出産をすれば子どもは普通に健康に育つ、というふうに思い込んでいました。子どもが亡くなるなんてことは考えてもいなくて、子どもを病気で亡くしたことがショックで立ち直れず、しばらくの間、何もできないでいました。
そんなある日、偶然バスの中で子どもを取り上げてくれた助産師さんに会ったんです。その助産師さんが「子どもが欲しいと思っているなら、早く次のお子さんを考えたほうがいいですよ」と声をかけてくれました。その言葉に、やっぱり私は子どもが欲しいな、と強く思い直すことができ、ラッキーなことにその後すぐ2人目の子を妊娠したんです。
2人目の息子は無事に出産しましたが、「この子は1人目の子が亡くなった日まで生きられるのだろうか」と、とても不安でした。助産師さんのサポートもあって、出産したあとに大きい病院で検査をしてもらい、健康に問題がない、と太鼓判を押されて、やっと子育てがスタートしました。それでもやっぱりしばらくは不安は消えませんでした。子育てのささいなことを心配ばかりしていたように思います。子どもが生後3カ月ころからライターの仕事を始めたことで、忙しくなって、子どもに対して心配しすぎる気持ちもだんだん和らいできた気がします。
自分の経験からも、妊娠・出産・子育てで子どもが健康に育つことは奇跡の連続なんだと思っています。小説では、その命の軌跡を書いていきたいな、という思いはあります。
仕事をしながらの子育てを助け合った存在
――今回の作品の中には、親以外に主人公を見守ったり助けたりする存在が登場します。窪さんが子育てをしてきた中でも、周囲に助けられたようなことはありましたか?
窪 ライター時代に、住宅関係の広報誌の仕事で全国のショールームを回る取材があり大阪出張になったときのこと。取材前日に当時2才の子どもが熱を出してしまったんですが、夫も母も仕事で頼れず、子どもの預け先が見つからなくて、困り果てて独身の友人に子どもを預かってもらったことがあります。友人は子どもと何度か会ったことはありましたが、丸1日預けるのは初めてのこと。子どもは熱が出ているし、彼女は子育て経験もないのでおっかなびっくりでしたけど、「とにかく夕方には帰るから!」となんとか彼女にお願いして・・・。そんな綱渡りみたいなこともありました。
あとは保育園のママ友とか、学童クラブのママ友たちにも、ものすごく助けられました。
「たまごクラブ」「ひよこクラブ」の取材は診療終了後の夜間に病院に行く取材が多かったんですが、夜は子どもを保育園に預けられないし、シッターさんの時間にも限度があるので、困ることがありました。
それを見ていたママ友が、「忙しそうだから預かってあげる」って言ってくれて、夜遅くの取材のときは預かってくれたんです。仕事を終えて私が迎えに行くと、子どもはごはんを食べ終わり、おふろも入って、あとは寝かせるだけだからって。そこまで面倒を見てくれたママ友に頭が下がる思いでしたが、おかげで仕事を続けることができました。その代わりに、彼女が忙しいときや、出かける用事があるときには彼女の子どもを預かって、相互に助け合っていました。
息子とは今は友だちのような関係に
――今作中、『銀紙色のアンタレス』の真のように、掃除や料理などを自分でできる男の子が登場しています。窪さん自身は息子さんに家事の手伝いをさせるなどは意識していましたか?
窪 私自身は、掃除をすることや食事を自分で用意することというのは、心身ともに健康な人であれば、基本的な人間の生活能力だと思っているので、息子にもそういう能力を身につけてほしいと思ってはいました。でもやっぱり親元にいる間は、私がいくら言っても彼は後片づけもおふろ掃除も、何もしませんでした。大学からはひとり暮らしを始めたので、そこでしかたなく生活能力が身についた感じです。
――ひとり暮らしの息子さんに、電話で家事のやりかたを聞かれたことはありますか?
窪 教えて、と電話がきたことはないんですが・・・ひとり暮らしを始めて1週間たったくらいのころ、夜に電話がかかってきて「包丁で指を切っちゃって血が止まらないんだけど救急車を呼んだほうがいいのかな」と言うんです。新しい包丁の切れ味がよかったみたいで、スポンジで洗っていて指を切ってしまったんですね。息子がどうしようかとマンションの廊下でウロウロしていたら、通りかかった大学の上級生の女性に「すぐ救急車を呼ばないと」と言われて、私に電話をしてきたらしいです。救急搬送してもらったら傷が深かったようで何針か塗ったんですが、あの電話は怖かったです。
――現在の息子さんとのご関係について教えてください。息子さんの恋愛や家族観などについて、お話しすることはありますか?
窪 大学でひとり暮らしを始めてから、社会人になった今も息子とは別々に暮らしています。たまに会ったり電話をすると、女友だちとみたいになんでもあけすけにしゃべってくれます。大学時代の恋愛はあまり知らないですが、25才過ぎたあたりからかな、そのときの彼女の話とか、今つき合っているのはこんな人で、とか話してくれるようになりました。
息子は独身ですが、結婚や家族を持つ願望が強いみたいです。子どもが大好きで、よく子どもが欲しいっていう話も聞きます。
――「子育て期はあっという間に過ぎる」とよく言いますが、仕事をしながらの自身の子育て期間を振り返って、どう感じますか?
窪 本当にあっという間ですね。とくに中学から高校大学の時期は、乳幼児期の1日1日の重みはなんだったんだろうというくらいな速さで過ぎていきます。だから、もし今赤ちゃんを育てていて、1日が長すぎてつらいという人がいたら、中学までの辛抱だよ、と言ってあげたいですね。中学生までにはもちろんいろんなトラブルもありましたけど、でも振り返ってみれば、それもいい思い出と思えるときが、きっといつか来ると思います。
お話/窪美澄さん、写真提供/文藝春秋 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
第一子の喪失の苦しみを乗り越え、友人やママ友などの言葉やサポートによって助けられながら、子育てしてきた窪さん。仕事を持ち多忙な中での子育ては、親だけではなく周囲の人たちとの結びつきも大切なのでしょう。
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
窪美澄さん(くぼみすみ)
PROFILE
1965年東京都生まれ。フリーランスの編集ライターとして、女性の健康を主なテーマに書籍、雑誌等で活動。2009年『ミクマリ』で女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。受賞作を収録した『ふがいない僕は空を見た』で11年、山本周五郎賞受賞。12年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞、19年『トリニティ』で織田作之助賞を受賞。ほか、『水やりはいつも深夜だけど』『いる いない みらい』『朔が満ちる』など著書多数。
夜に星を放つ
かけがえのない人間関係を失い傷ついた者たちが、再び誰かと心を通わせることができるのかを問いかける短編集。第167回直木賞受賞作。窪美澄著/1540円(文藝春秋)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い