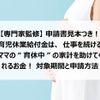【専門家監修】 育児休業給付金の申請手続きともらえる条件
育児休業給付金は、育児休業中の生活を支援する制度。原則、無給となる育休中の生活をサポートしてくれます。ただし、すべての人がもらえるわけではありません。その申請方法と、もらえるための条件などを詳しく説明します。
育児休業給付金ってどんな制度?
育児休暇中は、原則として無給です。仕事を継続するママ(パパ)を対象に、育休中の生活をサポートするために、雇用保険(共済組合)から育児休業給付金がもらえます。もらえる人は、雇用保険に入っていて、育児休業を取り、職場復帰する人です。もちろんパパが育休を取得する場合も同様です。ただし、雇用保険に入っていても仕事日数などの条件を満たしていないともらえないので、詳しくは勤め先または、勤め先を管轄するハローワークに確認しましょう。
もらえる人の条件は?
以下の4つの条件にすべて当てはまる人は、育児休業給付金がもらえます。契約のしかたにもよりますが、契約社員やパート、アルバイトの人も、雇用保険に入っていて以下の条件を満たせばもらえるはず。勤め先に確認を。
① 雇用保険(または共済組合)に入っていて育児休業を取り、その後も働き続ける人。
② 育児休業開始日の前2年間に、原則1カ月に11日以上働いた月が通算12カ月以上ある。
③ 育児休業を取り、育児休業開始から1カ月ごとの区切りに休業日が20日以上ある。
④ 育児休業中に休業開始日前の給料に比べ、8割以上の給料が出ない。
また登録型の派遣社員など期間雇用の人は、上記に加えて一定の条件を満たしていれば、もらえる場合も。派遣元に確認しましょう。
もらえる金額は?
育児休業給付金の給付率は2段階あります。育休開始から180日間は月給の67%(上限額28万4415円、下限額4万6029円)、それ以降は50%(上限額21万2250円、下限額3万4350円)がもらえる仕組み。ただし、育休中に休業開始日前の給料に比べて3割以上の給料が出る場合は減額され、8割以上出る場合は支給されません。
雇用保険に入っていてももらえないケース
雇用保険に入っていても、以下のような場合では、育児休業給付金をもらえない人もいます。注意しましょう。
□育児休業を取らない人
□妊娠中に勤め先を退職する人
□産休後に退職する予定の人
□育休中に給料が月給の8割以上出る人
二人目の子どもの場合にももらえる?
二人目の子どもの場合も、基本的に「もらえる人の条件(上記)」を満たしていれば、育児休業給付金は受け取れます。上の子が1才になってから職場に復職し、すぐに二人目を妊娠した場合でも、雇用保険に加入し続けていれば二人目の時にも育児休業給付金は受け取れます。ただし、育休中に二人目を妊娠した場合は、一人目の育休は終了し、二人目の産休が優先されます。なお、給付の上限・下限の見直しは毎年8月に行われているので、第1子のときと収入は変わっていなくても、給付額は若干変更になることもあります。
もらえるまでの手続きと注意点について
申請できるのは育休に入ってからですが、少しでもスムーズに受け取るためにも、必要書類は産休に入る前にもらい、育休に入るまでに勤め先に提出しましょう。勤め先の担当者の手続きしだいで入金時期も変わるため、担当者とは産休前から意思疎通を図っておくことが大切です。
育児休業給付金の手続きの主な流れは?
妊娠したら早めに、勤め先に育休期間と給付金をもらえるか確認する。
↓
育児休業給付金申請の必要書類をもらう。振込口座にする金融機関で、確認印をもらっておく。ただし、通帳のコピーでOKの場合もあるので、勤め先またはハローワークに確認を。
↓
書類に必要事項を記入する。
↓
必要書類を勤め先に提出する。郵送でOKか事前に確認を。また、自分でハローワークへ提出する場合もある。
↓
提出から約2〜5カ月後、育児休業給付金の初回分が振り込まれる。
↓
約2カ月ごとに手続きし、指定した口座にお金が振り込まれる。初回以降の手続き方法は、事前に勤め先に確認を。
育児休業給付金の手続きの期限は?申請を忘れた場合は?
育児休業給付金の申請には期限があります。とはいえ、原則として勤め先が申請してくれる制度なので自分で手続きをする必要はありません。育児休業給付金の申請は、育児休業を開始してから4カ月後の末日までにハローワークに提出すればよいことになっています。申請時期が遅い場合は、初回の育児休業給付金の支払いも遅くなることを知っておきましょう。心配なら、産休に入る前に、申請時期はいつ頃になりそうかを、勤め先に確認しておきましょう。
育児休業給付金を受給する際の注意点
○育休に入ったらすぐに支払われるわけではない
意外と知られていませんが、育児休業給付金が最初に支給されるのは、書類を提出してから約2〜5カ月後。育休に入る前に書類を提出したのに、初回の振り込みが遅い、とイライラする人も多いようです。育休に入ったらすぐに支払われるわけではないので、その間のやりくりの計画を立てておきましょう。
○毎月振り込まれるわけではない
育児休業給付金が振り込まれるのは、初回以降、おおむね2カ月ごと。毎月振り込まれるわけではないので、月ごとに家計のやりくりをしている人はとまどうかも。育休中は、家計管理もしっかりしておきましょう。
育児休業給付金に関するよくある疑問とその答え
早産で出産した場合、育休開始日は変更可能?
育児休業を予定している人で、出産予定日より早く出産した場合や、配偶者の死亡・病気・けがなど特別な事情があれば、1回に限って、育児休業開始予定日を変更することができます。ただし、当初予定していた育休開始予定日より前に、勤め先に申し出ることが必要です。
育休期間を延長した場合はどうなるの?
育児休業給付金の支給対象期間は、原則としてお子さんの1才に達する日(誕生日の前日)までになっています。ただし、保育園に入れないなどの事情がある場合は1歳6か月に達する日まで(2017年10月からは2歳に達する日まで)延長されます。
育休中にやむを得ず退職した場合、給付金はどうなるの?
育児休業給付金は、育休後も仕事復帰をするママ(パパ)をサポートする制度。ですので、育休中に退職することは、基本的にNGとなります。ただし、子どもに病気が見つかったり、実母の介護をしなくてはならなくなったりなど、やむを得ない事情での退職なら、すでにもらった給付金の返還は不要です。
ママではなく、パパも育児休業給付金をもらえる?
パパが育児休業を取得した場合も、もちろん育児休業給付金はもらえます。ママが専業主婦の場合でも、パパが育児休業を取れるのであれば、育児休業給付金がもらえることに変わりはありません。
また、夫婦で同時に育児休暇を取得することも可能です。育児休業給付金はそれぞれの月給に応じて、受け取れます。夫婦ともに育児休暇を取得する「パパ・ママ育休プラス」の制度を活用すると、お子さんが1歳に達する日までではなく、1歳2カ月まで育児休業を取得することも可能になります。
「育児休業給付金」ここがポイント
●もらえる人
雇用保険に加入していて育児休業を取り、職場復帰する人(パパもOK)
※雇用保険に入っていても条件をクリアしていないともらえないので、詳しくは窓口に確認を。
●もらえる金額
[育休の最初の180日間]月給×0.67×育休として休んだ期間
[181日以降]月給×0.5×育休として休んだ期間
●申請する時期
産後、育休に入る前(勤め先に申請する場合)
●受け取り時期
必要書類提出から約2~5カ月後(初回。その後は約2カ月ごと)
●申請・問い合わせ先
勤め先、または勤め先を管轄するハローワーク
育児休業給付金以外の活用できる制度
妊娠・出産・育児に関するお金の助成については、ここで紹介した「育児休業給付金」以外にも、「妊婦健診費の助成」「出産育児一時金」「乳幼児医療費助成」「児童手当」「医療費控除(確定申告)」や、トラブルがあったときに関係する「高額療養費」「傷病手当金」「未熟児養育医療制度」、妊娠しても仕事を続ける人が関係する「出産手当金」、妊娠を機に仕事を辞めた人が関係する「退職者の所得税還付申告(確定申告)」「失業給付受給期間の延長」、シングル家庭を応援する「児童扶養手当」など、様々な制度があります。
自分が関係する制度が何か、しっかり調べて、助成を受け損ねることのないようにしてくださいね。特に医療機関を利用する際は、要注意です。
まとめ
育休を取る予定のママ、いかがでしたか。育休中に生活のサポートをしてもらえるこの制度、とてもありがたいですね。条件や手続きなどでとまどわないよう、妊娠中から確認しておきましょう。ここでご紹介している内容は、ごく一般的なケースですので、あてはまらない場合もあります。あらかじめよく調べ、届け出先に確認しておきましょう。
(文/たまごクラブ編集部)
初回公開日 2017/08/18
育児中におススメのアプリ
アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数・生後日数に合わせて専門家のアドバイスを毎日お届け。同じ出産月のママ同士で情報交換したり、励ましあったりできる「ルーム」や、写真だけでは伝わらない”できごと”を簡単に記録できる「成長きろく」も大人気!
ダウンロード(無料)育児中におススメの本
最新! 初めての育児新百科 (ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ)
大人気「新百科シリーズ」の「育児新百科」がリニューアル!
新生児から3歳まで、月齢別に毎日の赤ちゃんの成長の様子とママ&パパができることを徹底紹介。
毎日のお世話を基本からていねいに解説。
新生児期からのお世話も写真でよくわかる! 月齢別に、体・心の成長とかかわりかたを掲載。
ワンオペおふろの手順など、ママ・パパの「困った!」を具体的なテクで解決。
予防接種や乳幼児健診、事故・けがの予防と対策、病気の受診の目安などもわかりやすく紹介しています。
切り取って使える、「赤ちゃんの月齢別 発育・発達見通し表」つき。



 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い