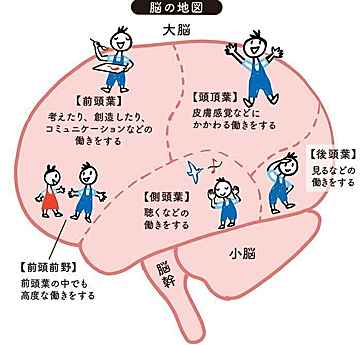脳医学者・瀧先生に聞く「人生は楽しい」と思える子に育てるために、親ができること
数々のヒット本を生み出し、脳医学者として最先端の研究をされている瀧靖之先生に、子育てのコツをお聞きするインタビュー。今回は、「子どもの能力を最大限に伸ばしたい!」と願うみなさんに向けて。前回の記事では、人間の学びは「模倣」がベースにあること、そのためにも親自身が楽しんでいることが大事である、ということをお伺いしました。
今回は「親が楽しむって、具体的に何すればいいの?」という疑問をぶつけました!
昔やっていたことを思い出してみて
親が自分のために、今よりもっと楽しく、何かをしたいと考えたとき、いちばんハードルが低いのは昔やっていたことを再開することでしょう。「やったことのないキャンプに頑張って行ってみる!」というよりも、小学生のころに習っていたピアノを弾いてみるとか、学生時代によく行っていた旅行をするとか。はじめの一歩を踏み出しやすいものを思い描いてみてください。
たとえば私は美術が好きなのですが、息子が1、2才のころから美術館に連れて行っていました。そうすると成長するにつれ、自然と興味を持つんですよね。7才の今では見返り美人だ、フェルメールだと言って、美術館に行くことが当たり前になっています。美術のファミリアリティ(親密さ)が上がると、学校で美術の授業に触れたとき、すでにちょっと知っているから嫌にならない。これがとても大事。勉強って、成績がいい・悪いよりも、好きでい続けることが何より大切だと思います。
ポジティブに生きる力をつけるには?
知識を得ることがおもしろいと感じ、勉強を好きでい続けられれば、仕事や趣味、対人関係、すべてにおいて興味を持つようになり、ポジティブに生きていけます。今、注目されている「非認知能力(目標に向かって頑張る力、ほかの人とうまくかかわる力など)」を育てることにつながるんですね。主観的幸福度、自己肯定感という言葉でも言い換えられるでしょう。
子どもが30代、40代になって人生の壁にぶちあたり、「もうこんな人生、嫌だ」と思ったときに、「ピアノでも弾いてみるか」「好きな絵を描いてみるか」となれるかどうか。それまでに3日坊主でもいいからやったことがあるのか、まったく知らないことなのか。このゼロとイチの差が無限大なんです。
親が子どもに「『人生は楽しい』と思いなさい」「自分を大事だと思いなさい」と言ったって、子どもはわからないじゃないですか。だったら私たちが楽しいことをやって、それを子どもと共有するんです。そうしたらいつか子どもは自分で育って走っていきますよ。
いつか、できるときに始めればいい
とはいえ、子育て中は目の前のことで必死だしすごく大変ですよね。とくに乳児のころは毎日がめまぐるしい。わが家もそうでしたが、3時間おきの授乳があるのに、楽しめるわけがないですよ。だから、ほんのちょっとでいいから頭のすみに「親が楽しむといい」ということを置いてもらえるだけでいいんです。
明日から無理に何かを始める必要はない。余裕ができたときに、「好きなことをやってみようかな」でいいんです。それが子どもと一緒にできることなら最高ですし、一緒にできなくても、親がストレスから少し解放されてニコニコしているだけでも子どもには伝わりますから。
「趣味や好きなことをすることは、子どもへの影響ばかりか認知症の予防にもつながります」と、瀧先生。いつか時間ができたときのために、今から何を始めるか想像するのも楽しいかもしれませんね。(取材・文/ひよこクラブ編集部)
参考
『最新の脳医学でわかった! こんなカンタンなことで子どもの可能性はグングン伸びる!』瀧靖之/著 1400円
(ソレイユ出版)
PROFILE
瀧 靖之先生
医師、医学博士。東北大学加齢医学研究所機能画像医学研究分野教授。主な著書に『16万人の脳画像を見てきた脳医学者が教える 「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社)、『脳科学者が教える! 子どもを賢く育てるヒント「アウトドア育脳」のすすめ』(山と渓谷社)など。7才になる男の子の父。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い