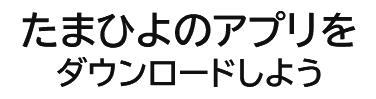「頑張る女性は嫌われる?」植え付けられたジェンダーギャップのモヤモヤが少子化を加速、男性育休の本質的視点は
本特集「たまひよ 家族を考える」では、妊娠・育児をとりまくさまざまな事象を、できるだけわかりやすくお届けし、少しでも育てやすい社会になるようなヒントを探したいと考えています。今回は「男性の育休」をテーマにした連載の第3回です。
国連のSDGs(持続可能な開発目標)で、17の目標の一つに掲げられているジェンダー平等。評価のための1指標として用いられるジェンダーギャップ指数(男女格差指数)は先進国のなかでも非常に低く、日本は国際的に「遅れている」とされています。
ジェンダーギャップをどのように解消していけばいいのか。『男性の育休 家族・企業・経済はこう変わる』の著者である小室 淑恵さん、天野 妙さんにお話を聞きました。
「平成の女性活躍」は次世代の少子化を加速させた?
――先進国のなかでジェンダーギャップ指数が著しく低い日本。近年では、労働力不足という理由からではあるものの、「女性活躍」というキーワードがよく使われています。女性活躍が最も進んだといわれる平成の時代を、小室さん、天野さんはどう見ていらっしゃいますか。
小室さん(以下敬称略) 女性活躍を語るのもタブーだった時代が長かったので、それが当たり前のように語られるようになり、結果的に多くの方が労働市場に出ることができたのは、ポジティブな変化だと感じています。
ただ、その実態は、女性が育児や家事を完璧にやり遂げながら社会進出を果たすという「女性のスーパーウーマン化」によって支えられた女性活躍だったのではないでしょうか。女性は「家庭領域から仕事領域」に活躍の場を広げましたが、男性の多くは「仕事領域から家庭領域」に進出しませんでした。いわば、母親がギリギリの綱渡りを一人でこなしている状態で、活躍すればするほど疲弊していくというのが現実だと思います。
そのことが、家庭のなかで育つ子どもたちに、少なくはない影響を与えています。「ママは働きながら子育てもして、すごく大変そう。私はこんなふうに頑張れないから専業主婦が理想」「パパとママはいつも家事分担でもめている。僕は、将来あんな風に妻や子どもから恨まれるなら、結婚はしたくない」。そんな子どもたちが現実に増えているのです。今の状況を継続することは、さらなる少子化と労働力不足、そしていつまでもジェンダーギャップを埋められない未来を生むことになってしまいます。
天野さん(以下敬称略) これから日本は大介護時代に入っていきますが、女性の更なるスーパーウーマン化によって乗り越えられるほど容易なものではありません。
だからこそ令和は、男性が家庭のなかに入っていく、「男の家庭進出時代」にしなくてはいけないのです。これからは誰しもが、子育てや介護、病気など何かしらの制約を抱えて働く時代となります。すべての人の多様な価値観や働き方が認められ、後ろめたさを感じることなく、仕事も家庭も大事にできる社会に変わる必要があります。
男性も女性も、「仕事か〇〇か?といった2者択一や、性別役割の押し付けではなく、自らの人生を主体的に選択できる」そんな社会に変わるきっかけとして、男性の育休は大きなトリガーになると思います。
「頑張る女性は嫌われる」? 社会から受け取ったメッセージ
――これまでの人生で、ジェンダーの壁を感じたことはありますか。
小室 私は小学生くらいのときからすでに「女性は頑張ったら、最終的には嫌われるのだな」と悟っていました。当時のテレビドラマが余計にそうだったのですが、主役の男性との恋を実らせるのは不器用で頑張らない女性。頑張る女性はたいてい一人、留学に旅立つ結末だったでしょう?(笑)。ニュースを見れば、経済や政治の世界で活躍する女性はヒステリックな役割を担わせられていたり、男性的な振る舞いをしたりしている。
女性は頑張ったら嫌われるか、男性化するか。どちらかの道しかない。そんなメッセージを社会から受け取りつづけていたのです。だから私の場合、ジェンダーの大きな壁にぶつかったというよりも、勝負する前に先が見えて諦めていたという感覚に近いです。このトンネルの先は閉まっている。頑張ることはむなしい。何かに一生懸命になることは格好悪いとさえ感じていました。
大学生の時も、授業中は寝ているか、メイクを直しているか。まわりにも「私は専業主婦志向だ」と宣言していました。そうすれば、たとえ就職活動がうまくいかなかったとしても、負けたことになりませんから。ねじれた自己防衛本能を働かせていたのだと思います。
――企業経営者として活躍されている現在の小室さんからは想像できない姿です。「専業主婦志向」を公言していた小室さんが、その後、変わったきっかけは何だったのでしょうか。
小室 大学3年生のとき、猪口邦子(いのぐちくにこ)先生による特別講演を聴講したことがきっかけです。
猪口先生の話を聞いて、稲妻に打たれたような衝撃を受けました。話の内容としてはこうです。
「働きながら子育てをする人が消費者の大半を占める世の中になったら、働きながら子育てをする人向けの商品やサービスを開発できない企業は負けます。だからあなたたちは、ぜひ企業に就職して、結婚や出産をしたら会社に戻ってあげて、『育児中はこういう商品が必要です』『育児しながら働くためにはこういうサービスが求められているのです』と教えてあげてください」
私はそれまで、女性は結婚や出産で仕事を休んだり辞めたりするのに、男女同権を振りかざして、企業に迷惑がられながら働かせてもらうのだ、と思っていました。でも、猪口先生は経済合理性から女性が働くべき理由を教えてくださった。
女性が働くことは迷惑ではない。むしろ女性が参加しなくてはこれからの企業が勝てないのなら、「私だって働きたい!」「今すぐ人生を変えたい!」と思ったのです。
当事者が発信しないと、社会は変わらない
――天野さんにも同じ質問をさせてください。これまでの人生において、ジェンダーの壁を感じたことはありますか。
天野 私も小室さんと同じく、小学生のときから、ジェンダーの壁を感じていました。私が育った環境は、両祖父が軍人だったこともあり、「女性が男性を立てて、3歩下がって歩く」といったような考え方が根づいた家庭だったんです。
たとえば自宅のリビングでくつろいでいるとき、3人の兄は何もせずにテレビを見ているのに、私は母から「お手伝いしなさい」と言われる。「なぜ、私だけ手伝わないといけないの?」と聞くと、「あなたは女の子でしょ」と諭される。子ども心に「おかしいな」「理不尽だな」と思っていました。
ただ、学生時代はそんなにジェンダーギャップを感じてはいなかったんです。中学・高校は女子高。大学は理工学部で男性が多い環境だったのですが、基本的には成績によって評価されていて、男女平等に扱われている感覚があったので、我が家だけが時代遅れで、社会は変化したのだと思っていました。
しかし、社会人となり10年を過ぎたあたりで、自分を含め女性の先輩たちも難しい仕事が与えられていなかったり、評価が低かったりといった状況がありました。最初は自分の能力が原因だと思っていたのですが、第一子出産後の復職面談で「時短勤務の人は一般職の仕事しかありません。続けますか、辞めますか?」と宣告されました。結果、総合職営業から一般事務職へと変更され、給料も3分の1になりました。
突然頭をハンマーで殴られたような衝撃がありました。勤務時間が短い人は役に立たない。仕方がないから雇ってやる。と言わんばかり。これまで変だと感じていたけど、自分の能力のせいにしていたことが、そうではない…と、腑に落ちました。つまり「あぁ…女だからか」と。でも今思えば、ジェンダーの壁はいつでも目の前にあったのに、気づかないふりをしていただけなのかもしれません。
――「ジェンダーの壁はいつでも目の前にあったけれども気づかないふりをしていた」というお話は、多くの女性に当てはまるように感じます。天野さんがそこから一歩ふみだせた、変われたきっかけは何だったのでしょうか。
天野 思えば、社会を変えようとする女性たちを私たちは「見て」いたんです。小学生のころは田嶋陽子さんが前線に立ってジェンダーの壁を解消しようと声をあげていました。でも「あんなふうに表に立って発言するのは自分には無理だ。それに、きっとこの人たちが世の中を変えてくれる」と、思っていました。他力本願です。
大人になっても他力本願。出産を機にやりがいのある仕事を失い、待機児童の問題にぶつかってもなお、この問題を解決してくれるヒーローの出現を待っていました。
でもある政治家の一言で、はっと気が付いたんです。それは、第3子出産後に待機児童問題について話し合う新聞社主催のイベントでした。ステージ上の女性政治家が「待機児童の問題ってなんで長年解決しないのかわかりますか?」「当事者が、困っているという声を直接政治家に伝えに来ないからなのです。そして、この問題は自分が解決してしまうと忘れてしまうんです」と言ったのです。みんなが他力本願で、個人の最適化で乗り越えてしまっているから長年解決されない。その言葉にものすごく心を揺さぶられました。
誰かが立ち向かわないとダメなんだ。当事者が発信し、政治家に直接語り掛けていかないと、社会は良い方向に変わらないと気づいたのです。それをきっかけに少しずつ行動に移していけるようになりました。
「育休をとるのは女性」と決めつけていませんか?
――お二人の共著『男性の育休 家族・企業・経済はこう変わる』には、「女性だけに休業させる育休制度は女性の長期的なキャリア形成の妨げになる」と書かれています。男性育休の取得率を上げることは、ジェンダーギャップを解消する一助にもなりそうです。
天野 本を書くにあたって、さまざまなご家族にインタビューさせてもらいました。そのなかで、女性が産休後すぐに復帰して、男性が一年の育休をとることを決めたご夫婦がいました。
「なぜ、妻が復帰し、夫が長期の育休をとるのですか?」と聞いたら、「僕が必死に競争して出世を狙うより、女性活躍の時代ですから、妻が復職して出世を目指すほうが、早く成果が出るからです。それに、妻のほうが僕より有能なんですよ」という答えが返ってきたのです。
これこそが家庭のなかでジェンダーの壁がない状態だと感じました。女性も男性も変わらず、気兼ねなく育休をとることができるようになったら、子どもが生まれるたびに家庭ごとの意思決定ができるようになります。「今度はどちらが、育休をとる?」と家族会議をすればいい。「お互い育休をとる」という判断もあるでしょうし、「交互にとる」という選択もあります。
そして強調しておきたいのは、専業主婦の夫にこそ育休をとってほしいということです。専業主婦家庭は、性別での男は仕事/女は家庭といった役割分業制が明確に引かれやすいため、家事育児が何もできないという夫が多くいます。その場合、第2子以降の出産に伴う妻の入院や、妻が病気になることがあっても、妻がいないと家のことが何もわからないという状態に陥りやすいのです。特に今はコロナ禍で実家の両親を頼る状況でもありません。専業主婦の夫こそ育休を取得し、家事育児スキルを一通り身に着けるのが重要です。何よりも産後うつのリスクが高い現代の子育てにおいて、男性の育休取得は家族の幸福にもつながりますし、長期的な視点での家庭内でのジェンダーギャップを見直していく、いいきっかけになるはずです。
---
「男性の育休」をテーマに3回にわたってお送りしてきた本連載。
男性の育休が、少子化対策の突破口となり、企業のビジネススタイルや人々の働き方、ライフスタイルを変え、そしてジェンダーギャップの解消を含めた社会変革のレバレッジポイントになることをお伝えしてきました。
育休を取得するかどうかは家庭ごとの判断に委ねられる問題ですが、企業が育休取得の権利を男女ともにしっかりと説明することで、一歩踏み出す勇気をもてる人が増えるのではないでしょうか。そして一人ひとりの小さな行動が、より働きやすく、生きやすい社会をつくっていくのではないかと感じました。書籍『男性の育休 家族・企業・経済はこう変わる』では、豊富なデータや具体的事例をもとに、基本的な制度の概要や取得の際の注意点、社会的課題まで網羅されています。興味のある方はぜひ手にとってみてください。
取材・文/猪俣奈央子

Profile
【小室 淑恵】
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長。資生堂を退社後、2006年に株式会社ワーク・ライフバランスを設立。1000社以上の企業や自治体の働き方改革コンサルティングを手掛け、残業を削減し業績を向上させてきた。その傍ら、残業時間の上限規制を政財界に働きかけるなど社会変革活動を続ける。ワークライフバランスコンサルタント養成講座を主催し、卒業生は約2000人。著書に『働き方改革 生産性とモチベーションが上がる事例20社』(毎日新聞出版)『プレイングマネジャー 「残業ゼロ」の仕事術』(ダイヤモンド社)他多数。
【天野 妙】
合同会社Respect each other代表、みらい子育て全国ネットワーク代表。日本大学理工学部建築学科卒業。株式会社リクルートコスモス(現コスモスイニシア)等を経て、性別・役職・所属・国籍に関係なく、お互いが尊敬しあう社会づくりに貢献したいと考え、起業。ダイバーシティ/女性活躍を推進する企業の組織コンサルティングや、研修など、企業の風土変革者として活動する傍ら、待機児童問題をはじめとした子育て政策に関する提言を行う政策起業家としても活動中。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い