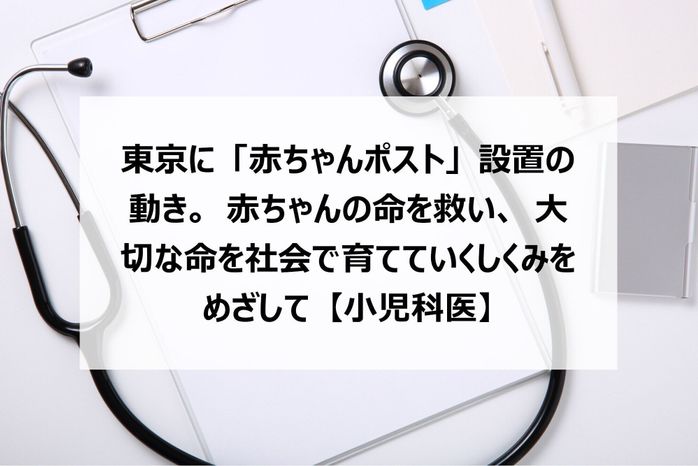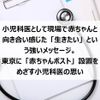東京に「赤ちゃんポスト」設置の動き。赤ちゃんの命を救い、大切な命を社会で育てていくしくみをめざして【小児科医】
親が育てられない赤ちゃんを匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」を、2024年の秋に東京に設置する計画を表明したのが、医療法人社団「モルゲンロート」の小暮裕之理事長。2022年11月には小池百合子都知事と面談し、赤ちゃんポスト事業の検討を始めるよう求める要望書を手渡しました。どんな施設を計画しているのか、今後の課題について考えることなどを、小暮先生に聞きました。
江東区内の産婦人科に「赤ちゃんポスト」を設置予定
――2024年秋に、江東区内で産婦人科医院を開業して、そこに「赤ちゃんポスト」を設置する方針とのことです。「赤ちゃんポスト」設置のために産婦人科医院を作ろうと考えたのですか?
小暮先生(以下敬称略) 「赤ちゃんポスト」計画より以前に、産婦人科医院を開業する計画がありました。開業を考えた理由は、4人の子どもを出産した妻との経験からです。妻は第1子〜第3子を無痛分娩で出産しました。僕が新生児科の医師として病院に勤務していた際、さまざまな分娩に立ち会う中で、無痛分娩をした人のほうが産後の体力の消耗が少ないことを見ていたので、妻にも無痛分娩をすすめたんです。
第1子のときの産院では、ある程度陣痛が進んでから麻酔を入れたんですが、そのときの陣痛のしんどさと麻酔が効いてからの体の楽さを経験し、妻は「2人目以降も絶対無痛分娩がいい」と言っていました。第2子以降の出産のときには、僕が上の子の面倒を見るために仕事の都合をつけたり、祖父母に預けたりするために、計画出産にする必要がありました。さらに無痛分娩となると、費用はかなり高額だったんです。そのときに、無痛分娩が日本で広がらないのは金額がネックになっていると感じました。
そこで、費用をもっと抑えながら、計画出産や無痛分娩などの出産方法を選べる施設を造りたいと考えました。子どもを持ちたい夫婦にとってもっと産みやすい社会にしたいし、1人目の出産が痛い・苦しい記憶よりも、痛みが少ないほうが2人〜3人の出産につながりやすいんじゃないかとも。実際、わが家の場合は、子ども4人が年子です。妻の経験からは出産時の負担が少なかったことがよかったと感じています。
さらに、産婦人科医院を開業するとなれば、24時間の医療体制ができるから、こちらも以前から思いはあったのですが「赤ちゃんポスト」も併設できるな、と考えました。
赤ちゃんの虐待死を予防するために「妊娠相談ほっとライン」の認知を広めたい
――赤ちゃんポスト設置の目的を改めて教えてください。
小暮 私たちは「赤ちゃんポスト」の設置によって虐待死と殺人罪の母が減ることを目標としています。そのために、①望まない妊娠出産、想定外の出産・育児負担を「予防」すること、②望まない妊娠が発生し、すでにお悩み中の方を「助ける」こと、③「こうのとりのゆりかご」が必要ない状態、虐待死が「ゼロ」になる状態を作ることをめざしたいと思っています。
予防対策として有効なのは相談事業ですが、東京都が2014年に設置した「妊娠相談ほっとライン(※)」の認知度の低さが課題と考えています。都営地下鉄の空きスペースや学校に「妊娠相談ほっとライン」のポスターを掲示したり、産婦人科のホームページにバナーを掲載したり、SNSやYouTubeなどでも発信する必要があると思います。2022年秋の小池都知事に赤ちゃんポスト事業の検討を始めるよう求める要望書を届けた際にも、そのことを伝え協議中です。
私たちが参考にしていて、視察にも行かせていただいた熊本の慈恵病院では相談事業も行っています。慈恵病院のシステムは、相談事業から実際の赤ちゃんの預かり、そして養育施設や里親・養親につなげることまですべて病院が行っていて、それにはかなりの人件費などがかかります。素晴らしいモデルなのですが、同じことを持続可能にしていくには、大変な努力を要するという事を教えていただきました。
東京では、都以外にも相談事業を行うNPO法人などもありますので、行政やNPOなどと協力しあって相談から養育まで運営できるモデルケースが作れれば、全国にも広がりやすくなるのではと考えています。
困難を抱えた妊婦が安全に出産し、生まれた命をつなぐために
――赤ちゃんポスト設置のほかに、養子縁組の支援にも取り組む考えだとか。
小暮 「赤ちゃんポスト」は、赤ちゃんの命を救うための最終手段だと思っています。赤ちゃんの虐待死を予防するために最も重要なのは、育ての親へつなげる特別養子縁組制度や里親制度がもっと一般的になることだと考えています。予期せず妊娠したが、育てられないといった場合に、養子縁組によって育てたい人にマッチングすれば、赤ちゃんの命が助かるわけです。
日本では特別養子縁組があまり一般的でありませんが、当たり前の価値観にしていくためには、養子縁組や里親のもとで育って大人になった人が発信して話題になることが必要だと思います。熊本の慈恵病院で「こうのとりのゆりかご」と呼ばれる保護施設ができて15年。預けられた子どもたちが大人に近づきつつある今、「こうのとりのゆりかご」に預けられた宮津航一さんが実名を公表して発信したり、“みかん高校生”のペンネームで漫画を描いて発信している人もいます。
――預けられた赤ちゃんを特別養子縁組の夫婦にマッチングするのは、どのような流れになるのでしょうか。
小暮 特別養子縁組で子どもを迎え入れるには、審査などのために6カ月ほどの時間がかかるそうです。産院の「赤ちゃんポスト」で預かった赤ちゃんは、健康状態が良好と確認できたら、養親(ようしん)が決まるまでは乳児院に預かってもらいます。特別養子縁組がもっと広まれば、養子に出したいと考えている実親が妊娠中からマッチングすることも可能になるでしょう。理想としては、赤ちゃんが病院を退院するときには、養親に迎え入れてもらうことです。特別養子縁組については、NPO法人にも協力してもらう予定です。
「赤ちゃんポスト」設置反対派の意見の一つとして、「乳児院の負担が増える」と聞いたことがあります。命を救われた赤ちゃんがいるから乳児院の負担が増える、という言い方はとても残念です。負担が増えるから助からないでいいのか、という考えだとしたら到底理解できません。私は小児科医として、赤ちゃんの命を最優先にするべきだと考えています。
――出産や子育てが難しい妊婦が、病院以外に身元を明かさず出産する「内密出産」についてはどう考えていますか?
小暮 複雑な家庭環境や、経済的困窮などの理由で病院にかかれず、自宅などでの危険な出産をしたり、赤ちゃんを育てられずに遺棄したりすることを防ぐため、「内密出産」にも取り組みたいと考えています。2022年9月に厚労省が「内密出産」のガイドラインを公表しました。ガイドラインには身元情報を明らかにした出産が行われるよう説得することを前提に、子どもが自分の出自を知る権利に対応できるよう、医療機関が妊婦の身元情報を管理すること、などの対応方法が盛り込まれています。
また私たちは、経済的な事情や複雑な家庭環境のために産前・産後の支援が必要と認められる「特定妊婦」に対して、自己負担なしでの出産を実施したいと考えています。費用面では、NPO法人に寄付を集めてもらいながら実施する方向です。「特定妊婦」がもし産後に子どもを育てることが難しければ、特別養子縁組によって養親とマッチングする。出産の支援と養子縁組の両面から、赤ちゃんの虐待死を防ぎたいと考えています。
そのためにも、「赤ちゃんポスト」設置前後に、官民連携して赤ちゃんの虐待死ゼロに向けて取り組み、さらに全国の医療機関でも実施できるようなモデルを作ることをめざしています。
お話・監修/小暮裕之先生 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
1人でも多くの赤ちゃんの命を助けるために、赤ちゃんポストの設置だけでなく、妊娠中の相談事業の周知なども課題となっています。
現在、東京に設置する「赤ちゃんポスト」の名称を募集しています。1月から募集を開始し、すでに300件近くの応募があるのだとか。「だれもが“赤ちゃんの命が助かる場所”とイメージがわくようなネーミングを寄せていただきたいです」と小暮先生は言います。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い