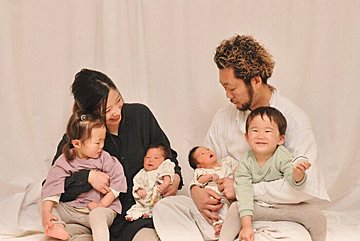ダブルケア~育児と介護~を同時に行うことになったら、あなたはどうする?
iStock.com/sezer66
0~1才代の赤ちゃんがいるママたちのばあば・じいじは、多くは50~60代、中には70代以降の方もいらっしゃるかもしれませんね。おそらく元気いっぱいで、ママやパパをサポートしてくださっている方も多いと思いますが、50才を過ぎると、いろいろな病気のリスクがアップして、思いがけない病気を患う心配も出てきます。そして、日常のサポートが必要になってしまう恐れも…。
もし、赤ちゃんのお世話に加えて、じいじ・ばあばの介護ケアもしなくてはならなくなったら…あなたはどうしますか? 子育て支援と介護支援を研究している、横浜国立大学大学院の相馬直子先生に話を聞きました。
「ダブルケア」とは、同時に複数の人のお世話をすること
「ダブルケアをする」とは、実際、どんな状況になるということなのでしょうか? 相馬先生に聞きました。
ダブルケアは、1人で大変さを抱える可能性が高い
「『ダブルケア』とは、複数の人のお世話が同時に進行する『ケアの複合化』を言いますが、とくに育児と介護の同時進行を指すことが多いです。晩婚化や晩産化、そして少子高齢化により、きょうだいで介護の負担を分け合えなくなってきた日本では、ダブルケアに直面する人が増加しており、今後ますます多くなってくると考えられています。
育児と介護のダブルケアの大変なところは、日本では、いずれも“家庭内でどうにかしなくてはいけない”という意識が強いこと。さらに、“女性が(妻が、娘が)ケアをしなければならない”という意識が社会にまだ残っていること。その結果、ダブルケアラー(ダブルケアをする人)が孤立し、大変さを1人で抱えなくてはならない可能性が高くなるのが、問題となっています」
縦割り行政のはざまで、十分なサポートがけにくい
「また、今まで、国ではダブルケアの実態を十分に把握できていませんでした。そのため、行政がダブルケアのケースに対応できないことが多くありました。
たとえば、介護のためにフルタイムで働けない・仕事につけない人は、保育園入所のポイントが低く、保育園に入りにくくなってしまうといった状況です。サポートのニーズが高いにもかかわらず、縦割り行政のはざまで、十分なサポートを受けられず、困難を強いられている人が少なからず存在していたのです」
ダブルケアはお金がかかる
「子育てにお金がかかるのと同様、介護にもお金がかかります。子育ても介護も、行政による負担金の助成制度はあります。しかし、ある程度の自己負担金も必要になるため、育児と介護のお金が同時にかかってくることに。介護は突然始まるので、急に必要になった介護費用を、学資保険を解約して捻出(ねんしゅつ)するといったケースもあるといいます」
ダブルケアに直面している家庭の割合は?
実際に、育児と介護の両方に直面している人は、どのくらいいるのでしょうか? 相馬先生の行った調査の結果を紹介してもらいました。
予備軍も含めると30代で4人に1人
「ダブルケアに直面している人の状況を、2012年に横浜市内の子育て支援センター3カ所で調査した結果、平均年齢は、41.1才、1人目の子の年齢の平均は、7.7才でした。またソニー生命と連携して、2015年に全国の大学生以下の子どもを持つ母親に調査を行った結果では、実際にダブルケアに直面している人は、30代で6.8%、40代で9.5%。また、数年先にダブルケアに直面する可能性があるという予備軍も含めると、30代で27.1%、40代で19.9%でした。決して少なくない割合で、ダブルケアに直面する可能性のある人がいることがわかります」
6割の人は、ダブルケアの備えをしていない
「ソニー生命連携の2017年調査では、ダブルケア未経験者の6割で、ダブルケアの備えをしていないというデータになりました。また、ダブルケア経験者に『ダブルケアの備えとして行っておいてよかったと思うこと(2017年ソニー生命連携調査)』を聞いた結果で、最も多かったのは以下の回答でした。
全体1位:親が元気なうちに介護について話し合う
男性1位:だれがいつ要介護になるリスクがあるのか整理する
女性1位:子育て・介護に関する経済的な準備(貯蓄・保険など)をする
だれもが『うちは100%大丈夫』と言いきれない状況にあります。できることから始めておくほうが、安心と言えるでしょう」
介護に関する基本情報だけは知っておきたい
0~1才代の赤ちゃんのいる家庭では、育児については詳しくても、介護については何も知らないという人も少なくないでしょう。けれども、ダブルケアの備えとして、少なくとも基本情報だけは得ておくことが大切です。
相談窓口は「地域包括支援センター」
「まず、支援施設についてですが、育児の場合は子育て支援センターが取りまとめていますが、介護の場合は『地域包括支援センター』という施設になります。急に介護が必要になった場合、何もわからなくても、この施設で相談をすると教えてもらえるでしょう。わからなければ、まずは『自治体の介護保険課』に連絡するのでもいいでしょう。
また、必ず利用することになる『介護保険制度』についても、基本的な内容や手続きのしかただけは、ざっくりとでも知っておくと安心です。
近年、ダブルケアの実態が明らかになってきて、いずれの支援施設でも、ダブルケアの相談に乗ってもらえることが増えてきました。また、利用しづらかった行政のサポートも、少しずつダブルケアの視点で改善が見られるようになってきています。
しかし、実際にダブルケアに直面している人たちからは、まだ十分にサポートが受けられないという声も多く聞かれます。今後も、さらに当事者が声をあげて、改善を求めていくことが必要と言えるでしょう」
ダブルケアカフェやSNSなどの交流の場が登場
「ダブルケアの人は、子育て中のママにも介護中の人にも相談がしにくいことから、うつうつとした気持ちを抱えながらも、グチをこぼす場所もないという声もよく聞かれます。ただ、最近では、SNSなどでダブルケアのスレッドが立ち上がっていたり、ダブルケア中の人たちが、ダブルケアカフェを開催するなど、当事者同士で、情報交換をしたり相談し合う交流の場が広がってきています。
もしダブルケアに直面したら、決して1人で抱え込まず、ぜひこのような会を利用して、支え合い、つながりながらのダブルケアを行ってほしいと思います」
介護は、まだ先の話と思っていたママも多いかもしれませんね。でも万が一のために、少なくとも情報だけは得ておきたいですね。
(取材・文/ひよこクラブ編集部)
■監修●相馬直子先生(横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 准教授)
東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学、日本学術振興会特別研究員を経て、2007年より現職。英国ブリストル大学 講師 山下順子先生とともにダブルケアについて共同研究されています。1児の母。
■関連記事
・節約より絶対貯まる! ムダを減らしてお金を増やす、毎日の小さな習慣
・「“産後うつ”かも…」出産後いちばん大変だったことは?【0~5才ママ調査】
・「親子で発達障害⁈」育児エッセイが話題のモンズースーさんにインタビュー
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い