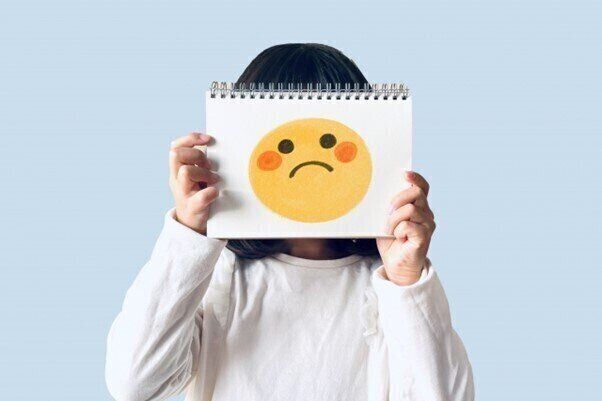「薬を飲んでくれない…」ついやりがちな親のNG行動とは。イヤイヤ期の子どもに薬を飲ませるコツも紹介
「イヤイヤ期の子どもが薬を飲んでくれない」と困っていませんか? イヤイヤ期の子どもは、この時期特有の反抗やこだわりに加えて、味覚の発達や記憶面での成長などにより薬を嫌がる場合があります。今回は、イヤイヤ期の子どもに薬を飲ませる工夫やNGポイントを解説します。
イヤイヤ期の子どもが薬を嫌がる理由
子どもの自我が芽生えて、強いこだわりを持ったり主張し始めたりするイヤイヤ期には、薬の服用を嫌がることが少なくありません。この時期の子どもは味覚が発達して好き嫌いが顕著になり、薬の苦みや甘みを嫌うことがあります。また、薬の形状から飲みづらさを感じて、嫌がることもあるようです。
さらに、薬を飲まなかったときに厳しく叱ってしまうと、叱られたことが嫌な思い出として残り、薬を飲むこと自体を嫌うようになる可能性があります。イヤイヤ期の子どもが薬を嫌がるときは、「親に叱られて薬を嫌がる悪循環」に陥らないよう、まずはママやパパが気負い過ぎないようにすることが大切です。(※1)
イヤイヤ期の子どもに薬を飲ませるコツ
イヤイヤ期の子どもに薬を飲ませる4つのコツを解説します。
飲み物・食べ物に混ぜて飲ませる
子どもが粉薬を嫌がるときは、ジュースやアイス、服薬補助ゼリーなどに混ぜて薬の苦みを軽減するのがおすすめです。ただし、食品と合わせると苦みが増したり薬の効果に影響したりすることもあるため、事前に薬剤師に確認してください。
また、「水薬が甘すぎて苦手」という子には、1回分の服用量を水で薄めて甘みをやわらげてみましょう。「水薬の苦みが嫌い」という場合には、ガムシロップで甘みをつけると飲みやすくなります。
形状の異なる薬に変更する
粉薬が苦手なら水薬に変更するなど、子どもの飲みやすい形状の薬で代替できるものがないか、医師や薬剤師に相談してみましょう。成長に合わせて飲みやすい薬が変わり、これまで飲めなかった薬でも飲めるようになっていることがあります。
また、解熱剤の粉薬を上手に飲めない場合には、坐剤を使うのがおすすめです。(※2)
薬を飲む道具を工夫する
道具を活用すると上手に飲めることがあります。たとえば、粉薬を薬の袋から直接口に入れるのを嫌がる場合でも、スプーンに載せてから口に入れればすんなり飲めることがあるので試してみましょう。
スプーンに少量の水を入れて粉薬を少し溶かすと、かさが減るので飲み込むのが楽になります。スプーンは使い慣れているもののほうが、子どもが安心できるでしょう。
楽しい雰囲気作りをする
保護者が「絶対に飲ませなければ……」と気負い過ぎてしまうと、子どもはピリピリした空気を察知して薬の時間を怖がってしまいがちです。できるだけ楽しい雰囲気を作り、薬を飲めたら「がんばったね」とたくさん褒めてあげましょう。嬉しくなって、薬への抵抗感が減るかもしれません。
また、子どもの好きなキャラクターを絡めて服薬する理由を説明したり、「〇〇ちゃんの中にいるバイキンをやっつけるために、お薬を飲もう」と励ましたりするのも効果的です。
もし薬を飲めなかった場合でも、チャレンジしたこと自体を褒めてあげましょう。
薬を飲ませる際のNG行動は?
子どもに薬を飲ませるときは、無理に口を開けたり、押さえつけて飲ませたりするのは厳禁です。無理強いすると、子どもはますます嫌がってしまいます。
また、親が怒ったり怖い顔をしていたりすると、子どもの警戒心が強まることがあります。親もリラックスを心がけてください。
「飲みたくない!」と子どもが駄々をこねると親もついイライラしてしまいますが、感情的になったり突き放したりすると逆効果なので、深呼吸をして落ち着きましょう。成長するにつれて、子どもも徐々に説得に応じてくれるようになってきます。飲ませ方を工夫しながら、イヤイヤ期を乗り切っていきましょう。
イヤイヤ期の服薬を上手に乗り切ろう
イヤイヤ期の子どもに薬を飲ませるときは、無理強いすると逆効果です。ジュースやアイスに混ぜる、道具を活用するなどの工夫をして、子どもが受け入れやすい飲み方を探しましょう。
楽しい雰囲気で、飲めたらたくさん褒めることも重要です。子どもの成長に寄り添いながら、リラックスした気持ちで根気強く服薬を促しましょう。
<参考文献>
PROFILE
あんしん漢方薬剤師
山形 ゆかり
薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角・吉野家他薬膳レストランなど15社以上のメニュー開発にも携わる。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホひとつで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートを行う。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い