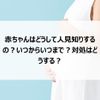新生児~1歳までの赤ちゃんの体重はどう変わっていくの?
赤ちゃんは生まれてから1年の間に、体重が約3倍も増えます。人間の一生の中で、この1年が一番成長する時期なのです。でも個人差も大きいので、自分の子どもが順調に大きくなっているか心配になりますよね。
そこで、新生児期から1歳になるまでの身長と体重の変化について、慶應義塾大学医学部小児科教授の高橋孝雄先生に教えてもらいました。
誕生から1ヶ月たつと、500g~1kg程度体重が増えます
生まれて数日間は、母乳やミルクを飲む量より、排せつや汗で体内から出ていく水分のほうが多いので、一時的に出生体重より体重が減少。しかし、その後少しずつ体重が増え、1ヶ月後には500g~1kgくらい体重が増えます。
一時的に出生時より体重が減りますが、その後増えていきます
●誕生時から30日後の身長・体重の変化の平均
(身長・体重は乳幼児身体発育値の3~97パーセンタイル値)
男の子
身長/44.0~52.6cm→48.7~57.4cm
体重/2.10~3.76kg→3.00~5.17kg
女の子
身長/44.0~52.0cm→48.1~56.4cm
体重/2.13~3.67kg→2.90~4.84kg
※ ここで紹介する身長と体重は、乳幼児身体発育調査(平成22年厚生労働省)の3~97パーセンタイル値。パーセンタイル値とは全体を100として小さいほうから数えて何番目になるのかを示す数値で、3~97パーセンタイル値は、赤ちゃんが100人並ぶと3番目から97番目に当たります(各月齢同様)。
2~3時間くらいの間隔で目を覚まして母乳やミルクを飲み、また眠ることを繰り返し、1日の7割以上は眠っています。1日におしっこは15~20回、うんちは2~8回します。この時期は飲む量より、うんち・おしっこで排せつされたり、汗として出る量のほうが多いため、一時的に体重が減少します。
これは「生理的体重減少」と呼ばれ、出生体重の1割以内であれば心配のないもの。生後7~10日ごろには、出生体重を超えて体重が増えるようになります。
その後は1日に20~40g、つまり1ヶ月で500g~1kgくらい体重が増えますが、個人差が大きいので、少しずつでも増えているのであれば、大らかに見守りましょう。
ただし、1週間で70g未満、1ヶ月後に500g未満しか増えない場合は、小児科で相談を。
●この時期の赤ちゃんの様子
すでに聴覚はほぼ完成していて、音が聞こえてくる方向がある程度わかります。
視力は0.02前後なので、30cm先のものがやっと見える程度。明暗のコントラストがはっきりしたもののほうが見えやすいです。
低出生体重児では出生体重に戻るのに時間がかかります
低出生体重児とは、生まれるまでの妊娠期間にかかわらず、出生体重が2500g未満の新生児のことです。
周産期医療の進歩によって1500~2500gで生まれた赤ちゃんの多くが、正期産(出産予定日前後の妊娠37週0日~41週6日までの間の出産)で生まれた赤ちゃんと同じように育ちます。
<出生体重による区分>
低出生体重児:出生時の体重が2500g未満の赤ちゃん
極低出生体重児:出生時の体重が1500g未満の赤ちゃん
超低出生体重児:出生時の体重が1000g未満の赤ちゃん
小さく生まれた赤ちゃんでは生理的体重減少の期間が長く、出生体重に戻るまでに時間がかかります。
どれくらい時間がかかるかは在胎週数などによって変わります。正期産だけど低出生体重児であった場合、輸液水分や栄養を点滴で補給する必要がなく、おっぱい・ミルクだけで大丈夫であれば、通常より2~3日長くなる程度です。
「身体発育曲線」は赤ちゃんの成長の目安になるもの
母子健康手帳に示されている「身体発育曲線(正式名称は乳幼児身体発育曲線。発育曲線と略されることも)」は、厚生労働省が10年ごとに乳幼児の身体発育を調査し、作成しているもの。どの月齢でも、小さい方と大きい方、7本の曲線からなる帯のどこかに入る子が全体の94%います。
赤ちゃんの発育の目安として乳幼児健診などで使われます。
表の横にある数字は「パーセンタイル値」と呼ばれ、全体を100としたとき小さいほうから数えて何番目になるかを示しています。たとえば、体重が50パーセンタイルの赤ちゃんは「100人中の小さい方からも大きい方からも50番目」つまり、平均的な体重ということになります。
身体発育曲線は、赤ちゃんの身長・体重・頭位がその月齢・年齢全体の中でどれくらいのところにいるのか、成長の目安となるものですが、帯の中に入っていなければ大変!というわけでもありません。
帯の上や下にいても、曲線のカーブに沿って増えているなら、その子なりに発育しているということ。心配しなくていい場合がほとんどです。
ただし、曲線をまたいで大きく上や下に外れたり、横ばいのままだったりする場合は、小児科医や自治体が行う健康相談窓口などに相談してください。
赤ちゃんの発育具合を確認することは大切。でも神経質になりすぎないで
赤ちゃんの発育具合を把握するために、身長・体重・頭位を定期的に測定しましょう。乳児健診では必ず測定しますが、それ以外に、自治体が行っている乳幼児の身体測定なども利用するといいでしょう。
また、ショッピングモールやデパートなどの赤ちゃん休憩室にも、ベビースケール(赤ちゃん用体重計)が置いてあることがあります。おむつ替えのついでに測ってみるのもいいですね。
家庭にベビースケールがある場合は、授乳前で排せつ後に測定を。おむつも脱がせた裸の状態で測るのがベストですが、裸にすると赤ちゃんが不安で泣いてしまうのなら、洋服を着たまま測ったあと着衣の重さを測り、その分を引けばOKです。
赤ちゃんの発育のスピードは個人差が大きいですし、身長や体重の増え方にむらがあるのも当たり前のこと。心配なあまり頻繁に測定しすぎたり、増減に神経質になったりするのはやめましょう。
1ヶ月~1歳の赤ちゃんの月齢別身長・体重の目安
新生児期を過ぎると母乳やミルクを上手に飲めるようになり、少しずつ体つきがしっかりしてきます。1ヶ月~1歳は赤ちゃんがどんどん成長する時期です。身長・体重の変化と、各月齢の代表的な発達の様子を知っておきましょう。
1~4ヶ月はぐんぐん大きくなり、4ヶ月で体重は出生時の約2倍に
●1~2ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/50.9~59.6cm
体重/3.53~5.96kg
女の子
身長/50.0~58.4cm
体重/3.39~5.54kg
身長は出生時より約6~7cm程度伸びます。体重は約1~2kg増え、全体的にふっくらとした体つきに。手足をバタバタしたり、顔を左右に動かしたりできるようになります。
●2~3ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/54.5~63.2cm
体重/4.41~7.18kg
女の子
身長/53.3~61.7cm
体重/4.19~6.67kg
母乳の飲み方が上手になり、おなかがいっぱいになると自分から離す赤ちゃんも。手足の動かし方もスムーズになります。
●3~4ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/57.5~66.1cm
体重/5.12~8.07kg
女の子
身長/56.0~64.5cm
体重/4.84~7.53kg
身長は平均で12~13cm伸び、体重は出生時の約2倍に。授乳リズムが整ってきて母乳は6~8回、ミルクは5~6回になります。
4~8ヶ月は体がしっかりしてきて、できることが増えます
●4~5ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/59.9~68.5cm
体重/5.67~8.72kg
女の子
身長/58.2~66.8cm
体重/5.35~8.18kg
首がしっかりしてきて、たて抱きにしてもほとんどぐらつかなくなります。昼夜の区別がつき始め、睡眠のリズムが整ってきます。
●5~6ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/61.9~70.4cm
体重/6.10~9.20kg
女の子
身長/60.1~68.7cm
体重/5.74~8.67kg
ほとんどの赤ちゃんの首がすわり、寝返りを始める子も。うつぶせにすると上半身をしっかり起こしたり、うつぶせのまま両手を使って遊んだりできるようになります。
●6~7ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/63.6~72.1cm
体重/6.44~9.57kg
女の子
身長/61.7~70.4cm
体重/6.06~9.05kg
短時間なら、両手で体を支えて1人でおすわりができるようになります。寝返りが上達し、足で勢いをつけなくても、腰をひねって回転できるように。
●7~8ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/65.0~73.6cm
体重/6.73~9.87kg
女の子
身長/63.1~71.9cm
体重/6.32~9.37kg
おすわりが安定するので、おすわりで遊ぶのを喜ぶ赤ちゃんが増えます。親指とそのほかの指で物を挟んで持てるようにも。
8ヶ月~1歳は身長が伸びてほっそり体型に。手脚の発達が著しい時期です
●8~9ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/66.3~75.0cm
体重/6.96~10.14kg
女の子
身長/64.4~73.2cm
体重/6.53~9.63kg
体重の増え方より身長の伸びのほうが大きく、だんだんほっそりした体型に。おすわりがさらに安定し、はいはいをする赤ちゃんも多くなります。
●9~10ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/67.4~76.2cm
体重/7.16~10.37kg
女の子
身長/65.5~74.5cm
体重/6.71~9.85kg
はいはいが上達し、素早い移動や方向転換ができるように。つかまり立ちから伝い歩きができる赤ちゃんもいます。親指と人さし指で小さな物をつかめるようにも。
●10~11ヶ月の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/68.4~77.4cm
体重/7.34~10.59kg
女の子
身長/66.5~75.6cm
体重/6.86~10.06kg
多くの赤ちゃんがつかまり立ちをするようになり、伝い歩きを始める子もいます。指を使って細かい動作ができるようになるので、遊びの幅が広がります。
●11ヶ月~1歳の赤ちゃんの身長と体重
男の子
身長/69.4~78.5cm
体重/7.51~10.82kg
女の子
身長/67.4~76.7cm
体重/7.02~10.27kg
生まれたときと比べて身長は20~25cm程度、体重は5~7kg程度増加し、幼児らしい体型に。伝い歩きが上手になり、立っちができるようになる子もいます。
体重が増えない&増えすぎるときの対処法は?
母乳・ミルクを飲む量、動く量などによって、体重が思うように増えないと心配するママがいれば、増えすぎて心配…というママもいます。体重が増えないとき、増えすぎているときの対処法を知っておけば、大らかな気持ちで赤ちゃんに接することができるでしょう。
カウプ指数は赤ちゃんの肥満の目安となる数値
健診などで赤ちゃんの身長・体重を測定すると、「カウプ指数」を算出されることがあります。これは、乳幼児の肥満の目安となる数値です。
<カウプ指数の算出方法>
体重(g)を身長(cm)の2乗で割って10倍
カウプ指数が乳児は22以上、幼児は20以上だと肥満とされます。
でも、乳幼児の肥満はほとんどが心配のないもの。特に乳児期は歩き始めると運動量が増え、全体的に脂肪が落ちてほっそりすることが多いので、今は太りぎみでも様子を見守っていれば大丈夫です。
ただし、ママ・パパともに肥満傾向にある場合は、赤ちゃんも将来、生活習慣病のリスクが高くなる可能性があるので注意が必要。ママ・パパの偏食や食べ方のスタイルは、赤ちゃんの食習慣にも影響することが考えられるので、ママ・パパがバランスのいい食事をしっかりかんで食べるよう意識することが大切です。
そして、親子で体を動かす時間を作るようにしましょう。
体重が増えないときはどうすればいい?
赤ちゃんの体重があまり増えないときは、主に3つの原因が考えられます。
●原因1 飲む量が不足している
赤ちゃんがおっぱいを吸うのに慣れていなかったり、母乳の分泌量が少なかったりする可能性があります。赤ちゃんの体重の増加が思わしくないときは母乳外来などを受診し、赤ちゃんの飲み方や母乳が出ている量をチェックしてもらいましょう。
<対処法>
小児科や母乳外来などで母乳が足りないと判断されたら、十分に分泌されるようになるまでミルクを足します。ただし、母乳の出が悪くならないようにすることが大切なので、ママの自己判断で足すのは控えましょう。また、ミルクを足す場合もまずは母乳を飲ませ、不足分だけミルクで補います。
●原因2 よく動くため消費カロリーが多い
体を動かすのが好きな子は消費カロリーが多いため、母乳やミルクをたくさん飲んでいても、あまり体重が増えないことがあります。
<対処法>
よく飲み、よく動き、うんちやおしっこもちゃんと出ていてご機嫌に過ごせるのであれば、しばらく様子を見て大丈夫です。
●原因3 なんらかの病気
生まれつきの消化器の病気によって体重が増えないこともあります。飲む量が不足する原因として、心臓や筋肉、神経の病気が隠れていることもあります。また、消費カロリーが増えてしまう病気もまれにあります。
<対処法>
飲む量、授乳後の様子、おしっこ・うんちの状態、ご機嫌など、赤ちゃんの全身状態をよく観察し、気になることがあったら小児科で相談しましょう。
とくに、授乳後に噴水のように吐くことをくり返して体重が増えないときは、「肥厚性幽門狭窄症(ひこうせいゆうもんきょうさくしょう)」の可能性もあるので、早めに受診してください。また、うんちの色が白っぽい、便秘がひどいなどの症状も要注意です。
体重が増えすぎるときはどうずればいい?
1歳までの赤ちゃんが太っていても、将来の肥満に影響を与えることはないので、発育曲線のカーブを大幅に超えていなければ神経質にならなくて大丈夫です。
ぐんぐん成長する時期なので、ママの自己判断で飲む量・食べる量を減らすのはNGです。
<対処法>
授乳回数が多い、離乳食を食べすぎるなど、気になることがあったら小児科医や保健師などに相談し、適切な与え方を教えてもらうといいでしょう。
また、体を動かす時間が少なくないか、生活リズムを見直してみることも大切です。
赤ちゃんの体重気がかりQ&A
【Q】 欲しがるだけ母乳を飲ませていたら、1ヶ月間で1400gも体重が増えてしまいました。肥満が心配なので、授乳回数を減らしたほうがいいでしょうか(1ヶ月)
【A】 3ヶ月ごろになると自分で飲む量を調節できるようになります
1ヶ月ごろは脳の満腹中枢の発達が不十分なため、必要以上に飲んでしまうことがありますが、3ヶ月ごろになると、自分で飲む量を調節できるようになります。授乳間隔が2~3時間空いているなら、欲しがるだけ飲ませて様子をみましょう。
頻繁に欲しがり授乳間隔が空かない場合は、泣いたらすぐ飲ませるのではなく、抱っこしてしばらくあやしてみて。抱っこだけで落ち着くこともありますよ。
【Q】 出生時は3800gと大きめでしたが、その後あまり体重が増えません。大丈夫でしょうか。(3ヶ月)
【A】 体重増加の経過を見て、少しずつでも増えていれば心配いりません
大きめで生まれた赤ちゃんは、体重増加が少し緩やかになっただけでも、体重が減ってしまったような錯覚を起こしがち。身体発育曲線に照らし合わせて体重増加の経過を確認し、少しずつでも増えているなら、しばらく様子を見て大丈夫です。体重増加がストップした、横ばい状態が続いている、少しずつ減っているといった場合は、小児科医に相談を。
【Q】 体重が10kgくらいありましたが、インフルエンザにかかって300g減ってしまいました。発育に影響は出ないでしょうか。(11ヶ月)
【A】 一時的に体重が減っても、回復後に増えてくれば大丈夫
インフルエンザが原因で具合が悪く、食欲が落ちたことで一時的に体重が減ってしまうことはあります。減ったのが元の体重の3%程度で、回復して食欲が戻ったあと、また順調に増え始めるようなら心配いりません。そのまま体重が減り続けたり、発育曲線のカーブから大きく外れてきたときはほかに原因があるかもしれません。小児科医に相談してください。
【Q】 2300gと小さめに生まれ、今も身長・体重ともに発育曲線の下のほうです。同じ月齢の子に追いつけるでしょうか。(10ヶ月)
【A】 ゆっくりペースで成長する様子を見守って
小さめで生まれても、身体発育曲線のカーブに沿って少しずつでも大きくなっているなら大丈夫です。また、首すわりやおすわりなどの発達に問題がなければ、今後の成長に大きな影響はないでしょう。
赤ちゃんのころは小柄でも、思春期に急に大きくなる子もいます。その子なりに成長する姿を見守って。
赤ちゃんの体重の増え方は個人差が大きい上、コンスタントに増えていくわけでもないので、何かと心配になりますね。
身体発育曲線から少し外れていても、その子なりに大きくなっていて、毎日元気に過ごせているのなら問題ありません。日々成長しようとしている赤ちゃんの力を信じ、応援してあげましょう。
(取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部)


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い