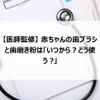【医師監修】子どものトラブル知らずの口と歯は“くう・ねる・あそぶ”で育つ!
「歯磨きしていればむし歯の心配なし!」「甘いものを控えてバランスのいい食事習慣でお口は健康☆」そう思いがちですが、どうやらそれだけでは十分とは言えないようです。
お子さんの口と歯を健康に保つポイントについて、日本小児歯科学会認定専門医で、多くの保育園や小学校の歯科健診にも携わる、鈴木さち代先生に聞きました。
むし歯などのトラブルは運動不足も原因の一つ!?
お子さんの口と歯は、体の発育発達とつながっているって知っていましたか?
「かむ」「すりつぶす」「飲み込む」などの口・歯・頬の動きは、体幹を養う運動をしっかり行いながら、食べさせ方などの生活習慣に注意を払うことで上手にできるようになります。逆に、口・歯・頬の動きが十分にできていないと、固いものなどはイヤなどの好き嫌いが増えたり、むし歯や歯並びに心配をかかえることも。
健やかな口と歯を育てるいちばんの近道は、お子さんが“くう(食べる)・ねる・あそぶ”を存分にバランスよくすること。
「うちの子、大丈夫かな?」と思ったら、次のポイントを確認してみましょう。
健やかな口と歯を育てる“くう・ねる・あそぶ”のポイント
●体幹を養う運動感覚を育てる遊びをする
いちばんのおすすめは、なるべく歩くこと。
そして、走る(例:鬼ごっこ)、転がる(例:マット運動)、ぶら下がる(例:鉄棒)、ジャンプする(例:トランポリン)・渡る(例:平均台を歩く・揺れる(例:ブランコ)・はいはいするなどの体幹を養う運動遊びを取り入れましょう。
砂遊びなど感覚を刺激する手指を使う遊びもいいでしょう。
●おなかをすかせておいしく食べる
“おなかペコペコ”で食べる食事のおいしさが体感できるように、運動遊びをたくさん行いながら、おやつやジュースの与えすぎに注意し食事リズムを整えましょう。
空腹で食べる食事は、栄養の消化・吸収もよくなり、食への関心も高まります。調理のお手伝いや家庭菜園もいいですね。
●一口量が最適か確認する
食べ物を頬張って両方の頬がふくらむ子は、一口量(※)を減らすように気を配りましょう。
おにぎりなどを一口分かじり取ったら口を閉じて食べるように促し、飲み込んでから次の一口を食べるように声かけを。食事中は食べ物を水分で流し込まないように注意します。
しっかりかめば唾液も出て、水分がなくても飲み込めるように。
※一口量・・・お子さんが食べ物を一口分かじり取った量
●早寝早起きの生活リズムを整える
夜の就寝中は成長ホルモンが分泌され、脳も整理される大事な時間。夕食時間や就寝時間が遅くならないようにし、朝は早めに起こして朝日を浴び、体を目覚めさせましょう。
朝食が進まなければ、夕食は思い切って少なめに。残りを朝食に回してみることはおすすめです。
朝の仕度がラクになる上、空腹で起きるので朝食がおいしく食べられます。就寝前にテレビやタブレットを視聴すると眠れなくなります。就寝1時間前は見せないように。
●口や顔の感覚を育てる
口まわりや口の中を触られるのが苦手だと、歯磨き嫌いになることも。鼻水をふき取ったり口まわりをふかれることを嫌がる子も、まずは全身をぎゅっと抱きしめてリラックスさせるのがおすすめです。
背中が丸くなるように抱っこしたり、あお向けの状態で両足をおなか側に押し上げ、腰を伸ばしてあげるのもいいでしょう。アップップーなどの変顔遊びで顔や口まわりを自分で触る・引っ張る、おうちの方に触られる・引っ張られる経験も大切です。
人間の口は生きるために食べ物を体内に入れる、いわば“命の入り口”なので、手指よりも敏感です。
腸管の一部でもあるので、体調不良などのシグナルを発することもある重要な場所。3~6ヶ月に一度は歯科医院で口と歯の状態を診てもらうと安心ですね。
(取材・文/茶畑美治子 イラスト/くにともゆかり)
初回公開日 2019/12/3
育児中におススメのアプリ
アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数・生後日数に合わせて専門家のアドバイスを毎日お届け。同じ出産月のママ同士で情報交換したり、励ましあったりできる「ルーム」や、写真だけでは伝わらない”できごと”を簡単に記録できる「成長きろく」も大人気!
ダウンロード(無料)育児中におススメの本
最新! 初めての育児新百科 (ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ)
大人気「新百科シリーズ」の「育児新百科」がリニューアル!
新生児から3歳まで、月齢別に毎日の赤ちゃんの成長の様子とママ&パパができることを徹底紹介。
毎日のお世話を基本からていねいに解説。
新生児期からのお世話も写真でよくわかる! 月齢別に、体・心の成長とかかわりかたを掲載。
ワンオペおふろの手順など、ママ・パパの「困った!」を具体的なテクで解決。
予防接種や乳幼児健診、事故・けがの予防と対策、病気の受診の目安などもわかりやすく紹介しています。
切り取って使える、「赤ちゃんの月齢別 発育・発達見通し表」つき。



 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い