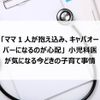切り傷・すり傷は消毒しない!乾かさない!新しい考え方【日本外来小児科学会リーフレット検討会より】
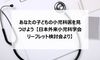

子どもはいろいろなケガをしますよね。血がにじむ程度のすり傷や切り傷など、「病院へ行くほどじゃないけれど・・・」という軽いケガのとき、みなさんはどのようにしていますか?まず消毒して、ガーゼをあてると、乾いてかさぶたができて・・・ですか?でも、消毒はしみるし、ガーゼをはがすとき痛いし、また血がにじんできますよね。本当にこの方法でいいのでしょうか?
ご家庭でできる傷の手当てについて、痛くなく、あとが目立たないウェット療法を紹介します。ウェット療法は湿潤(しつじゅん)療法とも呼ばれます。
この情報は「日本外来小児科学会 リーフレット検討会」の小児科の先生方がお母さん・お父さんに伝えたい内容を「たまひよ」と一緒にまとめたものです。
傷を消毒し、乾かし、ガーゼをあてることにはデメリットが!?
切り傷やすり傷があるケガをしてしまったとき、消毒し、乾かして、ガーゼをあてるというケアにはデメリットがあることがわかってきました。
・消毒することのデメリット
消毒液は細菌やウイルスを殺しますが、治そうとする細胞も殺してしまい、皮膚が元に戻る力を奪います。
・乾かすことのデメリット
傷からしみだすジクジクした浸出液(しんしゅつえき)には、白血球や皮膚の細胞の再生を促す成分がいっぱい含まれます。乾かすと傷の保護ができないので、回復が遅れるだけでなくきれいに治りません。
・ガーゼをあてることのデメリット
傷が治るための大切な浸出液を吸い取ってしまいます。また、ガーゼ交換のときにせっかくできた新しい皮膚の細胞を一緒にはがしてしまうので、痛くて出血もし、回復は遅れます。
ウェット療法の基本的な考え方とメリットについて
「消毒しない」、「乾かさない」、「ガーゼをあてない」で、痛みが少なく、きれいに傷を治す『ウェット療法』が今、注目されています。3つのポイントについて紹介します。『ウェット療法』は『湿潤療法』とも呼ばれています。
1 傷は消毒しないで、きれいに洗う
消毒液を使わないので、皮膚の細胞の自然治癒力が失われません。毎日洗うことで、化膿(かのう)の原因となる泥や死んだ組織などの異物は洗い流され、きれいな傷の表面が保たれます。
2 傷は乾かさない
傷は浸出液でおおわれるので、細胞が早く再生します。かさぶたができないので、きれいに治ります。
3 ガーゼをあてない
浸出液を吸い取らずに、傷の表面の潤った状態を保てます。ガーゼをはがすことによる、再生した細胞のダメージをふせげます。
ウェット療法のメリット
ウェット療法のメリットは、
1. 痛くない
2. 治りが早い
3. 処置が簡単
4. かさぶたができないままきれいに治る
と考えられています。ケガの際には傷を消毒せず、よく洗いガーゼをあてない「ウェット療法」が有用です。
ご家庭で対応可能な傷の具体例について
ちょっとした切り傷やすり傷などでは、ことさら医療機関を受診する必要はありません。3つの例を紹介します。頰のこの程度の「すり傷」(写真1)では、ご家庭でのウェット療法で十分対応可能です。左のまぶたの傷(写真2)も、まぶた全体がやや腫(は)れた感じはあるものの、ウェット療法のみで翌日には腫れが引き、数日後には治ってしまいました。右手の中指をドアに挟んだこのような傷(写真3)でも、多少の出血はあっても、つめの色に変化がなければ問題ありません。途中から、傷を痛がる、傷の周囲が腫れて赤みを帯びた場合は別として、ご家庭で治療可能な傷も多いのです。
(写真1)
(写真2)
(写真3)
病院で診てもらったほうがいいケガ・傷について
以下の項目にあてはまる場合は、家庭のウェット療法は行わずに、医療機関を受診してください。
1.動物や人にかまれた傷
2.骨や筋肉が見えている傷
3.傷がジグザグしていたり、開いていたり、出血がなかなか止まらない場合
4.傷の中に木くずやジャリなどの「異物」が残って取れそうにない場合
5.大きな水ぶくれができていたり、破れていたりするやけど
6.電気カーペット、湯たんぽによる低温やけど
ご家庭でできるウェット療法
ここでは食品包装用ラップフィルムを用いての簡単なウェット療法を紹介します。ドラッグストアで販売されているワセリン、サージカルテープを準備します。食べ物を包むためのラップフィルムは、人体に害はなく心配はいりません。
① 水道水で傷と周囲を洗い流す。
② 出血している場合、清潔なガーゼなどで押さえ圧迫する。
③ 出血が止まったら、ラップフィルムに直接ワセリンを塗り、傷にあてる。
④ ラップがズレないようにサージカルテープでとめる。包帯で巻いてもいい。(入浴可)
⑤ 1日1回、傷をよく洗う。(消毒不可) ③、④を繰り返す。
⑥ ツルツルの新しい皮膚ができたら「治った」と判断。通常は4、5日です。
夏など汗をかきやすく、あせもができやすい時期は1日に数回交換してください。浸出液が多い場合にも、こまめに交換してください。
※ラップの箱には「食品包装用途以外には使用しないでください」と記載してある点をご承知おきください。
ラップフィルムを用いたウェット療法の実際
ラップフィルムへのワセリンの塗り方は、難しいものではありません。パンにバターを塗るのと同じ要領とお考えください。下の写真は、1歳の子の手のひらのやけどを、ご家庭でラップを用いたウェット療法で処置したものです。子どもの手の動きは激しいので、テープで固定してもラップフィルムが外れそうなときは、その上を包帯でグルグル巻きにしてもかまいません。2週間後には、きれいに治っています。
1歳の手のひらのやけどです
ラップフィルムにワセリンを塗ります
ワセリンを塗った側を手のひら側にあて、テープで固定します。
2週間後にはここまできれいに治っています。
ウェット療法で注意をしなくてはいけないことってどんなこと?
ウェット療法を行っているときに注意をしなくてはいけないことについて。
【1】におい
ラップフィルムとワセリン交換の際、独特のにおいがすることがよくあります。これは、皮膚の常在菌や分泌物が臭気を帯びたもので、化膿(かのう)しているわけではありません。
【2】化膿
傷が化膿した場合は、痛がったり、赤く腫れてきます。そのようなときは受診してください。
ウェット療法にはたくさんのメリットがありますが、残念なことにまだすべての医療機関で対応してくれるわけではありません。この療法を行っている身近な医療機関を把握しておくといいでしょう。
(文/日本外来小児科学会リーフレット検討会 写真提供/佐久間秀人先生 イラスト/杉井亜希 構成/ひよこクラブ編集部)
■監修/日本外来小児科学会リーフレット検討会
日本外来小児科学会リーフレット検討会は、子どもの病気、健康、安全、生活など、子どもを取り巻くすべてのことがらに対してリーフレット制作に取り組んできました。この活動の1つとして、保護者や子どもにぜひ知っておいてほしい情報を記載したコンテンツを「たまひよ」と一緒に作成し、オンラインで発信していきます。
日本外来小児科学会 は1991年に設立された学術団体です。
【おすすめのホームページ】
「新しい創傷治療 」
「ウェット(湿潤)療法 」


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い