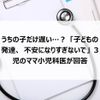指しゃぶり、実は大切。手指の操作性、口内の触覚の発達を促す・3児のママ小児科医


今回のテーマは、「指しゃぶりをしていて心配」というお悩みです。3児を子育て中のママ小児科医・藤井明子先生が、日々の診療の中でママ・パパたちから寄せられたお悩みについてのアドバイスや、日々の子育てに頑張っているママ・パパに伝えたいさまざまな情報を発信します。「ママ小児科医の笑顔便り」#2
赤ちゃんが自分の意思で指しゃぶりをするのは生後5カ月ごろから
妊娠期におなかの赤ちゃんの超音波(エコー)写真で、赤ちゃんが手を口元にもっていっている様子をみたことがあるかもしれません。まるで、赤ちゃんが指しゃぶりしているように見えるかもしれませんね。
赤ちゃんは胎生24週ごろから指を吸うようになり、胎生32週くらいになると指を吸いながら羊水(ようすい)を吸うことができるようになります。おなかの中で吸うことを練習することで、生まれたばかりの赤ちゃんもおっぱいを吸う=吸啜(きゅうてつ)することができます。
出生後すぐはおっぱいを吸うことのみで、指を吸ったりすることはあまりみられません。生後2~3カ月になると、グーでにぎった手をなめたり、親指をなめたり、指をくわえたりする赤ちゃんも見られるようになります。
生後5カ月になると、手を自分の手として認識するようになるハンドリガードや、自分の意思で指しゃぶりをするようになります。
そして、7カ月ごろになると歯が生え始める赤ちゃんもいて、指しゃぶりをしすぎると、前歯が前に出すぎたりして、歯並びが悪くなるのではないか…と心配されるママ・パパもいます。
1才くらいまでの指しゃぶりは見守っていてOK
歯が生え始めるころになると、指だけでなく、おもちゃなどいろいろなものをしゃぶるようになります。
目で見て、口に持っていく、口の中での感覚を知るという、視覚、手指の操作性、口内の触覚の発達が促されているからです。
ずっと口に入れるだけでなく、おもちゃの遊び方、手指の操作性などの発達がさらにすすむと、指をずっとしゃぶっているということは減っていきます。
1才くらいまでの指しゃぶりは、「今、手指を動かす練習をしているんだな」「口の触覚を確かめているんだな」などと、温かく見守ってあげましょう。
1才を過ぎるころになると、はいはいもさかんになったり、つかまり立ちをしたり、なかには歩いたりして、行動や興味の幅も広がって、自然と指しゃぶりの時間が減っていきます。
お昼寝や夜の寝かしつけのときに指しゃぶりが残る場合がありますが、この場合でも無理に指しゃぶりを離させる必要はありません。
ただし、日中もずっと指しゃぶりをしていて、両手でおもちゃを操作しながら遊ぶような様子が見られない場合には、注意が必要です。
指しゃぶりする時間が長時間だと、歯並びに影響することがあるからです。
指しゃぶりをやめさせたい…興味のあるおもちゃで気を引いてみて
1才を過ぎて、日中も指しゃぶりをしている場合には、まずはどういうときに指しゃぶりをしているのか見てみましょう。
①ママやパパが少し離れた場所にいて、赤ちゃんに一人でテレビ番組を見せているとき
②一人でおもちゃを使って遊んでいるとき
③大人に絵本を読み聞かせしてもらっているとき
…などかもしれません。
①や②など、一人でいるときに指しゃぶりしている子には、大人が一緒に遊んで、指しゃぶりしている手を、おもちゃの操作へと促すといいかもしれません。
指しゃぶりをさせないように、口から指を抜くというより、興味のあるおもちゃに気を引くことで、口にある手指をおもちゃのほうにもっていくという、お子さんが自発的に手を動かすように促せたらいいと思います。
③など、手を使わない遊びや片手しか使わない遊びで指しゃぶりしているときは、両手を使ったおもちゃの遊びが楽しいな、と遊びの幅が広がると、しだいに指しゃぶりの時間は減っていきます。
両手を使った遊びは、たとえば、
・いないいないばあ
・積み木を両手で積んでできたら両 手でぱちぱち
・押したりゆらしたりすると音が鳴るおもちゃを鳴らしてみる
などもいいでしょう。
また、2才を過ぎての両手を使う遊びは、
・指先を使って、ひもとおしする
・コップを重ねる
・粘土をこねたり丸めたりする
などの遊びもいいかもしれません。
一人遊びよりも、親御さんと一緒に遊ぶ+両手を使った遊びを取り入れてはいかがでしょうか。
監修・文/藤井明子先生 構成/ひよこクラブ編集部
赤ちゃんの指しゃぶりは、発達とともに自然と頻度が減っていきます。しかし、1才を過ぎても回数が減らない、長時間の指しゃぶりが気になるようなら、大人がほかに興味を持てる遊びに誘ってあげるといいですね。親子で一緒に遊ぶ時間を増やして、様子をみてみましょう。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い