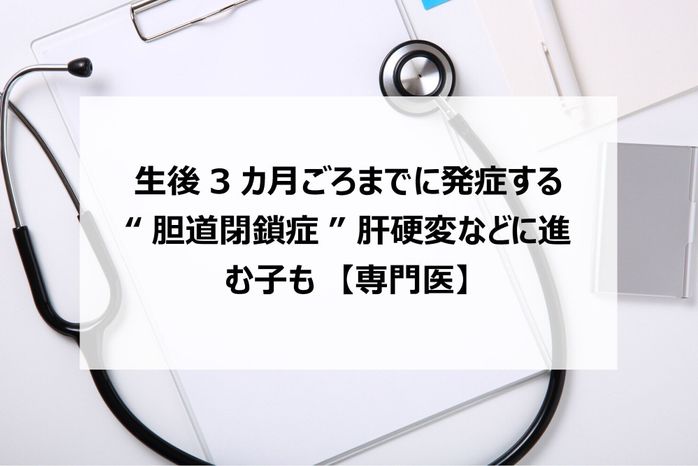生後3カ月ごろまでに発症する“胆道閉鎖症”肝硬変などに進む子も 【専門医】
「胆道閉鎖症」(たんどうへいさしょう)という病気を聞いたことがありますか。胆道閉鎖症は、新生児から3カ月ごろまでに発症する病気です。時には命にかかわることもあるため、1カ月健診で見逃さないことが重要です。胆道閉鎖症に詳しい、横浜市東部病院小児肝臓消化器科 部長 乾あやの先生に話を聞きました。
新生児から3カ月ごろまでに発症するも、乳幼児健診で見逃されてしまう場合が
胆道閉鎖症は、新生児から3カ月ごろまでに発症する病気で、胆道形成異常説、ウイルス感染説などもありますが原因は不明です。
「胆道閉鎖症は、肝臓でつくる消化液(胆汁)を十二指腸に流すための通り道である胆管が、何らかの原因で破壊され閉塞(へいそく)し、肝臓から腸に胆汁を流せなくなる病気です。胆汁が腸に流れなくなると、肝臓の中にたまってしまい、肝細胞が破壊されて、悪化すると肝硬変に至る予後不良な病気です。そのため早期発見が大切です。
胆道閉鎖症の原因は不明ですが、アジア人に多く、女の子のほうが男の子よりも発症率が2倍高いことがわかっています。また胆道閉鎖症になる子は、約1万人に1人といわれています。約1万人に1人とは肝臓の病気としてはめずらしいわけではないのですが、1カ月健診などでしっかりうんちの色を確認しないと見逃されてしまうこともあります」(乾先生)
胆道閉鎖症は早期発見、早期治療(手術)がカギ! 便色カードの活用を
胆道閉鎖症は、おしっこやうんちの色の変化でママやパパが気づくケースが多いと言います。
「おしっこは、濃いウーロン茶のような色です。うんちは白やうすい黄色で、母子健康手帳に載っている“便色カード”の1~3番です。
ビリルビンは胆汁色素で、赤血球中のヘモグロビンが肝臓や脾臓(ひぞう)などで壊されたときにできます。健康な子は、うんちによってビリルビンが体外に排出されるので、便色カードの5~7番の色のうんちが出ます。
胆道閉鎖症は、薬で治療できる病気ではありません。診断がついたら、手術を行いますが、手術はできるだけ早いほうが望ましいです。そのためには早期発見が必要なため、新生児期から3カ月ごろまでは母子健康手帳にある“便色カード”を活用して、うんちの色を見比べる習慣をつくりましょう。
1~3番の色を疑うときは、すぐに受診してください。1カ月健診では、必ず便の色を健診するお医者さんと一緒に確かめてください」(乾先生)
便色カードは、厚生労働省の通達により2012年4月から全国の母子健康手帳に掲載されていますが、日本胆道閉鎖症研究会調べでは、便色カードなどを用いたスクリーニング(ふるい分け)による早期診断例が増えていることがわかっています。
「栃木県では、19年間にわたり新生児(31万3230例)をスクリーニングし、全国平均と比較した結果、葛西手術(胆道閉鎖症の手術法)を受けた月齢の平均は、スクリーニング開始前は生後70.3日でしたが、スクリーニング開始後は生後59.7日に。10.6日も手術が早く受けられるようなったというデータがあります。早い治療開始は、予後にも影響します」(乾先生)
便色カードには生後2週、1カ月、1~4カ月のうんちの色を記入する欄があるので、記入して1カ月健診時などに診てもらいましょう。
「便色カードは、カナダや台湾でも使われています。台湾では、生後60日以前 の葛西手術例が49.4%から65.7%に増加したという報告もあります。
カラーチャートなので、日本でも“便の色が忠実に表現できていない”などの指摘はありますが、ママやパパが見たときに異変に気づくには有効です」(乾先生)
胆道閉鎖症で怖いのは合併症! 肝硬変や肝不全に進むケースも
低月齢の赤ちゃんの手術と聞くと「できることなら回避したい」と思うママやパパもいるでしょう。しかし胆道閉鎖症は、早期手術が必要です。理由は、なぜでしょうか。
「胆道閉鎖症は手術しなければ、肝臓が徐々にかたくなり、やがて肝硬変となり、さらに悪化すると肝不全に進みます。このような場合は、腹水がたまったり、栄養状態が悪くなったりして、赤ちゃんの発育・発達にも影響をおよぼすので肝臓移植が必要になります。
また胆道閉鎖症になると、ビタミンKが体内に吸収されにくくりなります。ビタミンKが不足すると内出血を起こしやすくなり、脳内で出血すると、その後脳性まひなどの原因にもなりますし、死亡してしまうこともあります。こうしたことを防ぐためにも、早期発見、早期手術をして、胆汁を腸に流すことが必要です」(乾先生)
胆道閉鎖症は、実は手術をしても完治するのは難しい病気です。術後も定期的に通院し、経過観察、治療をしていく必要があります。
「日本胆道閉鎖症研究会の調べでは、胆道閉鎖症の10年生存率は87.8%、10年自己肝生存率は53.2%というデータもあります。早期発見、早期手術をすることで、自分の肝臓で少しでも長く生きられる可能性は広がります。
胆道閉鎖症の専門は小児外科ですが、早期発見のためには、小児内科や産婦人科との連携が欠かせないと思います」(乾先生)
お話・監修/乾あやの先生 取材・文/麻生珠恵、ひよこクラブ編集部
乾先生は「胆道閉鎖症は、うんちの色が毎回白っぽいわけではないので、1回でも“おかしい”と思ったら、念のため小児科へ。胆道閉鎖症の疑いをまったく持たないなど診断に不安を感じたときは、念のため小児科あるいは小児外科のある総合病院などを再診したほうがいいでしょう」と言います。
乾あやの先生(いぬいあやの)
profile
済生会横浜市東部病院 小児肝臓消化器科部長 専門は肝臓、感染症、代謝異常。日本小児科学会専門医、認定小児科指導医、日本肝臓学会専門医・指導医、小児栄養消化器肝臓学会認定医、日本胆道閉鎖症研究会役員。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い