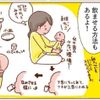「放射能を計る線量計を首から下げてキャンプに…」福島の子どもたちとキャンプを10年、心の傷を癒す専門家たち
2011年3月11日14時46分。東北地方を未曾有の大震災が襲いました。日本中が呆然となり、生活に必要な物資などを優先せざる得ない日々のなか、子どもたちの心の傷を癒したいと動いた専門家たちがいました。臨床心理士、教師、そして野外活動の専門家が一丸となり、被災地の子どもたちの心のケアをすることを目的に、「みどりの東北元気キャンプ」の企画が立ち上がったのです。そしてわずか4カ月後の7月には第1回キャンプを開催、その後2019年まで試行錯誤を繰り返しながら、計22回のキャンプを実施、合計1000名の福島の子どもたちが参加したといいます。この「みどりの東北元気キャンプ」について、主催者のひとりであり、キャンプディレクターを務めた大熊雅士さん(現小金井市教育長)に、たまひよONLINEが話を聞きました。
前編では、キャンプを企画した理由と被災した子どもたちのキャンプ場での様子についてです。
震災で受けた子どもの心の傷を癒すために
ーーー 「みどりの東北元気キャンプ」を企画したきっかけを教えてください。
大熊雅士さん(以降大熊):郡山で教員をしていた教職大学院時代の教え子から、彼のクラスに転校してきた津波に遭った子のケアを相談されたことがきっかけです。僕だけではちょっと手に負えなかったので、同じく東京学芸大学教職大学院教授で教育臨床心理学が専門の小林正幸先生に相談したところ、子どもとのケアや関わりについて丁寧にアドバイスをくれました。
実は2000年から小林先生や仲間と一緒に、学校の友達や先生との関係において何らか傷を負った子どもたちを対象とした「不登校げんきキャンプ」を実施していました。第1回のキャンプに参加した小金井市の適応指導教室の生徒24人のうち20人が学校復帰を果たしたことから「奇跡のキャンプ」と呼ばれ話題になりました。
その知見やノウハウを生かせば、震災で受けた心の傷を癒すことのできるのではないかと、すぐに企画を練り始めました。
ーーー 企画からキャンプ開催まで4カ月。かなり早かったですね。
大熊:一刻も早く開催したかったので、すぐに企業を回ってスポンサー探しを始めました。幸いなことに僕たちの企画に賛同した東急不動産や三井物産がスポンサーになってくれて、2011年7月に第1回を、その後2019年まで計22回の「みどりの東北げんきキャンプ」が実施できました。
次はキャンプの参加者集めです。実際に何度も福島に行って、避難所を回ってキャンプに誘うのですが、そのたびに周囲の大人からは「キャンプなんて遊びを今頃やれるわけない」と罵倒されました。後にも先にもあんな風に誰かから罵倒されたことはなかったです……。そりゃそうですよね。震災からまだ数カ月しか経っていませんでしたからね。
他の同様の活動はほとんどが無料だったのに対して、「みどりの東北元気キャンプ」では、食事代は実費で5000円いただいていたこともあって、爆発的に参加者が増えることはありませんでした。でも、キャンプに参加したことで子どもの心の成長が促されることが口コミで広がっていくと、特に宣伝しなくても、参加者が集まってくるようになり、10年間、キャンプを続けることができました。
放射能を測る線量計を首から下げた子どもたち
ーーー いよいよキャンプが始まります。
大熊:第一回のキャンプは、震災からわずか4カ月後の7月。まだその傷跡が生々しい時期でしたから、マスクだけでなく、放射線量を測る線量計を首から下げて参加した子どもも複数いました。
福島の原発とのキャンプ場のある小野川湖の間には安達太良山があるので、放射能の心配はないとわかっていましたが、子どもたちはマスクを取ろうとしません。だから、実際に僕が線量計でキャンプ場の線量を測ってみせて、「ここは安心だからマスクをしなくても大丈夫だよ」と言いながら、子どもたちにマスクを取らせることから始めました。
このキャンプを手伝ってくれたのは、小林先生はじめとする心理の専門家、豊かな人間性を育むことを目的とするプロジェクトアドペンチャープログラムを学んだ教員、そして全国から集まったキャンプの専門家。それぞれの分野のプロともいえる人たちです。僕がキャンプディレクターを務めることになりました。
ーーー 実際の活動に参加した子どもたちはどんな様子でしたか?
大熊:キャンプ初日に「湖で遊ばないか?」と誘ったときも、参加した子どものうちの何人かは水に入れませんでした。まるで、冷たいプールに入るのをためらっているように、とにかく水を怖がるんです。湖に足をちょっと足をつけるだけで、すぐに上がってきてしまいました。
でも大人は、水に入らない理由も聞かないし、「がんばってみよう」と声をかけることもしません。私たちは「『がんばろう』と言われた子どもは『できない自分』に気付いて、自己肯定感を下げてしまう」と考えていたからです。
キャンプ中は、子どもたちが無理することのないように、また子どもに関わる大人たちが間違った対応をしないように、常に小林先生たち心理の専門家がいつも少し離れた場所で見守っていました。
自分からやりたいことに近づいて行く
ーーー 子どもたちはどんな風に変わっていったのでしょうか?
ツリーハウスを作ったり、カヌーで湖を横断したり、ツリークライミングをしたりなど、さまざまな活動を用意しました。初日の夜には、それぞれの活動のキャプテンのプレゼンを聞き、翌朝、子どもたちは、やりたいこと、挑戦してみたいことを自ら選択するのです。
第一回のキャンプで、私がキャプテンをしていたツリーハウス作りに参加していたある男の子の話です。ツリーハウスがだんだんできてきて湖の見える高さまで来たとき、彼がポツリと「カヌーに乗りたい」と言ったんです。とはいえ、微かな気持ちの高揚だけで動くとまたダメになってしまう可能性もあります。
彼なりにカヌーではなくツリーハウスを選んだ理由も、湖を見てカヌーに乗りたくなった理由もあるのでしょうが、大切なことは、誰かに言われたからではなく、この子自身が勇気をもって、あきらめずに「自分からやりたいことに近づいて行く」ことです。自信を付けたこの男の子は、その後、楽しそうにいろいろな活動に参加していました。
このようにそれぞれの子どもたちが、キャンプに参加して自信をつけていく姿に僕たちも勇気付けられました。
取材・文/米谷美恵 写真提供/大熊雅士
次回は、キャンプでの子どもたちへの具体的な対応方法などについてお聞きします。
大熊雅士さん
profile
14年間の公立小学校に教諭として勤務した後、東京都教育相談所いじめ電話相談員、小金井市・江戸川区教育委員会、東京都教職員研修センター指導主事、葛飾区立小学校副校長を歴任。東京学芸大学付属世田谷小学校教諭、東京学芸大学教職大学院特命教授、カウンセリング研修センター学舎「ブレイブ」室長を経て、現在小金井市教育委員会教育長、文部科学省の教育課程編成委員、不登校対策委員、ITを活用した不登校対策委員。みどりの東北元気プログラムをはじめとするさまざまなキャンプ、遊び場を主催、多くの子どもに寄り添っている。その豪快ともいえる人柄を慕う教え子も多い。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い