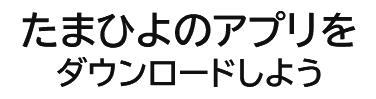【最新治療】“不思議な病気”といわれるランゲルハンス細胞組織球症。ママ・パパの「なんだかおかしい…」が早期発見に
小児がんの1つに「ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)」という病気があります。まれな病気ですが、発症時期は乳幼児期が多く、一度発症すると何度も再発したり、数年たってから新しく合併症を生じたりすることがあり、長期のフォローアップが重要になります。LCHの最新治療と課題について、この病気の治療・研究を専門的に行っている国立成育医療研究センター小児がんセンター血液腫瘍科医長の塩田曜子先生に聞きました。
自然に治ってしまうケースもあれば、命にかかわる危険な事態になることも
「ランゲルハンス細胞」は皮膚や気道、消化管などに存在する免疫細胞。LCHは、この種類の未熟な細胞が骨髄で作られる段階で異常を起こした病気で、体中のあらゆる部位で炎症を引き起こし、肉芽、壊死(えし)、組織や骨の破壊などを生ずることがあります。
全身の臓器に広がって重症化する例がある一方で、1カ所にとどまり自然に治ってしまうケースも少なくなく、また、罹患(りかん)する人も少ないため、“まれで不思議な病気”といわれてきました。
「医学部ではこの病気のことを小児科で習いますが、珍しい病気のため、教科書の片隅に書かれている程度で、しかも『ヒスチオサイトーシスX』と呼ばれていました。組織球の病気のようだけれどもよくわからないから“X”と表現されていたのです。
1980年代に、ランゲルハンス細胞と同じ特徴を持つ異常な細胞がLCHの正体とわかり、病気の名前が変わりました。一般診療の現場でLCHの患者さんを診る機会はとても少なく、いざ患者さんを診たときに確定診断までにかなりの時間を要してしまうことも多かったため、“みなしご病”ともいわれてきました」(塩田先生)
そんなLCHの診断・治療に光が見えるようになったのは、2010年のこと。ボストンの研究者によって、約半数のLCH患者さんの病変部の組織に「BRAF(ビーラフ)遺伝子」の異常があると報告されたことでした。
「BRAF遺伝子はいくつかのがんの発生にかかわる遺伝子として知られていて、変異したBRAF遺伝子によって細胞が異常に活性化され続けることを阻害する薬は、すでに大人のがん治療のために使われています。この発見を契機に、LCHに関する遺伝子研究が飛躍的に進み、『骨髄由来の腫瘍性疾患』として、がんの1つに分類されることになりました。子どもの場合は小児がんの専門医が治療にあたっています。
日本で LCH を発症する子ども(0~20才)の数は年間 60~70 人と推計され、国立成育医療研究センターには年間数人がこの病気を疑って受診しています」(塩田先生)
効果的な治療法がわかってきたけれど、それが効かないケースへの対応が課題
LCHは1つの臓器だけに病変が起こる「単一臓器型」と、複数の臓器に病変が見られる「多臓器型」があります。単一臓器型は幅広い年齢で発症がみられますが、多臓器型は子どもに多く、その8割は3才未満で発症しているそうです。
「病変が1カ所だと自然に治ってしまうこともあるのですが、多臓器型を乳幼児が発症した場合は重症化するリスクが高いため、早期に適切な治療を行うことがとても重要になります。
1980年代ごろから、どのような症状のLCH患者さんがどんなふうに元気に治っていったのか、世界中の専門医が患者さんの状態を見ながら治療の工夫を重ねてきました。
そして現在、多臓器型の治療は、ステロイド剤と化学療法(抗がん剤)を組み合わせて1年かけて行うのがスタンダードになっています。まず2カ月間入院して治療を行い、その後は外来で治療を続けます。退院後は普通の生活ができますし、みんな元気になっています。
しかし、『リスク臓器』といわれる肝臓、脾臓、骨髄を含む多臓器型を発症した乳幼児は急速に重症化し、スタンダードな治療では効果を得られないことがあります。その場合はすぐに強力な治療に変更したり、白血病やリンパ腫と同じように造血幹細胞移植を行ったりすることもあります」(塩田先生)
BRAF変異のある細胞の活性化を阻害する薬はすでに開発されていて、ほかのがんでは使われているとのこと。LCHでは使われていないのでしょうか。
「日本はもちろん世界中で、まだこの薬のLCHへの使用は認可されていません。海外の研究で、初めはとても効果があるものの、薬の使用をやめるとほぼ全例ですぐに再発してしまうことが報告されており、LCHに対する安全な使い方はまだわかっていません。また、小さなお子さんに対する副作用の検討も今後必要です。
しかし、この薬以外に命を救う方法がないと判断され、倫理審査委員会(※)の承認を受けた数例だけ、日本でもこの薬の使用が試みられました。
このような、重症化したLCHの治療法を確立させることが課題です」(塩田先生)
※臨床研究の倫理性、安全性、科学的妥当性を審査する委員会。病院ごとに設置され、担当医師から申請された事案について、承認・非承認の検討を病院内で行います。
「なんだかおかしい」というママ・パパの感覚が早期発見、適切な治療につながる
LCHは病気が治ったあとに残る「晩期合併症」にも注意が必要とされています。病気が発生した場所によって、難聴、手足の骨や背骨の変形などが見られるほか、LCHに特徴的なものとして、尿崩症は5年以上たっても新たに出現してきます。さらに成長障害、中枢神経障害なども見られることがあります。晩期合併症をケアするために、大人になっても定期的な観察が必要になります。
「欧米のデータでは、多臓器型では10年間の経過の中で70%以上に何らかの晩期合併症が出るとされてますが、日本の小児LCHの臨床研究では、多臓器型で40%ほど。だいぶ低くなっています。適切な治療を早期に行うことは、晩期合併症の減少につながっていると考えられます」(塩田先生)
LCHは子どもの発症例が多いとはいえ、全体としての発症数は少なく、かかりつけの小児科では判断できないこともありそうです。
「以前に比べると、LCHのことを理解している医師が増えてきていますが、多くの病気の中からLCHの可能性に思い当たるのはなかなか難しいというのが現状です。LCHの専門医は、1人でも多くの医師にこの病気を知ってもらうための活動も行っています。
中耳炎や皮膚トラブルが長引いていて、処方された薬を使っているのに改善しない、たんこぶがいつまでもひかないなど、いつまでもよくならない症状があるときはかかりつけ医から小児がんを扱う病院を紹介してもらい、詳しい検査を受けてください。
子どものLCHはかなり治療法がわかってきており、早期に適切な治療を行えば怖い病気ではありません。LCHを早期発見するには、日ごろからお子さんの様子を見ているママ・パパの『なんだかおかしい』という感覚がとても重要になります。
一方、私たち専門医は、LCHの再発と晩期合併症の減少および予防をめざして新たな治療法を探し出すために、世界中の研究者と連携して、研究を進めていきます」(塩田先生)
取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部
“みなしご病”といわれたLCHは研究が進み、治療法もかなり確立してきましたが、病気の認知度が低いという現状があるようです。「なんだかおかしい」と感じたときはそのままにせず、早めにかかりつけ医に相談しましょう。
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い