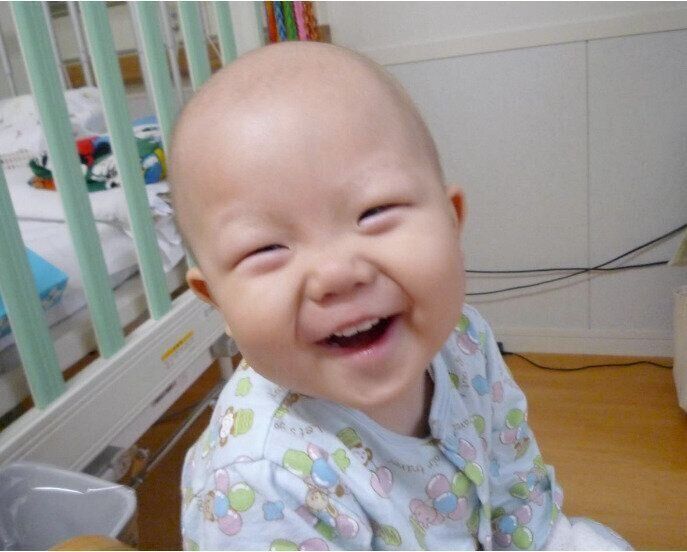「息子にもっと友だちを作ってあげたかった」病気の今を生きる子どもと、家族が笑って過ごせる『第2のおうち』をめざして【福岡子どもホスピス】
「福岡子どもホスピスプロジェクト」の団体職員として、小児がんや先天性疾患など重い病気や障害のある子どもと家族が過ごせる「子どもホスピス」の設立に向けて活動を進めている内藤真澄さん(58才)。内藤さんはひとり息子の駿くんが1才4カ月で白血病とわかり、2年間の闘病ののちにお別れとなってしまった経験を持ちます。内藤さんに、子どもホスピスがなぜ必要なのか、設立への思いや現在の課題などについて聞きました。
病気と闘う子どもの人生を豊かにしたい
最愛の駿くんが旅立ったあと、内藤さんは苦しい心を抱えたまま3年間ほど何も手につかず、外出もできない日々を過ごしていました。そんなとき、九州大学看護学部の准教授をしていた濱田裕子先生に出会い、大切な人を喪失した心のケアである“グリーフケア”のことを知ったきっかけで、自分の心に向き合うことができ、少しずつ外に出られるようになったそうです。駿くんの存在がいろんな人とつながるきっかけとなり、内藤さんは九州大学病院小児医療センター親の会すまいる代表や、福岡ファミリーハウスの理事を務め、闘病中や退院後の病気の子どもと家族にかかわる活動をするようになりました。
やがて、濱田先生が2009年に立ち上げた「福岡子どもホスピスプロジェクト」の活動に内藤さんも参加するようになっていきました。
プロジェクトは「病気の子どもと家族が一緒に笑い合って過ごせて、専門家に相談できる『第2のおうち』のような場所」を作ることをめざして、企業や自治体を回って協力を依頼しイベントなどで寄付金を募る活動をしています。
2021年6月、福岡子どもホスピスプロジェクトは、取引が10年以上ない「休眠預金」を民間公益活動に生かす国の事業に応募して採択され、助成を受けることに。九州大学病院に近い場所にホスピスの開設をめざして活動を続けています。
病気の治療のためにお友だちや家族と過ごすことが制限される子どもたちに、コミュニケーションの機会を作りたいという思いが強くあると言います。
「子どもホスピスは、治療が見込めない子どもと家族だけでなく、治療中の子どもにとっても人生を豊かに過ごす場所です。家族で一緒にごはんを食べる、おふろに入る、きょうだいと一緒に遊ぶ、そういうごく普通のことをできるように環境を整えてあげたいと思います。病気であっても、子どもは日々成長しますし、その人生が豊かであってほしい。そのためにお手伝いできることをしたい、というのが私たちの思いです。
駿が白血病の闘病中は、免疫力が下がってしまうために大部屋ではなく個室で私と2人きりで過ごすことが多かったんです。でもたまに大部屋で過ごすときには、病室のお友だちとブロックで遊んだり、ごっこ遊びをしたり、とても楽しそうな笑顔を見せてくれました。駿にはもっとお友だちを作ってあげられればよかった、大人だけでなく子ども同士の社会でもっと過ごすことができていたら、あの子の人生はもっと豊かだったんじゃないかな、と思うんです」(内藤さん)
子どもホスピスは難病児の家族の負担軽減や、精神的サポートの役割も
治療を受ける場合には病院で医療を受けますが、重い病気を持つ子どもや治療が見込めない子どもが自宅で過ごす場合には、家族が医療ケアを行うことになり、家族のだれかが疲れてしまうことも。そういうときホスピスを利用することができれば、専門スタッフに医療ケアを代わってもらうこともでき、家族の負担軽減にもなります。さらに子どもホスピスには、重い病気の子どもを持つ親の孤独を解消する役割もあるのだとか。
「福岡にある九州大学病院(以下、九大病院)は、全国に15カ所ある『小児がん拠点病院』の一つ。九州地方では唯一の小児がんの基幹病院です。九州は離島も多く、鹿児島や沖縄や奄美などからも重い病気の子が集まります。NICU(新生児集中治療室)やPICU(小児集中治療室)などでは面会時間が限られていることもあり、面会時間が過ぎたあとに親がどこで過ごすか、という居場所の問題があります。またもう一つ、親が不安と孤独を抱えているという問題もあります。
難病や治療の見込みが少ない子どもの親は、なかなか苦しい気持ちを他者に打ち明けることができません。ネットで情報を得ることはできますが、実際にだれかと話して役立つ情報を得たり、何気ない会話で不安な気持ちをやわらげたりできるコミュニティーがあれば、親の孤独や不安に寄り添うことができます」(内藤)
福岡子どもホスピスプロジェクトでは、病気の子どもと家族の受け入れだけでなく、入院中の子どもの家族が滞在できる機能も備えた施設を予定しています。現在、九大病院の近くには病気の子どもと家族の滞在施設として、内藤さんが理事をつとめる「福岡ファミリーハウス」があります。しかしこの施設は部屋数が少ない、借りている建物の老朽化などの課題もあると言います。
「ファミリーハウスは、検査や治療にきた子どもの親が安価で宿泊したり、滞在できたりする施設ですが、家族ごとの部屋に分かれていることもあって、ほかの家族とコミュニケーションを取れるようにはなっていませんし、子どもとの面会時間以外の時間を持て余してしまう、という声をよく聞きます。
そういうとき、子どもホスピスにも立ち寄れる環境であれば、同じような境遇の親御さんや、相談できる専門家に出会える機会になります。難病児が自宅で過ごすときに食べさせていいものや、どんな遊びをしたらいいのかなどの相談をすることや、病院では聞きにくいことも話すことができるかもしれません。あるいは、ホスピスで行う七夕やクリスマスのイベントの準備作業を手伝ったりすれば、何気ないコミュニケーションを通してほっとできる居場所になるのではないでしょうか」(内藤さん)
日本各地の子どもホスピス設置に向けて、議員連盟が発足
福岡子どもホスピスプロジェクトが受けている助成金の期限は来年度まで。「それまでになんとか開設までのめどをつけたい」と内藤さん。
「現在、最大の課題は土地です。来年度で助成金が終わってしまいますが、土地も建物もまだめどが立っていない状況です。九大病院と福岡市立こども病院に近い場所で建設できるよう、行政にも働きかけて、なんとか実現のめどをつけたいと考えています。そのためにできるだけ多くの人に子どもホスピスのことを知ってほしいと思います」(内藤さん)
休眠預金事業の採択を受けた子どもホスピスのプロジェクトは福岡のほかにも4団体あり、それ以外に、沖縄や福井、千葉、など全国各地で子どもホスピスのプロジェクトが次々に立ち上がっています。内藤さんは「それだけ必要な人たちがいるということ」だと話します。
「2022年11月に『全国こどもホスピス支援協議会』という与党の議員連盟が発足しました。これまで子どもたちの医療や福祉の問題に対応する窓口が、小児がんなどの病気は医療、障害のある場合は福祉、と分かれていることが課題でした。2023年4月からこども家庭庁が発足するにあたり、医療や福祉、教育などに分かれていた窓口の一本化を要望しています。さらにこの協議会をネットワークとして、各地のプロジェクトとつながりながら、各地の子どもホスピス設置の実現に向けて大きく動く流れができることを期待しています」(内藤さん)
お話・写真提供/内藤真澄さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
内藤さんは「子どもが『ホスピスに行きたい』と楽しみにできる場所をめざしたい」と言います。病気とともに生きる子どもとその家族に、寄り添い支援する存在が求められています。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることをめざしてさまざまな課題を取材し、発信していきます。
●この記事は個人の体験を取材し、編集したものです。
●記事の内容は記事執筆当時の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い