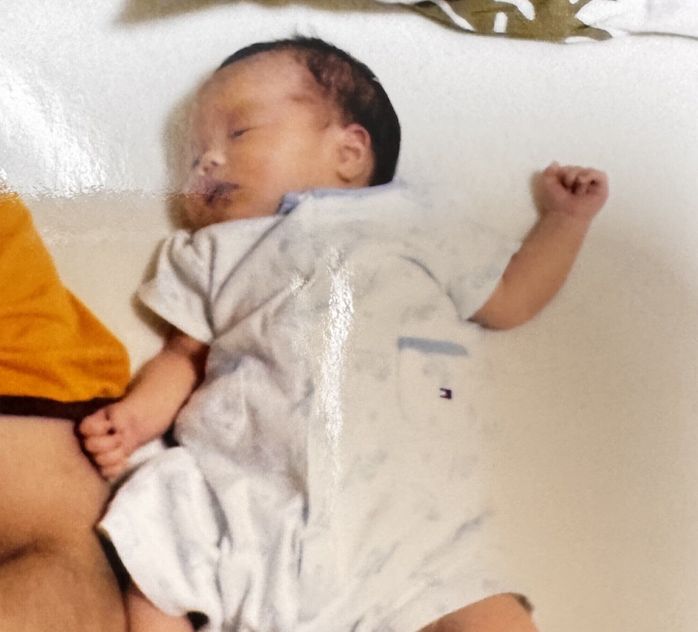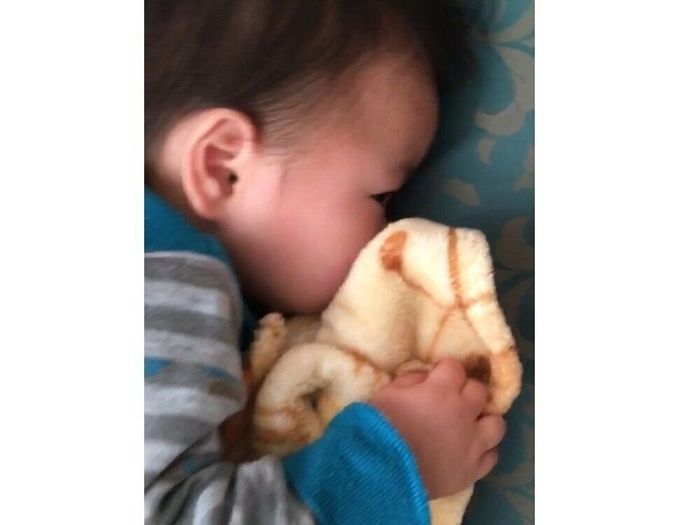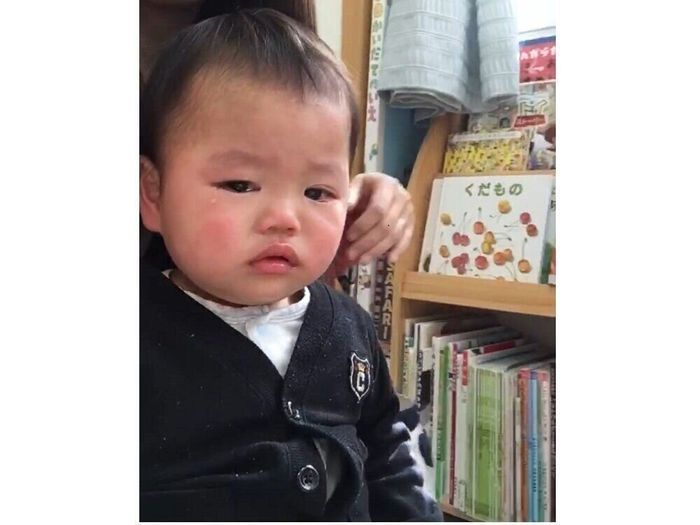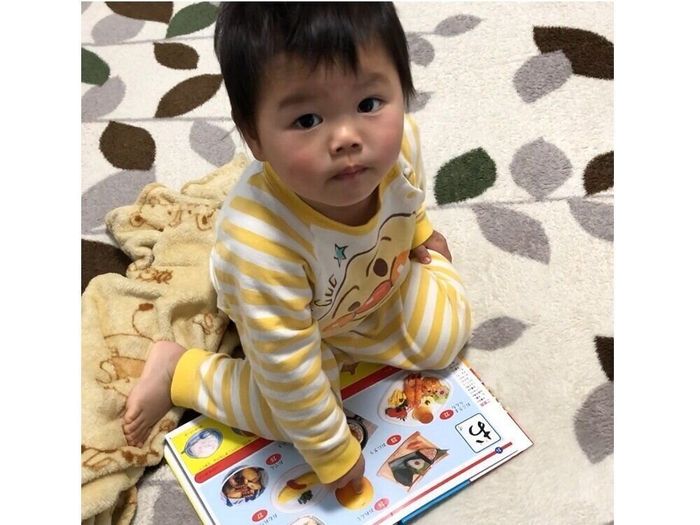あまり笑わない、言葉の発達がゆっくり。それは「男の子だから?」「個性?」と思っていた。【自閉スペクトラム症体験談】
4月2日は、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。自閉スペクトラム症は、発達障害のひとつで、弘前大学大学院の研究グループは、5歳の自閉スペクトラム症の国内有病率が3%以上と推定されると報告しています。また注意欠如多動症(ADHD)や知的発達症(ID)などと併存するケースも多く、併存率は88.5%と発表(※)しています。
2025年4月から小学4年生になるもっくんが自閉スペクトラム症と軽度知的障害と診断されたのは4歳のときです。母親のもっくんママは、YouTube「もっくん&かりんとう」で、もっくんと妹のかりんちゃんの日常を配信しています。もっくんママに、もっくんが生まれたときのことや気になる様子について聞きました。2回インタビューの前編です。
さかごで切迫早産と診断されて入院。帝王切開で2814gの元気な男の子が誕生
もっくんママは、結婚して1年ぐらいでもっくんを授かりました。
「夫とは、オンラインゲームで知り合いました。一緒にゲームをしていて優しくて頼りがいがあるいい人だな~と思うようになり、おつき合いを始めました。
トントン拍子に結婚の話になり、結婚から1年で赤ちゃんを授かりました。妊娠がわかったときは、すごくうれしかったです」(もっくんママ)
もっくんは妊娠10カ月に入ってすぐに産まれました。
「ずっとさかごのままで、妊娠29週に切迫早産(せっぱくそうざん)と言われて入院したんです。おなかの張りが強かったのですが、張り止めの点滴が効かずに、大学病院に救急搬送されて、MFICU(母体胎児集中治療室)に入院することに。ベッドに寝てずっと安静の状態でした。しかし、陣痛が来て、さかごだったので帝王切開で産むことになりました。
生まれたばかりのもっくんを見たときは『元気に生まれて来てくれてありがとう!』と心から思いました。出生体重は2814g、身長は48cmでした」(もっくんママ)
生後2カ月から母乳が上手に飲めずに、離乳食に興味を示さない
もっくんママは、生後2カ月ごろからもっくんの子育てが「なんか大変だな・・・」と感じ始めます。でも最初は、「育児は、みんな大変なもの」と思っていたそうです。
「最初に困ったのは授乳です。母乳で育てていたのですが、生後2カ月ごろから急に上手に飲めなくなりました。そのため搾乳をした母乳を哺乳びんで飲ませたり、開業している助産師さんから授乳指導を受けたりしましたが、なかなかうまくいかなくて・・・。そのころ1回の授乳時間に、1時間ぐらいかかっていました」(もっくんママ)
次に困ったのは離乳食です。
「離乳食を始めたころは、とにかく食に興味を示さず食べてくれないんです。とくにおかゆを嫌がりました。
しかし生後9カ月ぐらいになり、ふと『白米なら食べるかな?』と思って、少し食べさせてみたところ、まるで急に食のスイッチが入ったように、離乳食の準備中にも『早く~』と言わんばかりに、私のそばから離れないし、お皿が空っぽになると『もっと~!』とかんしゃくを起こすようになりました。1歳前は、3回の離乳食のほか午前と午後に補食を1回ずつ食べさせていたのですが、いくら食べても満足しないんです。
また、ケラケラと笑わないのも気になってはいましたが、クールな子なんだろうな~と思っていました」(もっくんママ)
言葉の発達がゆっくりで、1歳代では「わんわん」、「ピーポーピーポー」だけ
ほかに気になったのは、言葉の発達です。
「1歳では『わんわん』。1歳の終わりごろに『ピーポーピーポー』という言葉が出たぐらいです。
1歳6カ月健診では、言葉の発達と指さしをしないことを指摘はされたのですが、『様子をみましょう』と経過観察となりました。
ママ友たちに相談しても『男の子は言葉が遅い傾向がある』と言われたりしたので、私もあまり深刻には考えていませんでした。
でも近所に住んでいた、保育士をしているママ友に相談したところ『もしかしたら言葉の発達が遅れているのかもね。専門の人に相談して、言葉の発達を促してあげたほうがいいかもよ』と言われてたんです。そこで保健センターに相談したところ、療育に通い始めることになりました」(もっくんママ)
1歳9カ月から療育へ。初日は、大泣きして部屋に入らない
もっくんが療育に通い始めたのは1歳9カ月のころからです。そのころになると、もっくんママはさらに育てにくさを感じるようになっていました。
「療育に初めて行ったときも、大泣きして、みんながいる部屋に入ろうとしないんです。
そうしたら担当の先生が、『みんな、ここで遊んでいるよ』と優しく話しかけてくれて、その部屋の写真を見せてくれたんです。たまたま、もっくんが好きな車の乗り物が映っていて、その写真を見て『あれ?』と思ったようで、やっと落ち着いてくれました。
以前、児童館でも同じようなことがあり、スタッフの方が一生懸命もっくんをあやしてくれたのですが、まったく泣きやまなくて・・・。当時は言葉の発達を促すために、なるべく外に行って遊ばせたいと思っていたので『ここにはもう来られないかも・・・。どこで遊んだらいいんだろう?』と思って、悲しくなりました。
また、私がもっくんのことをママ友たちに相談してもなかなか理解が得られずに、疎遠になってしまった人もいます。ママ友たちに『うちの子も、かんしゃく起こすときあるよ! 大丈夫だよ』と言われても、私が『でも、なんか違うんだよ~』と否定するので、話がかみ合わないと思われたのかもしれません。
親子で孤立していくような寂しさを感じた時期もあります」(もっくんママ)
熱性けいれんを起こしたことで脳波の検査を。脳波には「異常なし」と言われて
もっくんママが自閉スペクトラム症を疑ったのは、もっくんが3歳になったころです。
「くるくる回るものが好きで、室外機や車のおもちゃのタイヤが回る様子をずっと見たりするんです。
言葉の発達もゆっくりなままで3歳のときは『パン食べる』『ジュースちょうだい』など、2語文で自分がしたいことだけを伝えてくる感じでした。
もっくんは、1歳から3歳までに熱性けれんを3回起こしています。かかりつけの小児科で『一度、大きな病院で検査したほうがいい』と言われて、大学病院を紹介してもらいました。検査のとき、医師に『自閉スペクトラム症を心配している』と伝えたところ、『いくつかの検査の中に脳波の検査もあります。脳波の状況で自閉症かどうかわかりますよ』と言われました。『脳波の検査の結果、異常は見られない』とのことでした。
『そのときはもっくんの様子は発達障害ではなく、個性なんだ・・・』と思いました。でも、育てにくさは変わらずで、心配、不安は続いていました」(もっくんママ)
【精神科医さわ先生より】子どもの発達が気になるときは専門医に相談を
もっくんの体験談にある、「脳波の状況で、自閉症かどうかわかりますよ」というのは誤解です。脳波の検査で自閉症についてはわかりません。そもそも神経発達症(発達障害)の診断が、何かひとつの検査の結果だけで確定診断がつくというものではありません。しかしながら、インターネット上にはたくさんの間違った情報があふれており、育児に困って一生懸命情報を調べる親御さんたちが間違った情報に左右されて困ってしまうということも多々あるだろうと思います。あくまでも、クリニックや病院など専門家のもとで診断は受けてほしいと思います。
また自閉スペクトラム症は、何歳になれば診断ができるというものでもありません。早い子どもであれば、1歳や2歳ごろに診断がつくこともありますが、3歳や小学校にあがってから、遅い方だと大人になってから気づかれるというケースも少なくありません。
発達が心配になったり、社会生活や家での生活に支障をきたしている場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。
また、すべての自閉スペクトラム症のお子さんが授乳が苦手ということはありませんが、中には食欲にむらがあったり、空腹や満腹などの感覚に鈍感という特性からうまく授乳や離乳食が進まないという特徴がみられることもあります。
お話・写真提供/もっくんママ 監修/精神科医さわ先生 取材・文/麻生珠恵、たまひよONLINE編集部
自閉スペクトラム症は、脳の働き方によって起こるもので、しつけなどが原因ではありません。主な症状は、目と目が合わない、笑いかけても笑い返さない、まねが少ない、言葉の発達が遅い、こだわりが強い、感覚の過敏さ、集団行動が苦手なことなどがあります。しかし、すべての方がこれらの症状があてはまるわけでもありません。また、これらの症状がなくても自閉症と診断されることもあります。
インタビュー後編は、もっくんが自閉スペクトラム症と診断されたことや下の子が生まれたときのこと、就学について紹介します。
「たまひよ 家族を考える」では、すべての赤ちゃんや家族にとって、よりよい社会・環境となることを目指してさまざまな課題を取材し、発信していきます。
※国立大学法人弘前大学「5歳における自閉スペクトラム症の有病率は推定3%以上であることを解明 」(2020年5月26日)より
精神科医さわ先生
PROFILE
児童精神科医。精神科専門医、精神保健指定医、公認心理師。1984年三重県生まれ。藤田医科大学医学部を卒業後、勤務医を経て2021年に名古屋で塩釜口こころクリニックを開院。開業直後から予約が殺到し、現在も毎月約400人の親子の診察を行っている。これまで延べ3万人以上の診察に携わってきた。2人の娘を育てるシングルマザー。長女が不登校となり、発達障害と診断される。
●記事の内容は2025年3月の情報であり、現在と異なる場合があります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い