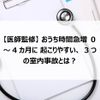【医師監修】赤ちゃんが頭を打った! たんこぶができた! 応急処置と注意すべきポイントとは?
ちょっと目を離したすきに、赤ちゃんはソファなどから落ちたり転んだりして、頭を打つことがあります。打ったところが腫(は)れてたんこぶになることも。
すぐにどういう処置をすればいいのか、病院へ連れていったほうがいいのかそのまま様子を見ていいのか、悩みますよね。
正しいケアと注意すべきポイントを小児科医の片岡正先生に教えていただきました。
赤ちゃんの体は転んだり落ちたりしやすい!
体のわりに頭が大きい乳幼児はバランスが悪く、体もしっかりしていないために、よく転んだり転落したりします。転んだときにすぐ手を出すことができないので、頭を打ってしまうことが少なくありません。
寝返りしてベッドやソファから転落する、不安定なおすわりで頭を床やテーブルの角にぶつける、つかまり立ちして支えから手が離れて転倒するといった事故は多くあります。歩き始めてからは床や道路で転んだり公園の遊具から落ちるなど、高いところからの転落が増えます。ベビーカーやショッピングカート、階段からの転落も、月齢を問わず多くなっていますので、気をつけるようにしたいですね。
頭を打ったときに心配なけが
転落・転倒して頭を打つと、軽いすり傷などで済むこともありますが、打撲、内出血、骨折などのけがをすることがあり注意が必要です。
打撲
頭を打ったとき、皮膚に傷がなくても腫(は)れてたんこぶができたり、皮膚の色が変わることがあります。適切な処置をすればさほど心配はいりませんが、頭部の打撲は、意識がない、けいれんを起こすなど、救急車を呼ばなければならないほど重症なこともあります。
皮下出血(たんこぶ)
強く打ったときに皮膚の下の血管が破れて出血し、血がたまることがあります。たんこぶは単にぶつけたところが腫(は)れただけの場合もありますが、皮下出血が起こり、破れ流れ出た血液や体内のリンパ液が頭蓋骨(ずがいこつ)の外側にたまって腫れている場合もあります。頭部は血液の量が多いので、その分大きく腫れてしまいます。
手足の軽い皮下出血や頭蓋骨の外側の軽い皮下出血は心配ありませんが、頭蓋内出血を起こすと危険です。
骨折
転んだり、何かにぶつかったり、高いところから落ちたりしたときに、打ちどころが悪いと骨折してしまうこと があります。骨折から頭蓋内出血を起こすとたいへん危険です。
頭を打ったときの応急処置&してはいけないこと
赤ちゃんが頭を打ったときにするべきことと、逆にすると危険なことがあります。両方を知っておきましょう。
正しい応急処置
■打った部位を冷やします
たんこぶや腫れはすぐに冷やし、安静にします。ビニール袋に氷を入れて氷のうを作り、患部にタオルをあてて、その上に氷のうを置いて冷やしましょう。保冷剤にタオルを巻いて冷やす方法もあります。または、ハンカチやガーゼを冷水に浸して絞り、患部にあてて冷やします。
いずれも冷やす目安は20〜30分です。それで腫れが引かなければ、それ以上冷やしても効果はありません。冷やしすぎに注意しましょう。
たんこぶはその後、その部分の皮膚が青くなる場合がありますが心配はいりません。完全に治るまでにはだいたい1ヶ月くらいかかります。
■切れて血が出ているとき
清潔なタオルやガーゼなどで出血している部分を上からしっかり圧迫し、受診しましょう。
傷が小さく出血も止まった場合は、診察時間内に受診すれば大丈夫。ただし、傷口が大きい、出血が止まらないなどのときはすぐに受診してください。
■意識がないとき
意識を失うと、舌のつけ根が落ち込んで空気の通り道(気道)をふさいでしまいます。軽くおでこを押さえて頭を後方に傾け、指で下あごを軽く押し上げるようにして気道確保を行い、救急車を呼びます。
■吐く場合は
あお向けの姿勢では吐いたものがのどに詰まりやすいため、誤嚥(ごえん)して窒息することがあります。吐いたものが口から出やすいように、そっと頭を横向きにして寝かせます。嘔吐(おうと)が続くときは救急車を呼びます。
■手足を骨折しているようなら固定します
手足を動かすと痛がる場合は骨折が疑われます。患部を挟み、上下 2つの関節にわたるように添え木をあてて、バンダナや包帯などで縛って固定します。添え木の代用として、板、段ボール、丸めた新聞紙などが使えます。指の添え木には割箸が使えます。
頭を打ったときにやってはいけないこと
■「泣けば大丈夫」と思うのは危険
頭を打ったときに「泣けば大丈夫」というのは間違いです。小さい管が破れていると、あとで症状が出てくることがあります。数日間は注意して様子を見ましょう。
■たんこぶや腫れのある部位を温めるのもNG!
温めると血流がよくなり、かえって腫れがひどくなります。腫れている部位をおふろで温めないように注意しましょう。
病院に行くべき症状と受診のタイミング
頭を打ったりたんこぶができたとき、以下の症状がある場合は受診が必要です。頭を打って泣いても、その後に機嫌がよくなり、いつもどおり遊んでいるなら自宅で様子を見ていいでしょう。
ただし、見た目ではわからなくても、頭蓋内出血を起こしたり、骨折していることもあるので注意が必要です。顔色や痛み、腫れの様子などに気をつけましょう。
下記の症状は数時間で現れる場合が多いですが、まれに数日たってから出てくることがあります。症状が現れたときはすぐに受診しましょう。
救急車は必要ないけれど、できるだけ速やかに病院へ行くべき場合
・顔色が青ざめ、腫れがひどくなる
・頭部切って出血した、血が止まらない、傷口が大きい
・胸を打ったあと、咳込んだり息が苦しそう
・血痰(けったん)・血尿(けつにょう)が出る
・痛みが激しくて呼吸がしっかりできない
・嘔吐(おうと)が2回以上あった
・打ったあと、ずっと泣きやまない、機嫌が悪い
すぐに救急車を呼ぶべき場合
・意識がない
・けいれんや嘔吐が続く
・目の焦点が定まらず、ボーッとして反応が鈍い
・目のまわりや耳の後ろに赤紫色の出血斑(しゅっけつはん)がある
・鼻や耳から透明の液体が出ている
・手足が変な角度に曲がっている
今すぐできる転倒・転落の予防&対策
おすわりやはいはい、つかまり立ちを始めたら、床は整理整頓してつまずいたりすべるようなものを置かないようにし、家具の角を事故防止のグッズでガードするなどして事故を未然に防ぎましょう。おふろ場ではすべり止めのマットを使用する、階段には柵をする、ソファやいすに上がらせないようにする、公園の遊具は大人がそばについて遊ばせる、ベランダには踏み台になるものを置かないなどの予防が大切です。
以下は、赤ちゃんの転落・転倒がとくに多いケースです。チェックして注意するようにしたいですね。
■家具から転落
いすやテーブル、ソファなどの家具に上がって遊んでいるうちに誤って転落することが。赤ちゃんをソファに寝かせていて、寝返りして落ちることもよくあります。
■浴室ですべったり、体がぬれたまま走って転ぶ
泡がついてすべりやすい浴室は、勢いよく転んで頭を打ちやすい場所です。おふろ上がりに体をよくふかずに走って、廊下などですべることもあります。
■クーファンから転落
新生児期に使うことが多いクーファンも、一歩間違えるとたちまち事故につながります。もし使うならば、1人で確実に2つの持ち手を握ってから持ち上げるようにしてください。
■遊具にぶつかる、遊具から落ちる
公園のブランコやすべり台から落ちたり、砂場のへりなどから落ちて転んだりします。大きな子どもとぶつかって転倒することもよくあります。公園内だからといって目を離さないようにしましょう。
■ベビーカーからすり抜けて落ちる
散歩中にベビーカーのベルトをすり抜けて立ち上がり、地面に転落する事故が多くあります。また安全ベルトをしなかったために、赤ちゃんが前にすべり落ちることもあります。スーパーに備えつけてあるカートから落ちる事故も多発しています。
【まとめ】これだけはやっておきたい予防&対策ポイント
・家具の角を事故防止のグッズでガード
・家の階段には上下にフェンスをつけ、すべり止めのシールをはる
・敷居などの段差にはテープなどでスロープをつけて段差をなくす
・床に新聞紙や電気コードを放置しない
・おふろ場ではすべり止めのマットを使用
・ベランダには踏み台になるものを置かない。柵のすき間から落ちないように工夫する
・自転車に乗せるときは子ども用ヘルメットをかぶらせる。自転車に子どもを乗せたままその場を離れない
・公園の遊具は大人がそばについて遊ばせる
こんなときはどう対応すればいいの? 先輩ママの体験談をチェック
頭を打つ、たんこぶができるといっても、そのシチュエーションはさまざまです。先輩ママたちの体験談から気をつけるべき状況や対応を学びましょう。
Q まだ3ヶ月で動けないのにベッドから転落!
3ヶ月の息子が昼寝中にベッドから落ちてしまいました。泣きやんでその後は普通にしていますが、大丈夫でしょうか?
A
「まだ寝返りをしない赤ちゃんは、ベッドから落ちない」と思い込んでいるママは多いですね。けれども生まれてすぐの赤ちゃんでも、手足を元気に動かして泣いていると、体がずれ動いて転落することがあります。ソファや柵をしていないベッドに寝かせたときは、新生児でも目を離してはいけません。落ちてしまったら、泣きやんだあと、顔色や目の動き、手足の動きなどをチェックして。いつもと同じなら心配ありませんが、気になることがあればかかりつけ医にすぐ相談しましょう。
Q おでこが赤い。頭を打った影響が心配!
6ヶ月の女の子のママです。先日一瞬目を離したすきに浴槽に転落させてしまいました。その後は普段どおりにミルクも飲み、異常はとくになかったのですが、浴槽の底に頭を打ったようで、おでこが赤くなっていました。頭を打った影響が心配です。
A
頭を打つとあとで何か症状が出てくることがあるので、心配になりますよね。でも頭を打って脳に障害が起これば、たいてい数時間以内に症状が現れます。それも意識障害やけいれんといった重症の症状です。頭を打ってほぼ24時間経過してなんともなければ、心配いりません。頭を打ったということは、浴槽には水が張っていなかったということですね。それはママの適切な処置が幸いしましたね。乳幼児のおふろでの溺水(できすい)事故はとても多いです。浴槽の水は必ず抜くことはもちろん、浴室の鍵もかけておきましょう。
Q 打った部分がへこみ、次にふくらんで赤くなった!
4歳になるめいが7ヶ月になるわが子を抱っこしていて、おもちゃのピアノの上に落としてしまいました。頭をぶつけ、へこんでいましたが、だんだんとたんこぶのようにふくらんで赤くなっています。わが子はグズッて寝ています。大丈夫でしょうか?
A
おもちゃのピアノの上に落ちて、頭がふくらんで赤くなっているとのことですが、これは皮下血腫、いわゆるたんこぶです。ぶつけたあとすぐに泣いて、その後機嫌がよければ病院へ行かなくて大丈夫。ぐずって泣いたあとに寝てしまった場合も心配ないでしょう。1~2時間ぐずったり、ぐったりしている、意識がはっきりしないときは救急で病院へ行きましょう。
Q ブンブン頭を振るのは転倒した影響?
もうすぐ9ヶ月になる男の子です。最近やたらと頭をブンブン左右に激しく振ります。8ヶ月になってすぐつかまり立ちをし始めたのですが、頭から転んでしまい、おでこにはたんこぶがいくつもできています。転倒した衝撃で脳がおかしくなっての行動でしょうか。あまりに頻繁に振るので心配です。
A
赤ちゃんはよく頭を振りますよ。異常な行動ではなく、むしろよく見られる行動です。頭を打っておかしくなったのではありませんから大丈夫。心配ならクッション性のあるマットなどを敷いておくといいかもしれません。転倒した衝撃で脳がおかしくなってしまったら、意識障害を起こすかけいれんするかのどちらかです。その場合は即、救急車を呼びましょう。
Q 階段から転落。後遺症が出ないか毎日不安です
10ヶ月の娘が先日、2階の階段の最上階から下まで転落してしまいました。落ちる音と泣き声で気がつき、救急受診、頭部CT撮影をしました。幸い頭蓋内出血や骨折、そのほか外傷などなく、問題なく帰宅しました。しかし、乳児は症状が出にくいとのこと。1週間たちましたが心配でたまりません。たんこぶのせいか、頭の形も気になります。後遺症がでないか毎日心配です。
A
階段からの転落、ものすごくよくある話です。後遺症を心配するよりも、二度と事故が起こらないように安全対策を徹底してください。階段からの転落を含めて、家庭内での事故で脳に障害を負うことはめったにありません。とはいえ、鎖骨などの骨折はよくありますし、けがをする可能性はあります。「たんこぶ」というのは皮膚の腫(は)れであり、骨の変形ではありません。いずれ頭の形はもとに戻るでしょう。もし脳によからぬことが起これば、意識障害かけいれんを起こしますので、症状が出にくいことはありません。まず心配しなくて大丈夫です。
Q&Aは全て「たまひよプレミアム」より転載
おすわりや立っちができて視線が高くなったり、はいはいや伝い歩きで移動できるようになると、赤ちゃんの興味はどんどん広がります。それだけに危険な目にあったり、いたずらから事故に発展することが増えます。まずは赤ちゃんの周囲の環境を、しっかり点検するようにしたいですね。
(取材・文/かきの木のりみ)
初回公開日 2019/03/18
育児中におススメの本
最新! 初めての育児新百科 (ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ)
大人気「新百科シリーズ」の「育児新百科」がリニューアル!
新生児から3歳まで、月齢別に毎日の赤ちゃんの成長の様子とママ&パパができることを徹底紹介。
毎日のお世話を基本からていねいに解説。
新生児期からのお世話も写真でよくわかる! 月齢別に、体・心の成長とかかわりかたを掲載。
ワンオペおふろの手順など、ママ・パパの「困った!」を具体的なテクで解決。
予防接種や乳幼児健診、事故・けがの予防と対策、病気の受診の目安などもわかりやすく紹介しています。
切り取って使える、「赤ちゃんの月齢別 発育・発達見通し表」つき。



 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い