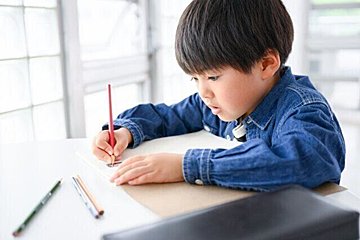SNSのアイコンを子どもの写真にしている派、しない派、どうしてそうなったのかそれぞれの理由
口コミサイト「ウィメンズパーク」に、「子どもがいる女性は、SNS のアイコンに自分の子どもの写真を載せている人が多い。なぜですか?」という、質問がありました。質問者はかなり前からSNSを利用しており、当時は「アイコン=自分の写真」が当たり前だったので、変化した理由を単純に知りたいと思ったそうです。ママたちからは、さまざまな声があがりました。
子どもを通してママの顔が見えるから
「そりゃあ可愛いから」
単純明快。ダントツで支持された声です。
「親バカだからでしょう。世界で一番可愛い我が子を自慢したい気持ちが、どこかにあるのでは」
「変なたとえですが、一番大切でお気に入りのアクセサリーを身につけている感覚なのかな」
「体じゅうに“ママ成分”が染み渡っているからね」
「子育て真っ最中の女性には、我が子がまさしく自分の“アイコン(象徴)”なのでしょう」
名言も出てきましたが、利便性があるという声もありました。
「最近のLINEはニックネームが多い。親しい人ならすぐわかるけど、習い事のグループLINEでは“この人誰だ”と、なります。でもアイコンの写真で“A君のママ”とわかって便利です」
「幼稚園・保育園では、誰が誰のママかさっぱりわかりません。役員とかクラスの連絡網では結構困りました。けれどLINEは、アイコンが子どもの写真なので助かりました」
「名前を覚えるのが苦手ですが、アイコンの子どもの写真で“あーあのママ”と、思い出せます」
「成長記録を兼ねているのでは。すっかりご無沙汰のママ友でも、アイコンの子どもの写真で“こんなに背が伸びたのかー”などがわかって、ほっこりします」
「できるなら自分の写真を載せたいです。でも何回撮ってもありのままの老け顔になる。なので、フレッシュな我が子になりました」
番外編でこんな声もありました。
「こういう子どもがいますって、わかりやすい。お子さんは女の子なんだなとか、4人兄弟なんだなとか、習い事はサッカーしてるんだなとか。アイコンに使うくらいだから話をふっても大丈夫だろうし、トークが盛り上がるきっかけになります」
ところが子どもの写真をアイコンに使うのは期限があるようです。
「年賀状の家族写真と同じ。アラフィフの私の周りでは、お子さんの顔写真を使っている人はいません」
「子どもが成長すると、ペットのアイコンばかりになりました」
そして「使いたい気持ちはわかるけど、子どもの写真は使いません」という声も多くありました。
SNSによってアイコンは使い分けている、という声
「子どもの写真はアイコンに使いません、後ろ姿でも数年前の赤ちゃんの写真でも。私を全く知らない人に“子どもがいる”という情報を与えたくないからです」
「ママ友以外の人に、子どもを見られることに抵抗があります」
ところが載せない派だったけど、やはり便利ということで、使い分けている人がいました。
「使用目的でアイコンを変えています。LINEは8割が子どもつながりなので、子どもの写真です。Facebookなどは趣味つながりが多いので、風景写真などにしています」
「使わない派でしたが、子どもつながりのグループLINEがどんどん増えて、LINEだけは子どもの写真です。後ろ姿だけど」
またこんな意見も。
「好きなアーティストの写真をアイコンに使う人も多いけど、そういう人に限って名前のみのローマ字だったり、ニックネームを使ったり。最初に名前を再登録すればいいのですが、うっかり忘れると誰だがわかりません。もう少し本名を匂わせて欲しいなぁと思います」
次はアイコンにまつわる面白エピソードの紹介です。
どうしてこの写真? SNSの謎のアイコン
「委員会の関係で、あまり親しくない同級生のママと電話番号を交換して登録しました。LINEが出てきてしまったのですが、アイコンがご本人の花魁姿でした。夜のお仕事のお姿のようです」
「花魁姿! ありました。それも二人も。お二人ともかなり年上の知り合いなのですが、びっくりしました」
「ママ友が自分のキメ顔をアイコンに使っています。まるで別人です。笑いをとりにいっている? と、思いましたがそういうタイプじゃないし、未だにツッコメません」
「友人のアイコンがブタのぬいぐるみです。ふと理由を聞いたら、アイコンを自分の写真にしたかったが、顔は嫌なので、遠くから撮った写真にしようとしたら体型が‥‥‥。結局、自分に似たぬいぐるみを選んだと言っていました。納得した表情をしたらムッとされました。“そんなことないよー”と、フォローするところだったようです」
筆者のLINEのアイコンはペットの猫。そして下の名前だけのローマ字表記。“誰だかわからん!”という声に反省して、訂正しました。
文/和兎 尊美
■文中のコメントは口コミサイト「ウィメンズパーク」の投稿を抜粋したものです。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い