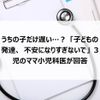赤ちゃんが安心しやすい、声かけ時の3つのコツ 【3児のママ小児科医】
3児を子育て中のママ小児科医・藤井明子先生が、子育てを通して感じた「赤ちゃんとのおしゃべり」をテーマに、先生の体験談をお届けします。
藤井先生が、診療の中でママ・パパたちから寄せられたお悩みについてのアドバイスや、日々の子育てに頑張っているママ・パパに伝えたいさまざまな情報を発信している連載の第7回目です。
赤ちゃんと2人きりのとき、声かけしていますか?
日ごろ赤ちゃんと一緒にいるママ・パパは、どんな言葉を赤ちゃんにかけていますか? どんな表情で、どんな言葉を、どのようなスピードで、どのようなトーンで話しているでしょうか。
赤ちゃんと2人きりで自宅にこもっていると、何と声をかけたらいいのかわからないときがあるかもしれませんね。
私も初めての育児のときは、しーんと静まりかえった部屋で長女と2人きり…という時間に、とまどった覚えがあります。朝に家族を見送って以降、だれとも話していないことに気づくこともありました。
「話す」ことは、コミュニケーションの一環ですが、コミュニケーションには、音声としての言葉を交わすだけでなくて、目と目を合わせてほほ笑み合うこと、指さしをすること、声の強弱、緩急をつけることなどの非言語性のコミュニケーションも含まれています。
赤ちゃんが安心しやすい、声かけ時の3つのコツ
診察に来たママ・パパに「赤ちゃんにどんな声かけをしたらいいのでしょうか」と聞かれることがしばしばあります。
私が長女と2人きりの時間のときを振り返ると、
1授乳をするとき
2おむつを替えるとき
3沐浴するとき
4着替えるとき
5朝起きたとき
6眠るとき
7お散歩しているとき
という場面で声かけをしていました。
娘がこちらを見ているときもあれば、声かけすることで娘がこちらを見てくれるときもありました。
健診やワクチン接種のときにも、赤ちゃんの目を見て、ほほ笑みながら声かけすると、赤ちゃんがにこにこと笑ってくれたり、不思議そうにこちらを見たり、泣きべそをかきそうになってこらえきれずに泣いたりと、さまざまな反応が見られます。
赤ちゃんに声かけするときには、【やや声を高め】、【ゆっくり】、【抑揚をたっぷりつける】ことをおすすめします。その声かけに安心して、赤ちゃんも応じるでしょう。「おっぱい飲もうね」「お着がえするよ」「おふろ気持ちいいね」などなど、今行っていることを伝えてみましょう。
また、赤ちゃんの「ぶー」「あー」などさまざまな喃語(なんご)に反応して、親が目を合わせて「ぶー」「あー」と笑顔で声かけをしてみてもいいでしょう。それも赤ちゃんが“何か音を出せば、まわりが応じてくれる”というすてきなコミュニケーションの始まりですね。
少し月齢が進んで、物を持ったり、動かしたりすることができるようになってきたら、おもちゃなどを使って遊びながら声かけするのもいいですね。
音がなるおもちゃを振って、一緒に声を出して遊びながら、短い言葉で声かけするのもいいでしょう。見たまま、感じたままを赤ちゃんに伝えるのもいいです。
また、いないいないばあ遊びや、くすぐり遊びもコミュニケーションを促す遊びです。赤ちゃんは好みの遊びを繰り返すことが好きです。好きな遊びを繰り返しながら、赤ちゃんとのやりとりを楽しんでみてはいかがでしょうか。
文・監修/藤井明子先生 構成/ひよこクラブ編集部


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い