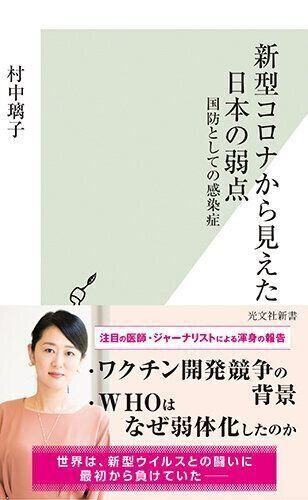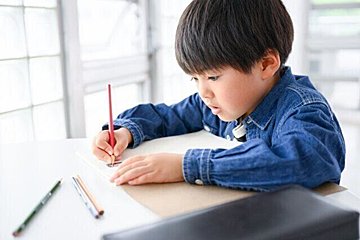省エネが肝心!新型コロナ時代、保育園・小学校の教室の窓の開け方【村中璃子医師特別寄稿】
寒暖差が激しい季節、子どもたちの保育園、学校での換気について知りたいと思うママ・パパのために、ドイツ在住で、WHO(世界保健機関)でパンデミック対策に携わった経験を持つ村中璃子医師に、2021年2月27日時点の考えを寄稿してもらいました。
まだまだ寒い時期の換気、どうすれば?
新型コロナのおかげで、世界中どこでも、寒い日でも学校や保育所の教室の換気をしなければならなくなりました。
わたしの暮らしているドイツでもクリスマス直前に完全なロックダウンに入る前、まだ学校が開いていた頃には、窓の開いた教室で子どもたちがコートを着たまま授業を受けている光景をよく見かけました。
ところが先日、テレビを見ていたら、子どもたちに「授業中に窓をあけることについてどう思うか?」と訊ねると意外な答えが返ってきているのを見たのです。
「寒い」と答える子もいましたが、圧倒的に多くの子どもが「授業に集中できるようになった」と答えました。「成績がよくなった」「テストでいい点が取れた」と答えた子どもも何人かいました。
実際に、窓を1時間締め切った教室と換気した教室の2つで、ほぼ同じ内容の20秒ほどの簡単なテストをしてみると、換気した教室でのテストの方が子どもたちの成績が圧倒的に良いという結果が出たのです。
理由はいたってシンプル。
窓を閉めていると教室の二酸化炭素濃度が上がりすぎるからです。
本当にそうなのでしょうか。
今度は、特殊な実験施設で、窓を閉め切った平均的な大きさの教室で生徒24人がいる環境をシュミレーションしてみると、二酸化炭素濃度は2時間で2000ppmを超えました。2000ppmとは、人が頭痛などを訴え始める二酸化炭素の濃度です。
新型コロナウイルスがいようがいまいが、やはり換気は大切なんですね。
換気も暖かい日であれば、寒がる子もいないし、かえって風邪を引いてしまう心配もないでしょう。
でも、寒い日はどうしたらいいのでしょう。
ヨーロッパの窓の多くは、取っ手を横にひねると全開し、縦にひねると上の部分だけが少し開くようにできています。
そのため、窓の上を少しだけ開けっ放しにして授業をしている学校もあります。
ところが、教室全体の空気の出入りを詳しく調べてみると、縦開けの窓の上を少しだけ開けっぱなしにする方式では空気の出入りはほとんどなく、1時間開けたままにしても教室の空気はぜんぶ入れ換わりませんでした。
一方、横開けの全開方式では、教室の空気は2、3分ですべて入れ替わりました。
新型コロナが流行するなか、日本でも「窓を数センチだけ開けておく」といった工夫をしている学校や職場も多いでしょう。
しかし、もうお分かりですね。
寒い思いをしながらちょっとだけ窓を開けたままにしておくよりも、短い時間でも定期的に全開してやる方が換気効率はいいのです。
幸い、保育所や学校が感染拡大の主要な原因だといったデータはありません。
ただ、各国の最新のデータに基づけば、子ども症状が出にくいだけでも大人と同じくらい感染しやすく、恐らくは、他の人を感染させる力も大人と同じくらいあると考えられています。市中感染が広がれば、学校や保育所でもそれにつれ感染が広がることは、各国のデータからはっきりしています。(※編集部注「新型コロナ、再びの一斉休園・休校をふせぐためにできること 村中璃子医師特別寄稿」参照)
「子どもたちをウイルスから守らなければ」という強い気持ちや責任感から、マスクに手洗い、消毒に換気……と、保育士や教職員もつい全部をがんばりがちですが、誤った方法でがんばっても、大変なだけで十分な効果は得られません。
春はもうすぐとは言え、寒い日はまだ続きます。
パンデミックもまだ続きます。
家事や子育てと同じで、コロナ対策を息切れせず続けるには「省エネ」が肝心です!限られた時間や注意力を効率よく使うことで、子どもたちの園や学校での生活を、よりしっかりと守っていくためです。
教室の大きさに対する子どもや保育士・教職員の数にもよりますが、保育所や学校では、「1時間に2、3回、窓全開で2、3分の換気」を心がけましょう。
村中璃子先生
PROFILE
医師・ジャーナリスト。一橋大学社会学部出身、北海道大学医学部卒。京都大学医学研究科非常勤講師。WHOの新興・再興感染症チームの勤務を経て、現在は医業の傍ら、執筆や講演活動を行っている。2017年、科学誌『ネイチャー』等主催のジョン・マドックス賞を、日本人として初めて受賞。海外メディアにもたびたび取り上げられ、世界からも注目を集める。著書に、『10万個の子宮 あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応なのか』 (2018年、平凡社刊)。近著に『新型コロナから見えた日本の弱点~国防としての感染症~ 』(2020年、光文社新書)



 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い