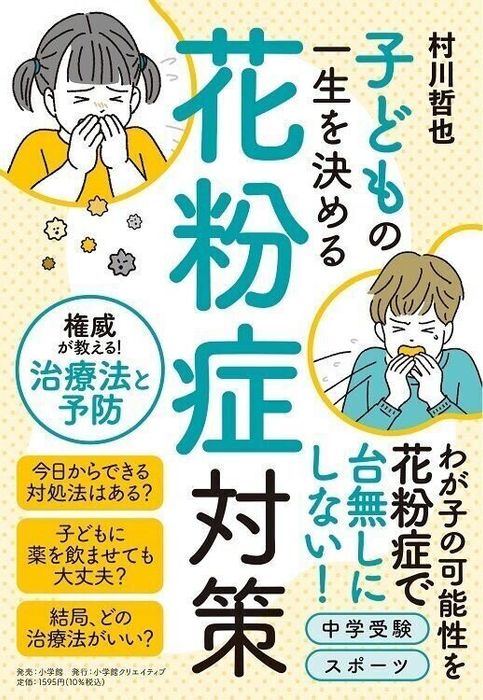花粉症も根治が期待できる時代!子どもを花粉症の悩みから救う、注目の治療法とは!?
花粉が気になる季節。最近、大人はもちろん、子どもの花粉症も増えているといいます。子どもは大人のように症状を訴えづらいもの。そのため花粉症にかかっている子どもの多くは治療を受けずにそのまま放置されがちだそう。実は花粉症は、治せる病気となっており、初期のうちに治療をスタートすることで、効果も早くのぞめるとのこと。子どもの将来のQOLも左右する、花粉症治療の最前線について、耳鼻咽喉科医の村川哲也先生に聞きました。
小さいうちからでも花粉症になるの?発症しやすい条件ってある?
「子どもの花粉症は年々増えていて、2〜3歳から発症することも珍しくありません」と村川先生。なぜ子どもの花粉症は増えているのでしょうか。
――子どもの花粉症が増えているとのことですが、その理由について教えてください。
村川先生(以下敬称略) お母さんお父さんが花粉症の場合など、遺伝的な素因はありますが、大きな理由の1つとしては、そもそも飛散する花粉の量が増えていることが挙げられます。スギやヒノキの飛散距離は約100kmともいわれているので、大人も含め、どこにいてもスギやヒノキの花粉を浴びていることになります。
さらに、道路が整備されたコンクリートの道が増えたことにより、1度地面に落ちた花粉が舞い上がり、それを吸うことで花粉症を引き起こすケースがあります。むしろ自然豊かな場所よりも、都会などのアスファルトが多い場所のほうが花粉症を発生しやすい傾向があるのです。山から飛んできた花粉に、排気ガスなどの汚染物質がくっつき、それを吸うことで花粉症を発症しやすくなります。
つまり、年齢が低い子どもでも、どこにいても花粉症を発症してしまう可能性があり、早い子では2〜3歳から発症することもあるのです。
――子どものうちに花粉症を発症すると、どんな問題点がありますか。
村川 子どもの場合に注意が必要なのは、花粉症であることが見過ごされてしまうことです。花粉症の時期は季節の変わり目で、風邪の流行時期と重なります。また、小さいうちは症状を上手に訴えることができません。たとえば「かゆい」と言えずに「痛い」と言ったりすることもあります。
家庭で風邪か花粉症かを見分けることは難しいのですが、ポイントとしては、鼻水が粘っこい場合や発熱がある場合は、風邪の可能性が高いでしょう。鼻水がサラサラの場合は、花粉症などのアレルギーの場合もあれば、風邪の場合もあります。
喉が痛い場合は、風邪のほか、花粉症で鼻が詰まって口呼吸をすることで痛くなることも。
ただ目をこすっている場合は、花粉症などのアレルギーの可能性が高いです。いずれにしても、春や秋に熱がないのに鼻が詰まっていたり、ひんぱんに目をこすっていたりしたら、耳鼻咽喉科を受診しましょう。
――腸内環境の悪化が花粉症に関連するというのは本当なのでしょうか。
村川 花粉症は免疫細胞が過剰に反応し、花粉を異物と判断することでアレルギー反応が生じて発症します。体内の免疫細胞の70〜80%は腸内に存在するため、何らかの原因で腸内環境が悪化すると、免疫が正常に働かず、花粉症のリスクは高まると考えられています。
また、脂っこい食事や野菜不足は腸内環境を悪化させるとされています。腸内環境は食事に影響されるため、家族そろって腸内環境が整う食事にすることはとても大切です。
トマトはNG、赤飯はOK!?花粉症にいい食べ物、悪い食べ物はあるの?
最近では、花粉症にまつわるさまざまな新情報が出てきています。そのなかでも、食べ物にまつわる話は、ママやパパたちに意外と知られていないものばかり!
――花粉症によくない食べ物はありますか?
村川 花粉症の人が食べると、他のアレルギーを引き起こす恐れがある食べ物もあります。その1つがトマトです。スギやヒノキの花粉症の人がトマトを食べると、唇が腫(は)れたり、口の中がピリピリしたり、喉がイガイガしたりすることがあります。これを「口腔(こうくう)アレルギー症候群」といいます。スギやヒノキに含まれるタンパク質と、トマトに含まれるタンパク質がとてもよく似ているために起こる症状です。口腔アレルギー症候群を起こすタンパク質は加熱すると症状が出ないこともありますが、トマトは生で食べることが多いので、気になる症状があるお子さんは控えましょう。
そのほかにも、花粉症の種類別に避けたほうがいい食材があります。カモガヤなどイネ科の花粉症がある人は、メロンやスイカ、トマト、オレンジはNG。またハンノキの花粉症がある人は、リンゴ、モモ、ナシ、キウイ、メロン、スイカなどで、シラカバ科の花粉症の人はリンゴ、モモ、サクランボ、ヨモギと、ブタクサの花粉症の人はメロン、スイカ、セロリなどで口腔アレルギー症候群が起こることも。子どもにこれらの食材を食べさせるときには、「口がヒリヒリしない?」などと聞き、ヒリヒリするようならすぐ耳鼻咽喉科を受診しましょう。
――花粉症予防になる食事はありますか?
村川 お米や小麦に含まれているでんぷんに免疫力を高める働きがあることが最近の研究でわかってきました。「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」といわれるもので、小腸で消化されずに大腸まで届き、食物繊維のような働きをします。レジスタントスターチは、温かいものよりも、冷めたものに多く含まれるため、冷めた(温かくない)ごはんなどがおすすめです。
また、効率よくとりたい場合は小豆もいいでしょう。小豆をたっぷりの水でやわらかくなるまで煮たあと、24時間冷蔵庫で冷やしてから食べると手軽にレジスタントスターチがとれます。ただし、砂糖を加えると効果が落ちるため、食べさせるなら小豆を入れて赤飯を炊き、冷ましてから食べさせるといいでしょう。
――そのほかに花粉症を発症させにくくする効果が期待できる食べ物はありますか。
村川 腸内環境をよくするという意味で、ヨーグルトもいいですね。その理由は発酵食品だからです。とくにプロバイオティクスと呼ばれているものがおすすめです。ヨーグルトに含まれている菌は、メーカーや商品によっても異なるため、同じ商品を食べ続けるより、ローテーションでいろいろな商品のヨーグルトを食べさせてあげましょう。同じ菌ばかりとっていると、働きが鈍くなるという見方があるためです。もちろん、発酵食品という意味では、みそやしょうゆ、酢、ぬかづけ、納豆などもぜひ食べさせてください。野菜などの食物繊維が豊富な食材もたくさん食べましょう。
花粉症の根治をめざす「舌下免疫療法」ってなに?
医療の発達により、花粉症は根治が期待できるようになりました。その中のひとつ、舌下免疫療法(ぜっかめんえきりょうほう)とはどのようなものなのでしょうか。
――まず、花粉症を発症した子どもへの治療で処方される一般的な薬について教えてください。
村川 花粉症の治療で使われる薬でもっとも知名度が高いのが、抗ヒスタミン薬でしょう。市販薬でも「アレグラ」や「アレジオン」などの名前で販売されているため、目にすることも多いと思います。ヒスタミンの働きを抑えることでアレルギー反応が出にくくなり、花粉による鼻水、鼻づまり、くしゃみなどの症状を緩和してくれます。
抗ヒスタミン薬の中には錠剤以外にドライシロップもあり、生後6カ月以上の赤ちゃんでも服用することができるものもあります。ただ、抗ヒスタミン薬の中には適用年齢が12歳以上や15歳以上のものなどがあるため、自己判断で服用するものではありません。そのほか、抗ロイコトリエン拮抗(きっこう)薬、漢方薬、点鼻薬、点眼薬などがあり、それぞれ用途や状況、体調によって使い分けられます。いずれにしろ、服用する場合は医師や薬剤師に相談しましょう。
――舌下免疫療法とはどのような治療法ですか?
村川 自分の免疫機能が、花粉に対して過剰反応しないようにするための治療です。
溶けるタイプの錠剤を舌下に入れて1分間待ち、1分たったら唾液ごとごっくんと飲みます。そのあとは5分間、飲食、歯磨き、うがいをするのを避けます。対象年齢は幅広く、5歳以上であれば使うことが可能で、根本的に体質改善をしたいと思っている人に適した治療法です。
ただし体質改善をめざすため、長期戦になります。毎日1錠ずつ飲み、体をアレルゲンに慣らしていくので、効果を実感するのに3年くらいはかかります。
――大人と違って子どもは、挫折してしまいそうですが……。
村川 薬を楽しくないものととらえたら、お子さんは飲んでくれません。最初の1錠は副作用をみるために病院で服用しますが、病院でも楽しく飲める工夫をしています。「○○味のラムネの味がするよ(実際、味はありません)」と言ってみたり、子どもの好きな曲や動画が終わるまで舌下に入れておいてもらったり。
習慣化することが大切なので、ご家庭では朝起きたあと、トイレに行く前に服用することをおすすめしています。トイレに入る前に飲んでおけば、トイレを終えて手を洗うまでには溶けているからです。
なお、舌下免疫療法は花粉が飛散しているシーズンではなく、飛散が始まる前にスタートします。
――子どものうちに治療しておくメリットはありますか。
村川 子どものうちに治療しておくといい理由の1つに、医療費が低額で済むことがあります。大人の場合、初回の治療費は、医療費が3割負担とすると4000〜5000円ほどかかり、それ以降も治療と薬の両方で1カ月あたり2000〜3000円ほどかかります。これが小学生だと医療費の補助があるから自己負担なし、もしくは1カ月に数百円程度となります。しかも、早いうちに治療をスタートしておけば、早く治ることも期待できるのです。
――妊婦さんに舌下免疫療法はできますか。
村川 残念ながら、妊婦さんに舌下免疫療法はできません。錠剤によるスギのアレルゲンを異物ととらえてしまう可能性があるためです。ただし、妊娠前から舌下免疫療法を行っていて、その間に妊娠した場合は継続できます。
妊娠中に花粉症がつらい場合は、薬の影響が少ない点鼻薬などで治療をするのが無難でしょう。出産後、授乳中の場合は、舌下免疫療法をスタートすることができます、
なお花粉症の人が妊娠を希望している場合は、効果が1年から1年半ほど続くレーザー治療を妊活前に受けておくのがおすすめです。
――乳児期の子どもの花粉症の発症を、少しでも遅らせるためにできることはありますか。
村川 乳児期は外出が少ないため、花粉を大量に浴びることはまずありません。お母さんお父さんが花粉を家に持ち込まないように、空気清浄機を使うといいですね。窓を開けて換気をしたいときは、朝から午前10時ごろの、花粉の飛散が少ない時間帯を選びましょう。
ベビーカーでおでかけするときは、ベビーカーのほろを下ろしておくだけでも効果があります。
また、赤ちゃんの皮膚が荒れていると、皮膚の傷から花粉が入ることで、ほかのアレルギーを発症することもあります。日ごろからローションやクリームを使って肌の保湿をこころがけ、皮膚のバリアー機能を整えてあげるといいでしょう。
――最後に、たまひよ世代のママとパパにメッセージをお願いします。
村川 小さいお子さんは花粉症で目がかゆくても、それを伝えられずにひたすら目をこすっていることも多いです。子どもは自分からはなかなか訴えることができないので、花粉症の時期はくしゃみが多くないか、目をかゆがってないかなど、よく観察するようにして、気になる症状があったら早めに耳鼻咽喉科を受診するようにしましょう。
早く治療を始めれば、それだけ早くお子さんを花粉症の悩みから解放してあげることができるので、ぜひ気をつけてあげてください。
監修/村川哲也先生 取材・文/樋口由夏、たまひよONLINE編集部
花粉症は1度発症すると一生つき合わなければならないというのは、もう昔の話。いまは根治が期待できるのがうれしいですね。さまざまな情報が出回っていますが、誤った情報を信じてしまうと、悪化させてしまう可能性もあるそう。そうならないためにも正しい知識を持ち、子どもが花粉症に苦しまないようにしてあげましょう。
●記事の内容は2025年2月の情報であり、現在と異なる場合があります。
村川哲也先生(むらかわてつや)
PROFILE
医師・医学博士。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会専門医・日本気管食道科学会認定専門医・日本レーザー医学会専門医。防衛医科大学卒業後、カリフォルニア大学バークレー校ローレンスバークレー国立研究所などを経て、2007年に喜平橋耳鼻咽喉科を開業。また、2025年3月16日(日)には衆議院議員玉木雄一郎氏らをゲストに迎え講演会を行う。詳しくはこちら(著書購入の方は無料)
子どもの一生を決める花粉症対策
花粉症に苦しむ子どもをもつ親御さんに向けた必読の1冊!すぐにできる対策から子どもに負担をかけずに根治が可能な治療法まで、最適な対策を花粉症治療の名医がわかりやすく解説。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い