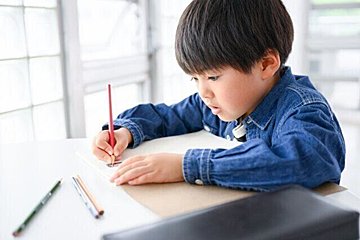「犬との暮らしがここまで子どもに影響するとは…」どこにも行けない夏でも7歳少女が笑顔でいられた理由
「ペットとの暮らしは人に癒しを与える」 一般社団法人ペットフード協会の調査によると、2020年に新たに犬を飼い始めた人は前年比114%。猫も同116%と過去5年間で最も高い伸び率を記録。同協会は「コロナ禍の影響で、ペットとの生活から癒やしを求める傾向がうかがえる」と分析しています。
7歳の女の子の支えになったのは……
「コロナ禍でなかなか自由に遊ぶことができなかったこの夏でしたが、みみ子がいると、ひとりっ子の娘も寂しくない様子です」 と、7歳の娘、ミックス犬のみみ子と暮らすエッセイストの藤田あみいさんは言います。「娘とみみ子はまさにいい相棒なんです」(藤田さん)。
犬や猫と触れ合うことで、人の脳内にはオキシトシンというホルモンが分泌されます。人間の出産時に陣痛を起こしたり、母乳の分泌を促進するときにたくさん分泌されることで知られていますが、ストレス軽減、相手に愛情を感じる気持ちを促すことから、幸せホルモンともよばれています。
長引くコロナ禍で、不安や過度なストレスが子どもたちの心の発達に与える影響が懸念されています。医師や獣医師などで形成された「人と動物の関係学研究チーム」によると、犬や猫との暮らしで分泌されるオキシトシンによって、子どもたちのストレスが緩和される可能性が大いにあり得るとのことです。
犬との暮らしで学習意欲が高まる
ペットとの暮らしが子どもに与える影響はそれだけではありません。
「犬を飼う前に比べ、娘が本を読む回数も増えたように思いますし、勉強をするときなどは『お姉ちゃん頑張るからね!』とみみ子に話しかけたり。意欲が向上したように思います」(藤田さん)
「哺乳類だけに限らず、爬虫類や昆虫についても、興味が湧いてきているようで、生態を知ることに意欲的になっているようです」と藤田さん。娘さんに聞いてみると「勉強や、習い事の練習の最中に気が散ったり、疲れたなぁと思うとき、みみ子に触ったり、匂いを嗅いだりすると、よしもう一度頑張ろうという気持ちになる」とのこと。
ペットとの暮らしが日々の学習や生活の糧になっている様子がうかがえます。
実際、小学3年生を対象にした読み聞かせの研究では、犬に読み聞かせたグループの子どもはほかのグループの子どもよりも読書速度や正確性、理解力が高まるといった結果*が出ています。
犬がいることでリラックスでき、課題への集中力が高まったと考えられます。
子どもの心の成長にも寄与するペットとの暮らし
「みみ子がお散歩に行きたがるので、運動がなかなかできない日でもお外に出てゆっくりと街を歩くことができる。みみ子が興味を持った葉っぱや、土など、みみ子の低い目線で物を見たりできて面白い」と藤田さんの娘さん。愛犬との暮らしを楽しみながら、小さな命を思いやる気持ちが育まれているのかもしれません。
赤ちゃんと暮らしているママやパパにとっては少し先の話かもしれませんが、子どもが大きくなったとき、「ペットとの暮らし」について家族で考えてみてもよいかもしれません。
取材・文/たまひよ編集部 取材協力/いぬのきもち・ねこのきもちWeb編集室
写真提供/藤田あみい
*Marieanna C., et al.(2014). The Effect of an Animal-Assisted Reading Program on the Reading Rate, Accuracy and Comprehension of Grade 3 Students. A Randomized Control Study, in Child Youth Care Forum, 43: 655-73.
『いぬのきもち』『ねこのきもち』では、未来を担う子どもたちに、絵本を通じてもっと犬・猫を好きになってもえたらという「未来のいぬ好き・ねこ好き 絵本プロジェクト」を実施中。
第一弾の絵本「いぬとねことたからもの」では読み聞かせ動画も無料公開中。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い