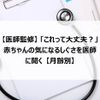赤ちゃんのフシギなしぐさにはワケがある!【専門家解説】
自分の足を一生懸命なめたり、小さいものを拾いたがったり。「どうして?」と赤ちゃんの行動が不思議に見えることはありませんか?その行動やしぐさには、実は理由があるのです。0~5カ月の赤ちゃんによく見られる行動やしぐさの理由について、発達心理の専門家・遠藤利彦先生に教えてもらいました。
ねんね~寝返りをするころの赤ちゃんがする、不思議行動のいろいろ
低月齢の赤ちゃんは、自分の意思とは関係なく“反射”という運動反応で動くことが多くあります。見る、触る、なめる、といった行動が見られてきたら、成長のサイン。自分の意思で体を動かしながら、自分の体のしくみや使い方を学んでいます。ママ・パパたちが「どうして、よくこのしぐさをしているんだろう?」「これって意味があるのかな」などと感じている9個の行動やしぐさについてみていきましょう。
【1】 こぶしをしゃぶる
【2】 口のまわりをつつくと吸いつこうとする
【3】 丸まって自分の足を触る&なめる
【4】 機嫌がよかったのに急に泣きだす
【5】 ジーッと自分の手を見る
【6】 触れたものをギュッと握る
【7】 音がするとビクッとバンザイする
【8】 「アー」「クー」と声を出す
【9】 授乳中に自分の髪の毛を引っ張る
【1】こぶしをしゃぶる
自分の指やこぶしをしゃぶることで、自分の体を確かめている行動です。触るのではなく、なぜしゃぶるのかというと、0~5カ月のころは、口の感覚がほかの部位より敏感なため。また、しゃぶる口の刺激となめられた手の刺激を受けることで、舌や手の動かし方も学習しています。くせになることはないので、心配しなくて大丈夫です。
【2】口のまわりをつつくと吸いつこうとする
赤ちゃんには、生まれながらに口に触れたものを吸ったり、すすったりする力があります。これは自分の意思とは関係なく反射(「吸啜(きゅうてつ)反射)による行動です。吸いつくからといって、必ずしもおなかがすいているというわけではありません。
【3】丸まって自分の足を触る&なめる
筋肉が発達し、自分の意思で少しずつ体を動かせるようになると、口や手を使って自分の体を確認するようになります。体の先端である足を触るのは、体全体のイメージをつかむためと考えられています。赤ちゃんの体はやわらかく、曲げていても苦しくないので、そのまま見守っていて大丈夫です。
【4】機嫌がよかったのに急に泣きだす
言葉が話せない赤ちゃんにとって、「泣くこと」は大切なコミュニケーション手段です。泣くことで空腹などの不快感、寂しさなどの感情を伝えようとします。大人には唐突に思えるかもしれませんが、泣いているときには何か理由があるものです。赤ちゃんの様子を見て、理由を探ってみましょう。
【5】ジーッと自分の手を見る
目が少しずつ見えるようになると、赤ゃんは目の前に手があることを発見します。手はどう動くのか何回も繰り返し見たり動かしたりして、自分の体を確認しようとしています。この行動は「ハンド・リガード」と呼ばれ、2~3カ月ごろに多く見られます。
【6】触れたものをギュッと握る
指を差し出すと小さい手でギュッと触れられると、赤ちゃんと握手ができたようで幸せな気持ちになりますね。これは、手のひらに触れたものを握る「把握反射」と呼ばれる反射行動の一つです。生まれてすぐから見られる反射ですが、多くの場合、2~3カ月ごろにはなくなります。足の裏を触ると、同じように足の指をギュッと閉じようとします。
【7】音がするとビクッとバンザイする
この行動は、「モロー反射」と呼ばれる反射の一つです。大人も突然大きい音がしたときなどに、体がビクッとなりますが、両腕がバンザイしているようにパッと広がるのは、この時期の赤ちゃん特有の反射です。
【8】「アー」「クー」と声を出す
これは「クーイング」と呼ばれる行動です。成長とともに口やのどが発達すると、いろいろな声を出しながら「こうするとこういう音が出る」ということを赤ちゃんが試しているのです。こうした声にママ・パパがこたえていくと、赤ちゃんの発声は活発になっていきます。
【9】授乳中に自分の髪の毛を引っ張る
お乳を飲んでいるときは手があいてるので、手を使って気晴らしをしているのでしょう。髪の毛を引っ張るのは、ちょうど触りやすい位置に頭があったから。「痛くないのかな?」と思うかもしれませんが、自ら痛みが伴うことはしないので、やめさせなくてOKです。
いかがでしたか?赤ちゃんには、その時期の成長に合わせたいろいろな行動やしぐさがあることがわかりましたね。低月齢時期だけの行動もたくさんあるので、見逃さず見守ってみましょう! (文/ひよこクラブ編集部)
※文内のまんがは似顔絵作家でもあるインスタグラマーまあこさん(@maako_manga )の体験です。
■監修
遠藤利彦先生
(東京大学大学院教育学研究科 教授)
発達心理を専門とし、発達メカニズムや子どもの生育環境を研究する発達保育実践政策学センターのセンター長も務めています。
■参考
『ひよこクラブ』2018年8月号「赤ちゃんの不思議なしぐさ解説事典」


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い