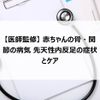「つま先歩き・片足だけつま先歩き」あんよは出来るけど…問題ある?【小児整形外科医】

歩き始めたとみんなで喜んでいたのに、ふと見るといつもつま先歩きばかりしている…?と思ったことはありませんか。個性なのか、それとも病気なのかと心配になってしまいます。見守っていいのか、受診したほうがいいのか、気になるところを小児整形外科が専門の千葉こどもとおとなの整形外科院長・西須孝先生に聞きました。
歩き始めのあんよはバラエティーに富んでいる
大人から見ると、不自然な行動にも見える子どものつま先歩き。しかし、西須先生によれば、歩き始めの子どもの歩き方は実にバラエティーに富んでいると言います。
「脚にはたくさんの筋肉があり、脳から指令を受けて動いています。歩くときには20以上の脚の筋肉が使われ、絶妙なタイミングで収縮と弛緩(しかん)が繰り返されているわけです。これを運動プログラムといいますが、歩き始めの子どもは転んだりつまずいたり修正を繰り返しながら、運動プログラムを形成していきます。その過程で歩幅が短かったり、広かったり、早歩きをしたり、ゆっくりだったりと子どもたちは、いろいろな歩き方を無意識のうちに試しているのです」(西須先生)
歩き始めのころの、いろいろな歩き方の中でも、つま先歩きはとくに多いそう。そして、つま先ばかりで伝い歩きする赤ちゃんの様子を心配して受診する人が多いと言います。
「伝い歩きのとき、つま先歩きをよくする子は、歩き始めてもつま先歩きを好むことが多いです。つま先歩きが好きな子をよく見てみると、好奇心が旺盛な印象です。遠くのものを見ようとしたり、つかもうとしたりしてつま先になるのですね。この場合は生理的なもので、病気の可能性は低いです」(西須先生)。
2才過ぎても続く場合は、専門医に相談を
歩き始めのつま先歩行は上手に歩くための練習過程のひとつ、ということですが、それが2才ごろまで続く場合は少し状況が変わってくると西須先生は言います。小児整形外科の病気である可能性も出てくるのだそうです。
「歩き始めてから3カ月以上、2才ごろまで続く場合は、『特発性つま先歩行』の可能性があります。ヨーロッパでは5%の子どもに見られますが、5才までに60%、10才までに80%が自然治癒することがわかっています。原因はわかっていないのですが、親子例が多く、親が子どものころにその状態だった場合、遺伝しやすいことがわかっています」(西須先生)
ただ、病名がついている病気ではあるものの、ほとんどは自然治癒し、治療が必要なケースはごく一部だと言います。
「まれに痙性(けいせい)まひと診断される場合があります。この場合は治療が必要となります。2才ごろからふくらはぎの筋肉がかたくなり、つま先でしか歩けなくなるのが特徴です。2才でこのような症状が出たら早めの治療が必要です」(西須先生)
痙性まひの子どもの中には、自閉症をもつ場合も
ヨーロッパの調査では、幼児期に発達障害がないと診断された子どもでも、10才になってもつま先歩行をしている場合は神経発達障害をもつ可能性があるというデータもあるそうです。
「つま先歩きがみられるから自閉症が心配という相談を受けることがありますが、これは心配しすぎです。確かに自閉症の子につま先歩きがみられることは知られていますが、健常児によくみられる症状が自閉症の子にもよくみられるのは当然のことです。ただし、つま先歩きの原因が痙性まひと診断された場合は、精神発達遅滞やそれに関連した自閉症をもっている可能性があります。
『特発性つま先歩行』や『痙性まひ』は整形外科医でも診断できる医師が少なく、見過ごされるケースも少なくありません。心配な場合は2才ごろまでに小児整形外科の専門医を受診しましょう」(西須先生)
片足だけつま先歩きする「よちよち歩き骨折」
一方、歩き始めのころ、片足だけつま先歩きをしているときは「よちよち歩き骨折」の状態になっていることもあります。
「この病気(けが)の特徴は、子どもが派手に転んだとか、高い所から落ちたとかいうような覚えが大人側にない、ということにあります。何もけがをした覚えがないけれど、しばらく片足だけつま先歩きしているのを不思議に思って受診するケースが多いです。つま先歩きではなくて、左右の足のつき方が違うことを心配して受診するケースもあります。」(西須先生)
また、子どもも痛がる様子を見せたり、痛いと訴えたりしないことが多いと言います。
「歩き始めのころの子どもの場合、自分の体の状態と言葉が一致していないことが多いですね。痛い、という言葉を知らないということです。また、痛い個所があっても痛くないように行動するという特徴もあります。『よちよち歩き骨折』はひびのケースが多く、すぐにレントゲンを撮っても映らないことが多いです。念のため2週間後にレントゲンを撮るとひびの部分に新しい骨が映るので、骨折していたね、とあとからわかります。そしてそのときには骨がくっついていることがほとんどです」(西須先生)
ただし、片足だけつま先歩きをしているときは、まれに関節や骨に細菌が侵入していることや白血病、リウマチなどの病気が潜んでいることもあるので、受診したほうがいいということです。
ママたちからの気がかりに西須先生が答えます
■1才3カ月の男の子がいます。1才ごろからつかまり立ちが出来るようになったのですが、かかとが床につきません。ずっとつま先立ちで、伝い歩きもつま先立ちのまま移動します。ネットで調べると自閉症の子どもに多いとありますが、呼んだら振り向くし言葉はある程度理解しているようです。取りあえず1才6カ月まで様子を見たほうがいいでしょうか?
【西須先生から】
足首がかたくなっていて、親が子どものかかとを床につけようと、力を入れてもどうしてもつかないときは受診したほうがいいですが、そうでない限り、まだこの時期ならとくに心配はないでしょう。2才になっても続けている場合は受診してみてください。
■1才4カ月の娘が、最近片足だけつま先でピョコピョコ歩くときがあります。ずっとその歩き方をするわけではありません。足を痛そうにしている感じもありません。この子の今のブームなのでしょうか。
【西須先生から】
いつもつま先で歩いているわけではない様子なので、今のブームなのかもしれません。よちよち歩き骨折の可能性もありますが、そうだとしてもつらそうな様子がなければ自然に治るので心配ありません。だんだん症状が目立ってくる場合や発熱を伴う場合は早めに整形外科を受診してください。
取材・文/岩崎緑、ひよこクラブ編集部
つま先歩きの多くは生理的なもので、歩き始めなら心配ないという話にほっとされた人も多いのではないでしょうか。ただ、なかには「特発性つま先歩行」などの病気が潜んでいるのも現実。2才まではしっかり様子を見ることが大切なことのようです。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い