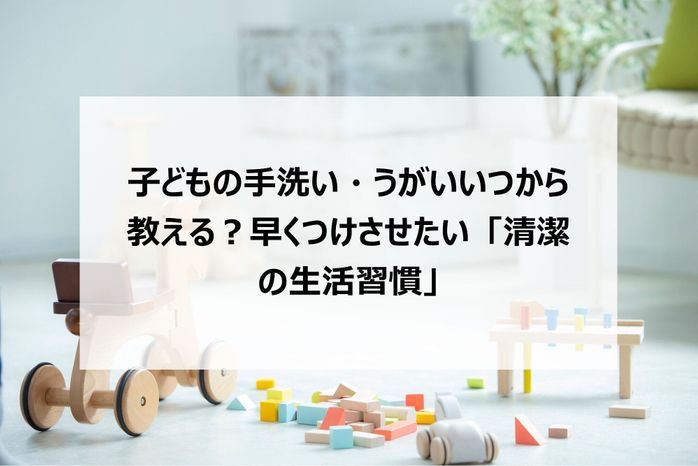子どもの手洗い・うがいいつから教える?早くつけさせたい「清潔の生活習慣」
保育園などでは、0歳代から“健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養うこと”を目的に、日々の保育のなかで、うがいや手洗いのしかたを教えています。これを清潔の生活習慣といいます。そのため家庭でも、0歳代から意識して教えていきたいものになります。
臨床心理士で、子どもの発育・発達に詳しい、日本女子大学人間社会学部心理学科教授 塩崎尚美先生に“0~2歳代の清潔の生活習慣づけ”について教えてもらいました。
年齢別★“清潔の生活習慣”を教えるときのかかわり方
0~2歳代に、清潔の生活習慣を教えるときの、ママ・パパのかかわり方を教えるときのかかわり方を紹介します。
0歳代/清潔にすることの気持ちよさを伝える
0歳代は“清潔にすると気持ちがいい!”ということを感覚で覚えていく時期。「手が汚れて気持ち悪いね。洗おうね」「着替えてさっぱりしたね」など快・不快を言葉で伝えると、感覚と言葉が結びついてしだいに“清潔にすると気持ちいい”ということがわかっていきます。
1歳代/まねを通して、やる気をはぐくもう
ママやパパのまねっ子をしながら、自分で手を洗ったりしようとする時期。そのため「〇〇ちゃん、手を洗おう」などと声をかけて、親子で一緒に手洗いを。「きれいになって気持ちいいね」など、言葉で伝えていくことも忘れずに。
2歳代/ルーティーンにして習慣づけを
朝起きたら顔を洗う、食事の前に手を洗うなどルーティーンにすると、しだいに自分からするように。気づかないときは「ごはんだから、手を洗ってくる?」と言葉をかけて気づかせてあげて。
0~2歳代★手洗い&うがいの基本の教え方
“清潔の生活習慣”というと「何から教えたらいいの?」と悩むママ・パパもいると思いますが、ここでは風邪予防ともなる手洗い、うがいの教え方について紹介します。
<手洗いの教え方>
0歳代/離乳食の前後に手をふくことから始めて
安定して立てるようになるまでは、洗面所で手洗いはしなくてもOK。その代わり、離乳食の前後に、おしぼりで手をふきましょう。「おてて、きれいにしようね」と言葉をかけながら、指の間もきれいにふいて、手をふくことの気持ちよさを伝えて。
1歳代前半/立てるようになったら、洗面台で手洗いを
しっかり立てるようになったら、洗面台で手洗いを。踏み台を用意して、自分で洗いやすい環境を整えます。手を洗うときは、ママ・パパが手首や指の間、つめの間など、こまかいところまで見てあげて。洗い終わったら笑顔で「きれいになったね」と言葉をかけると、「自分で!」という意欲につながります。
手洗いに興味を示さないときは、手洗いをテーマにした絵本などで、手洗いの必要性を伝えるのもおすすめ。
1歳代後半~2歳代前半/水量の調整のしかたなども教える
1人で手を洗うベースを作る時期。食事の前後や外から帰ってきたら、「手を洗おうね」と声をかけて、親子で洗面所へ。服がぬれないように袖をめくったり、水の出し方や水量の調整のしかた、水は出しっぱなしにしないなど、こまかい点も教えてあげて。
手洗い中に水遊びをはじめたら、「ここでは遊ばないよ。もう終わり!」と素早く切り上げて、洗面所は遊び場ではないことを伝えましょう。
2歳代後半/自分で洗えますが、見守りも必要
多少個人差はありますが、手洗いはほぼ1人でできるようになる時期。しかし洗い残しなどもあるので、なるべくそばで見守りましょう。「自分でできる!」という意識が高まるころなので、「きれいに洗えたね」「気持ちいいね」と言葉かけをして、さらにやる気を伸ばして。
<うがいの教え方>
0~1歳代前半/離乳食のあとは、お口をさっぱりと
うがいはまだできない時期なので、離乳食のあとにお茶や湯冷ましを飲ませて「お口、さっぱりしたね」と言葉をかけましょう。こうした言葉かけを繰り返すことで“清潔にすることって気持ちいい!”ということがわかっていきます。
1歳代後半/“クチュクチュ・ペッ”から練習
クチュクチュ・ペッの練習からスタート。ポイントは、ママ・パパがお手本を見せながら一緒にすることです。まずは口に水を含んでペッと吐く練習を。それができたら、水を口に含んでクチュクチュ動かす練習をします。
2歳代/“ガラガラうがい”の練習スタート
ガラガラうがいの練習をしましょう。教え方のポイントは、1歳代後半のクチュクチュ・ペッの教え方同様に、ママ・パパがお手本を見せて、親子でトライすることです。
風邪などが流行る季節なので、子どもの健康を守るためにも手洗い・うがいの「清潔の生活習慣」づけはしたいですよね。塩崎先生によるとルーティーンにすると習慣づけしやすいそうです。外から帰ってきたり、食事の前後は、手洗い・うがいをすると決めて、ママ・パパがリードして毎回同じことをするといいかもしれません。嫌がるときは、子ども用のコップやハンドタオルを用意しておくなど、ヤル気がアップする工夫も有効な場合も。(取材・文/麻生珠恵、ひよこクラブ編集部)
監修/塩崎尚美先生(日本女子大学人間社会学部心理学科 教授)
臨床心理士。専門は発達臨床心理学、乳幼児からの親子関係、子育て支援。一男一女のママでもあります。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い