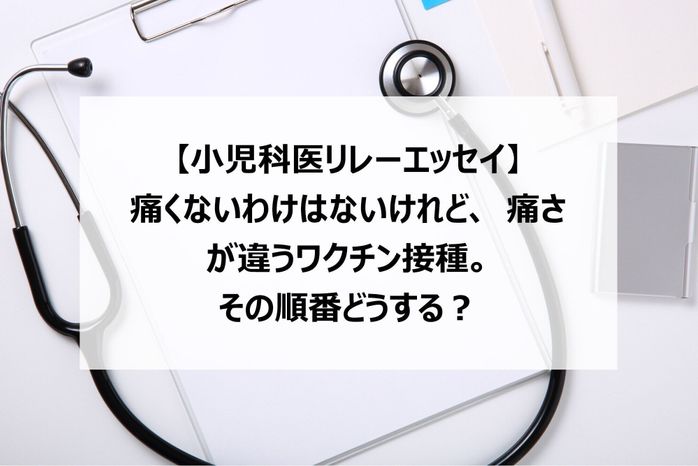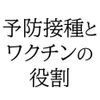【小児科医リレーエッセイ 22】 痛くないわけはないけれど、痛さが違うワクチン接種。その順番どうする?
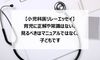

「日本外来小児科学会リーフレット検討会」の先生方から、子育てに向き合っているお母さん・お父さんへの情報をお届けしている連載です。今回は、鹿児島県鹿屋市・まつだこどもクリニック院長の松田幸久先生です。クリニックの正面にはくまさんの像があり「くまさん先生」と親しまれている松田先生から、子どもの命を守る「ワクチンの受け方」についてのメッセージです。
ワクチン接種物語
毎年10月からはインフルエンザのワクチン接種が始まり、クリニックは、子どもたちの泣き声でにぎやかになります。しばらくは、子どもたちには 試練の日々が続きますが、われわれ接種する医師にとっても、子どもたちに嫌われたり、接種の時に蹴(け)られたり、かまれたりすることもあり、戦場となります。
接種に来る前に
たいていの子どもは、病院に来る前に「今日は注射をする日だよ」などと説明をされているようですが、中には、「ワクチン接種のために来たこと」を直前になって知ってしまい、「いやだ。注射はしない!」とぐずったり、暴れて抵抗したり、中には逃げ出す子どもいます。ワクチン接種は、針を使うので痛いのは当然なのですが、どんなに「痛くないよ」「すぐ終わるから」と言っても、子どもは、不安でいっぱいです。やっぱり、ワクチン接種を内緒にして連れてくるのは、子どもをだまして連れてくるわけですから、よくありませんね。そうなると、お母さん・お父さんたちや、われわれ接種する医者は悪者です。接種の時は、子どもに説明してから来てもらいたいものです。
痛い? 痛くない?
どんなに細い注射針を使っても、針を刺すのが接種なので、痛くないはずはありません。年齢が上の子どもたちにとっては、我慢できる痛さもあるようですが、小さい子ども、とくに赤ちゃんには、大きな試練です。接種する側も、なるべく痛く感じないように努力はしています。接種した子どもの反応を見ると、皮膚に針が刺さる時に痛がる子もいれば、針からワクチンを注入する時に痛がる子もいます。また種類によっては痛いワクチン、痛くないワクチンがどうもあるようです。生ワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン、おたふくかせワクチン、水痘ワクチンなど)を接種する場合、あまり泣かないようです。不活化ワクチン(インフルエンザ、ヒブワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、日本脳炎など)は、1歳未満に接種が多いので、子どもが大声で泣くことを経験します。
予防接種を嫌がらない工夫
接種する場所の壁には、子どもたちが大好きなキャラクターなどが優しく「頑張ってね。」と言っている絵などを掲示していますので、接種前に気をそらさせるのも、効果があります。接種する時に、「1、2、3!」とかけ声と共に接種するものも有効です。
接種が終わると、接種部位に小さなばんそうこうをつけています。この小さなばんそうこうに、子どもたちが好きなキャラクターなどを描いています。すると接種前に「あのばんそうこう貼って」などとリクエストがあることもあり、子どもたちは、頑張って接種させてくれます。
接種するワクチンの順番は?
なるべく、痛みの少ないものから接種しています。同時接種をすることがよくありますが、順番としては、生ワクチンがあれば、そちらを最初に接種し、プレベナー(小児肺炎球菌)はほぼ全員の赤ちゃんが泣くので最後に接種しています。
きょうだいでくる家族では、だいたい年齢の上の子どもから接種しています。お兄ちゃんが頑張っているところを下のきょうだいに見せたりしています。黙っていると、何も知らない弟や妹を先にさせるお兄ちゃんたちもいるようですが、そんな時は、下の子どもが終わったら、自分の番が来ても、接種を嫌がる上の子どももいます。最初から、年上の順にすると決めて接種したほうが、スムーズに接種ができると思います。
子どもさんには優しい声かけを!
痛い注射をする直前まで、「注射をしないから」と言っているお母さん・お父さんもいますが、これは明らかにうそですので、言わないでほしいです。
接種前から「もう泣くの」「お兄ちゃん(お姉ちゃん)なのに、おかしい」と言ったり、また大声で泣く子に「静かにしないさい」と言ったりするのもかわいそうですね。
子どもたちは、痛い注射を我慢したのですから、泣かない子も、泣いた子もえらい!しっかりとほめてあげてください。看護師さんや、お母さん・お父さんたちの優しいひと言は、何よりのごほうびです。「終わったら、コンビニで何買おうか」「終わったら、何を食べに行こうか。」などというごほうびがあるようですが、うらやましい限りです。
文/松田幸久先生(まつだこどもクリニック院長)
Profile
鹿児島大学医学部を卒業。同年同大学小児科学教室に入局。2001年に、鹿屋で「まつだこどもクリニック」を開業。専門は、小児科学、とくに臨床遺伝学、遺伝カウンセリング。障害をもつ子どもたちやターミナルの子どもたちと接するようになり、童話を書き始める。「どろぼうサンタ」(こぐま社)、「天にかかる石橋」(石風社)、「魔法のドロップ」(石風社)などがある。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い