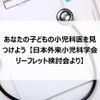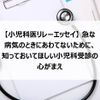【小児科医リレーエッセイ 23】 小児科医は病気を診るだけではなく、おせっかいな「おっつあん」です


「日本外来小児科学会リーフレット検討会」の先生方から、子育てに向き合っているお母さん・お父さんへの情報をお届けしている連載です。今回は、鳥取県境港市・岡空小児科医院院長の岡空輝夫先生です。日々の診療で感じていることからのメッセージです。
クリニックに住む、近所のおせっかいな「おっつあん」!
私が子どもだった昭和30年代は、子どもとはいえ、近所の大人たちとの接触(会話などのかかわり)もあり、目上の人とのあいさつや言葉づかいなど自然に学んできました。
クリニック受診の子どもたちの現状はどうでしょうか? 順番が来ていないのに、まだかな〜?とのぞきに来る子! 待合室を走り回る子!
「○○さ〜ん!」と呼んでも、返事なく、黙って診察室へ入ってくる…。
「こんにちは!」のあいさつにも、無言のまま!
「今日はどうしたの?」の問いかけにも、後ろに立つ親のほうに目を向けるだけ!
クリニックのトイレ・洗面所はどうでしょう?
トイレのふたは開いたまま! トイレットペーパーは散らかっている!
洗面台は水浸し! スリッパはそろっていない・・・
小児科医の役割って、病気を治すことだけではないはずです。園医や学校医の仕事はもちろんですが、クリニックでは子どもたちと直接会話できる特権を持っています。
その「特権」を生かさないのはもったいない! 昔の「おっつあん(おじさんのこと)」(あるいは、「おばはん(おばさん)」)のように、子どもたちに何かとおせっかいを焼くのも大切な役目じゃないでしょうか?
周囲とのかかわりがあった古き良き時代
私は1954年生まれで、母校の鳥取大学を卒業し、小児科医になって40年が経過しました。 もちろん、私自身もそして周囲の子どもたちも、決して模範生のような言葉づかいをしていた訳ではありません。私自身が歳を取っただけなのかもしれませんが、古き良き昭和の時代は、何かと周囲の大人の人とのかかわり合いと会話があり、少しずつではありますが、目上の人とのあいさつや言葉づかいを直され、怒られ、教えられ、そしてはぐくまれながら、普段の生活の中で学んできたように思います。
子どもたちの言葉づかいには心配な面が
勤務医時代はお母さんから問診を取ることのほうが多かったように思いますが、開業してからは20年以上、日常診療において、来院する子どもたちに直接、問診するように心がけています。「お母さんはちょっと黙って(い)てね!」と、子どもたちに「自分で言いましょう!」と問いかけています!
もちろん、すごく礼儀正しく、きちんと話してくれる子どもたちもたくさんいますが、多くの子どもたちの言葉づかいには心配な面が多々あります。
たとえば・・・
「今日はどうしたの?」と問うと、『ゲロ せき 熱』と単語だけ・・・
「調子はどう?」と言えば、『大丈夫』『普通』『微妙』の3パターン
「今日の給食おいしかった?」には、『普通!』が定番
「おかずは何だったの?」の問いには、『忘れた!』がいちばん多い。
「さっき食べたでしょう! 何とか思い出して!」で、『肉 魚 汁 白飯』
中学生に「中間テストはどうだった?」と問えば、『微妙・・・』
たまに待合室が混んで待ち時間が長いと、診察室をのぞいて…、『まだか〜!』
「おせっかい」を受けに小児科に来ませんか
いかがでしょうか? 私を含めベテラン小児科医は当然のことながら、お父さんやお母さんも何となく、すでに気づいていることかもしれませんね。昔と違い、ほとんどの両親や学校の教職員は格段に優しいですから、礼儀作法、言葉づかいなどを子どもたちは厳しく教えてもらっていません。当然ながら、生まれながらにして身に備わっているものではないので、少しずつ失敗しながら、学んでいけばいいのです。
時間をより有効に使うためには、薬をもらうためだけに小児科受診するのは、いかにももったいないと思います。とくに古き良き昭和の時代を知る、ベテラン小児科医のおっつあん(おじさんのこと)、おばはん(おばさんのこと)との会話は子どもたちの人生に彩りを添えるものだと思います。追加料金はかかりません(笑) 遠慮しないで、ぜひともご利用ください。
文/岡空輝夫先生(岡空小児科医院院長)
Profile
1954年夏、深夜に生まれ、急遽駆けつけてきた産婆さんが、「今夜は星が輝いていた!」の一言で、輝夫になったらしい。 鳥取大学医学部を卒業。 1996年に、郷里の妖怪に逢える街、境港市で「岡空小児科医院」を開業。 専門は、小児科学、とくに小児腎臓病、感染症、アレルギー、小児保健。 とかく検査や投薬が多い日常診療で、できるだけ検査や投薬の少ない医療を目指している。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い