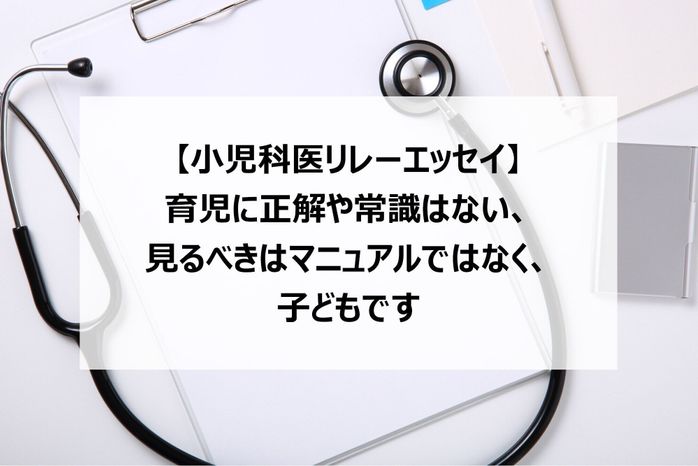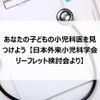【小児科医リレーエッセイ 21】 育児に正解や常識はない、見るべきはマニュアルではなく、子どもです
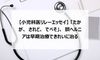

一見すると便利な情報選択の落とし穴
今こうしてネット経由で情報を見ているあなたに伝えたいことがあります。スマホやパソコンからすぐにアクセスできる情報はとても便利です。検索すれば何種類かの知りたい情報に簡単に到達できます。複数の候補の中から自分の判断で一つを選択すると情報が本当は間違っているリスクを過小評価しやすいので、「正しい情報」と信じ込む危険性があります。今読んでいる情報が本当に子どもに合っている情報なのか、ちょっと考えてみましょう。著者はあなたの子どもを診たことがないのです。味見をしたことのない料理をおいしいという人と一緒です。
育児雑誌やネット情報の限界
何年も前のことですが、私が書いた育児雑誌の記事を切り抜いて母子健康手帳に貼っている方がいました。それはそれで著者としてうれしいことですが、同時にしまったと思いました。その記事の内容はその方の子どもに合っていないのです。育児雑誌、各種ウエブサイトやSNSに情報を書き込むとき、「10人が読んで8人が納得して6人が当てはまれば合格点かな」ぐらいの気持ちで原稿を書いていました。すべての子どもに当てはまる治療はありません。ましてや育児は千差万別、成長や発達は個人差が大きく、平均的な子どもを想像して記事を書いていました。実は記事が当てはまらない子もそれなりにいるのです。
エビデンス(証拠)があっても過信はできない
医学は科学的根拠によって裏打ちされていることは事実です。たとえば「赤ちゃんの皮膚に保湿剤を使うことで湿疹を予防する効果」は自然科学的に証明されているので間違いではありません。だからと言って、全員に効果があるという意味ではありません。何もしなくても治療対象となる湿疹ができない子はもともとたくさんいます。つまり保湿剤を使わなくても湿疹ができない子どもに保湿剤は不要です。科学的エビデンスが示しているのは、保湿をすることで湿疹を作る子の何割かは救われる可能性があることであり、保湿剤(これも薬です)が必要な人を見極めて適切に使いましょうということです。
多様性を認めない育児はブームに翻弄される
私が小児科医になったころ(昭和の話ですね)、保湿剤はまったく使われていませんでした。そもそも保湿剤としてあったのはワセリンとオリーブ油ぐらいです。そして赤ちゃんの肌に使うのは天花粉(ベビーパウダー)だけでした。あのころはサラサラな肌が赤ちゃんのきれいな肌でしたが、それでも子ども全員に湿疹ができることはありませんでした。今はどうやらしっとりした肌が赤ちゃんの理想的は肌となっているようです。ひと昔前は若い女性の夏の美しい肌は小麦色の肌でした。サンオイルを塗ってきれいに日焼けさせていましたが、今時のきれいな肌は白い肌で、みなさん日焼け止めを塗っています。小麦色の肌と白い肌、どちらが本当はきれいな肌なのでしょう。
育児は多数派になる必要はありません。個性を大切にと言いながら多数派になろうと努力する育児は疲れます。ファッションではないので、流行の最先端をめざすことはやめましょう。
子どもの身体と心に不安があったら小児科医を受診しましょう
育児の中で子どもの変化に不安を感じることは当然です。わからないこと、困ること、あわてること、驚くことの連続です。そんなとき、どうしたらいいかスマホで検索する人は数多くいます。いろいろと調べて答えを見つけようとする努力も大切です。でもスマホやパソコンの情報を追いかける前に、せめて10分間だけまずは子どもをよく見てみましょう。頭のてっぺんから足の裏まで見てあげましょう。これを繰り返すと、もしかしたら、答えを見つけることができるかもしれません。そしてどうしても迷うこと、うまくできないことがあるならば、ぜひ小児科医を受診しましょう。
迷っているときには「それで大丈夫」と言ってもらえるかもしれません。うまくできないときには別のやり方を教えてもらえるかもしれません。育児の主役のあなたを支えることが小児科医の使命です。
育児に関するネット上の情報が正しいか間違っているかを判断することは、あまり役に立ちません。正しい情報であっても自分の子どもに合ってるかどうかがわからないからです。ネット検索をしている間、実はパソコンやスマホを一生懸命見ている自分に気づいてください。まずは子どもをよく見る時間を作りましょう。そしてわからないことがあれば小児科医に相談してください。きっとあなたの育児を支援してくれるでしょう。
文/崎山 弘先生(崎山小児科院長)
開業以来32年、保育所の園医、小学校の学校医、市の教育委員、保護司などの活動を通して地域の子どもたちとかかわる。診療所では子どもの心と身体の心配事に対応するとともに予防接種を積極的に実施し、Hibワクチンや肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワクチンなどの治験(日本の子どもたちが接種できるようにするための臨床試験)にも協力。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い