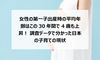「小学生の学力は地域によって差があるの?」教育格差問題を専門家が解説
「全国学力・学習状況調査」の報告によると、都道府県間の学力格差は縮小傾向にあるそうです。その背景について青山学院大学学部特任教授・耳塚寛明先生にうかがいました。
公立小学校の学力地域格差がなくなってきた?
地域といってもいろいろあります。まずは、都道県間の格差に注目してみましょう。
下のグラフは、2017年の「全国学力・学習状況調査」(国立教育政策研究所)の国語と算数の都道府県別平均正答数(全50問中)のデータです。
※画像クリックで拡大表示可
「全国学力・学習状況調査」とは、全国の国公私立の小中学校が参加し、教科は小6と中3の国語と算数・数学。各科目とも主に知識を問うA問題と、応用力を問うB問題に分かれています。
この調査の結果を都道府県別でみると、平均正答数の差はごくわずかであり、平均正答率の格差は縮小傾向にあります。グラフは2017年のデータですが、今もこの傾向は変わりません。
その背景を耳塚先生に聞きました。
学力の地域格差が縮小傾向。その理由は?
「学力格差が縮小したのは大きく2つの理由が考えられます。
『全国学力・学習状況調査』のデータを見てもわかるように、上位層と下位層の差はわずかです。この結果から、日本は都道府県間の学力格差を克服しつつあると言えるでしょう。
1963年文部省全国一斉学力テスト(中学校・500点満点)の結果では、最上位県298.3点と最下位県215.7点と、その差が約80点と、かつては日本も地域ごとに大きな学力格差があった時代もありました。当時は、学力と県民ひとりあたりの所得など地域の経済力が結びついていた時代。大都市圏の経済力や文化の豊かな地域のほうが、学力は高い傾向があったのです。
なぜ、教育格差を縮小できたかというと、第二次世界大戦以降、とくに昭和期は、政府が小中学校の教育条件を整備し、自治体の財政状況の良し悪しが子どもたちの教育に直接結びつかない仕組みづくりを進めてきたからです。また、経済だけでなく、美術や書籍、メディア、情報など文化的な豊かさの格差自体が年々小さくなり、平準化してきたことも考えられます。どの地域でも同じ条件で教育を受けられ、文化を享受できるようになり、地域の経済力と学力水準が相関しなくなった影響は大きいでしょう。
ただし、都道府県間の学力格差はわずかになりましたが、都道府県の内部での学校間の学力格差問題は残っています。これは、地域間の文化的環境の違いや、教育を大切にする伝統、教育を支える学校の組織力や教員の力量などいろいろな要因があるため、すぐに解決するのは難しいのが現状です。
また、2019年度からは『全国学力・学習状況調査』が大きく変わり、知識を問われるA問題と、活用の力を問われるB問題が統合され、B問題の比重が増えています。今までの「知識」だけでなく、知識を「活用」する力がより重視されるようになるため、縮小傾向だった都道府県間の格差も、今後は変化していくかもしれません」(耳塚寛明先生)
まとめ
2020年は小学校で新しい学習指導要領による教育がスタートし、大学入試制度も変更されるなど教育の流れが大きく変わる節目の年になります。たまひよONLINEでは、子どもの教育がどのように変わるのか、学力の都道府県格差がどのように変化していくのか、今後も情報を発信していきたいと思います。(文・酒井範子)
耳塚寛明先生
青山学院大学 コミュニティ人間科学部 学部特任教授。お茶の水女子大学名誉教授。専門は教育社会学。著書に『平等の教育社会学 現代教育の診断と処方箋』など。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い