【小児科医リレーエッセイ 4】 「手づかみ食べ」はテーブルマナーの始まりで、「一人できれいに食べる」ゴールにつながります

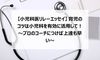
離乳がスタートすると、離乳食を食べさせる際の悩みや気がかりが出てくるようです。「日本外来小児科学会リーフレット検討会」の先生方から子育てに向き合っているお母さん・お父さんへのメッセージをお届けします。第4回は、東京・UTAKA DENTAL OFFICE佐々木歯科の佐々木洋先生の「食べさせ方・手づかみ食べの大切さ」についてです。
離乳食は「食べさせる」よりも「自分で食べる」ことがポイント
不随意な哺乳と異なり、食べる機能の学習では、捕食(とり込み)→送り込み→押しつぶし→舌の上にまとめ→のどに送り込むなどの分離した随意運動を覚え、それをつなげていきます。食べ物を口にとり込み飲み込むのには、味覚・触感・温感などの感覚と口唇・舌・あごや頭頸部の絶妙な協調運動が必要です。
それには頭で理解して器官の動かし方を覚えるのではなく、赤ちゃん自らが食べ物を処理することの繰り返しから、とり込む量や性状と処理のしかた、そしてその結果を身体で覚えていくことが大切になります。
たとえば離乳初期(5~6カ月ごろ)には、ペースト食をのせた浅いスプーンを赤ちゃんの下唇の上に置き、赤ちゃんが自分で口にとり込むのを待ってスプーンを抜き、その後、飲み込むのを待ちます。
口蓋(こうがい)前方部・前歯・口唇・舌は敏感なセンサーです。早く、いっぱい食べさせようとして、口の中に食べ物を入れてしまうと、赤ちゃん自らが捕食して食物の性状を感じることができないので、その後に続く押しつぶしや食塊(飲み込むことのできるまとまり)形成などの結果との対比や整合が生まれず、学習の混乱と遅れを招きます。
離乳の目標は「食べたい」気持ちをもって「一人で食べられる」ことなので、食べさせることよりも「自分から食べる」行動を引き出すことにコツがあります。
離乳期の赤ちゃんは、未経験の食べ物を避けようとして当たり前
離乳が進むとよく受ける質問が「なかなか食べてくれません」です。せっかく作ったのだからお母さん・お父さんは全部食べてほしいと思いますよね。でもこれには赤ちゃんが自分の食べる能力に合わずに食べられないだけでなく、なじみのない味・におい・触感は苦手に感じることがあるという深い訳があるのです。
視覚で確認した獲物を捕食する肉食動物と異なり、雑食動物は初めて口にする食物は警戒し、におい・味・食感などを試しながら安全を確かめようとします。これは「新奇恐怖」といわれるものですが、離乳期から幼児期の子どもにとっては、毎食がまさにこの繰り返しで、未体験の食べ物を避けようとするのは当たり前のことなのです。
体で安全を確認し、脳が興味をもつことの繰り返しから食域が広がります。食体験の乏しい幼児の食べる意欲や興味を強化する因子は、機能や好みに合った食物性状だけではありません。空腹などの生理的要因と安心や期待感をもたらす周囲からのはたらきかけも重要です。
家族がおいしそうに食べている様子に、子どもの食べる興味も増します。
手づかみ食べで、自分から手を出す行程がおいしさの源
離乳の最終課題である「一人食べ」では、腕・手・指と頭頸部の協調運動を学習します。視覚や頸部の運動機能が発達しても、手指や腕の運動が未熟な子どもにとって、手指の先にある道具を使うのは至難の作業です。
スプーンやフォークなどの食具使って食べられるようにすることはあせらないで、むしろ汚れを気にせずに十分に手づかみ食べを経験させることが大切です。手づかみ食べによって協調運動の基礎をしあげておけば、食具食べの上級コースの進み方はスムーズになります。また,食べる意欲が増す相乗効果も得られます。自分から手を出す行程が、おいしさの源なのです。
ムラ食べや食が細いには、波があるものです
離乳完了後も、「食が細い・食べ方にムラがある」など食べる意欲についての相談を受けます。チェックしたいのは、身長・体重の変化と、①食べられる量やペースと実際の差、 ②食事時の空腹状態、③食べるより遊びたいのかなどの項目です。
お母さん・お父さんはよく食べたときの量を理想とし、毎回同じように食べさせたいと考えますが、子どものムラ食べはよくあることで、数日間の体重変化に問題がなければ心配はいりません。就寝時刻・体を使った遊び・間食や飲料といった生活習慣を検証し、早起きや外遊びなど空腹がうまれる工夫を考えましょう。
食べる楽しさがわかれば、おのずと手はお皿に伸びます。このとき出てくる言葉は「おいしい」ですね。未来に向かって生きる力を育てるのだから、なにより「食べる」が幸せを感じる行為であってほしいと思います。家族やお友だちと一緒に食べて「おいしい」を共有できたら、喜びは倍増するでしょう。食べられることの有り難さも共有できたら、いただく命と作った人たちへの感謝の心も育ちます。こんな気持ちが、「いただきます」と「ごちそうさま」には込められています。家族で囲む食卓もお友だちと一緒の食事も、食物の話題と一緒に「いただきます」で始め、満足感と合わせて「ごちそうさま」で終わりましょう。
文/佐々木洋先生
(UTAKA DENTAL OFFICE佐々木歯科)
1977年東京医科歯科大学歯学部卒業後、子どもの発育にかかわる歯科医学3講座(東京医科歯科大学小児歯科学、昭和大学歯科矯正学・昭和大学口腔衛生学)に在籍。2001年より現職。現在は乳幼児から高齢者まで、ライフステージに沿った口腔成育(口のはたらきを生かした心と身体の成育支援)をテーマに、家族単位の診療に取り組む。日本矯正歯科学会認定医、日本小児歯科学会所属


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い

















