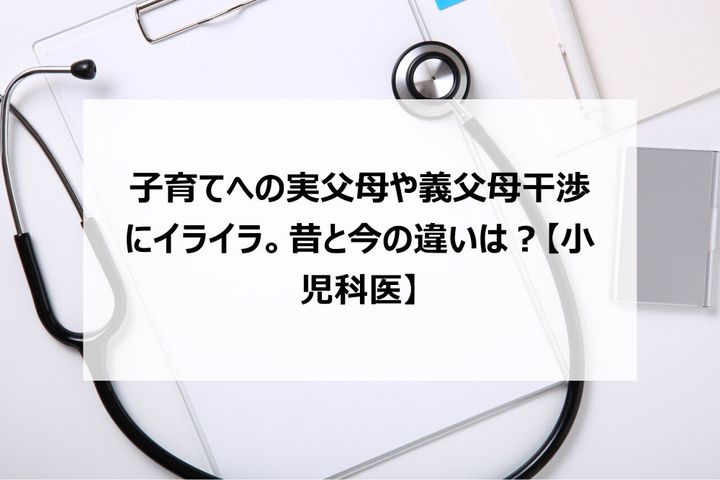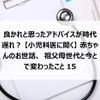子育てへの実父母や義父母干渉にイライラ。昔と今の違いは?【小児科医】
赤ちゃんには元気ですくすく育ってほしい。そう願う気持ちは、昔も今も変わりません。でも、ばあば・じいじに言われることで、「それって今は違うのでは…」と感じることもありませんか。また何度もいわれるとイライラしてしまうことも・・・。そんなママやパパの混乱を解決するべく、慶應義塾大学医学部・小児科教授の高橋孝雄先生に、赤ちゃんとの毎日のかかわり方で、今、知っておきたいことを聞きました。
抱きぐせ、かんの虫、3才児神話…これらのアドバイスに根拠なし!
――ばあば・じいじから「抱きぐせがつくから泣いてもすぐに抱っこしないほうがいい」といわれるママやパパは多いようです。実際はどうなのでしょうか。
高橋先生(以下敬称略) 「抱きぐせ」というものはありません。近年では多くの研究から、抱っこに代表されるスキンシップが、赤ちゃんの成長にいいことがわかっています。遠慮なくたっぷり抱っこしてあげてください。たくさん抱っこすることで、親子のきずなが深まっていきます。
――たっぷり抱っこすることが大事ということは、「赤ちゃんのときから保育園に入れるなんてかわいそう」という、ばあば・じいじの意見は正しいのですか?
高橋 戦後、「子どもが3才になるまではママが子育てに専念すべき」という、「3才児神話」の考えが広まりました。しかし、赤ちゃんとのかかわり方は、時間の長さではなく深さが大事、というのが今の考え方です。アメリカの大規模研究でも、働くママと専業ママで子どもの成長に明確な差がないことがわかっています。親子の信頼関係は、一緒にいる時間の長さではなく、子どもとの向き合い方の深さや温かさによって築かれていくのです。
つまり、子どもを「かわいい!」「大切!」と思って育てる、これができていれば、保育園に入れる入れないで変わることは何もないということ。ママとパパが「保育園に預けて共働きをする」と決めたのなら、自信を持ってそのように進めてください。
――赤ちゃんが指しゃぶりをするのを見て、ばあばから「愛情不足なんじゃないの?」と言われ、不安になってしまうママやパパもいます。
高橋 指しゃぶりは愛情不足からくるものではありません。赤ちゃんは、ママのおなかの中にいるときから指しゃぶりをしています。五感が発達していく過程によく見られる行為なのです。そのまま様子を見ていて大丈夫ですよ。
ちなみに、昔よく言われた「かんしゃくを起こすのは『かんの虫』がついているから」というのもまったく根拠のない話。「かんの虫」なんて存在しません。
かんしゃくは感情の発達によるもので、いわば成長の証し。イライラを解消する術を身につけている途中なので、おおらかに見守ってあげてほしいですね。
しつけは子どもを「説得」するために行うもの
――しつけについての考え方も、昔と今ではずいぶん違っています。今どきのしつけ方について、先生の考えを教えてください。
高橋 昔に比べて、今は「しかりにくい時代」だと感じています。親子関係だけでなく、学校教育でも、会社の上司と部下の関係でもそうです。ばあば・じいじの時代に比べて今のほうが、しかり方について悩む場面は多いと思います。
しかることは説得することです。つまり、「しかられたことを子どもが納得できるようなしかり方」が必要なんです。
子どもをのびのび育てることと、なんでも子どもの思い通りにさせることは違います。「この振る舞いを放置したら、この子は将来痛い目にあうだろうから、今ここで理解させなければいけない」と判断したら、毅然(きぜん)とした態度でそのことを子どもに伝え、どうすればいいのかを、子どもにわかる言葉で伝えてください。
――昭和の子育てでは、「言ってもわからない子は、たたいて覚えさせればいい」というような考え方もあったようです。今の時代はどう考えるべきでしょうか。
高橋 体罰は絶対に許されるものではありません。でも、手を上げることが説得力を発揮する場面もゼロではない、ということでしょう。
もちろん、ただの暴力は絶対にダメです。まずは、振り上げたその手に子どもを納得させるだけの力が宿っているのか、それを冷静に判断する必要があります。
「気づいたら、子どもに手をあげていた」ということがあったなら、ひとりで悩まずに、家族や地域の保健師さんなどに相談してみましょう。いろいろな子育てサポートを上手に利用することも、子どもを育てるうえで大切なことです。
早期教育は、「子どもに成功体験を与えるか」を選択の基準に
――今は早期教育に熱心なママ・パパが多いので、「そんな早くからいろいろなことを教えなくても…」と考えるばあば・じいじと意見が食い違うこともあります。
高橋 「子どものために何かしてあげたい」「よりよい教育環境を与えてあげたい」と願うのは、親の常ですね。お子さんにやらせてみたいことがあるのなら、ぜひトライしてみてください。
ただし、ママやパパに理解しておいてほしいのは、「早くできるようになる=もっとできるようになる」ではないということ。ベビースイミングに通っている赤ちゃんが、オリンピックに出るような水泳選手になることは、あまり考えられません。だから、子どもが楽しくできることはやらせればいいし、やりたくないこと、好きじゃないことはやめればいい。
――「続けていればできるようになるから頑張って!」と励ますのはよくないのでしょうか?
高橋 もちろん、子どもを励ますのは大切なこと。たくさん応援してください。でも、それも程度問題。子どもが嫌がることを無理にやらせても、いいことは一つもありません。できないことを続けて子どもが自信を失ってしまったら、子どもの発育・発達に悪影響を与えてしまいます。
乳幼児期は「できた!!」という達成感を味わえることをたくさんさせてあげてください。ママやパパをはじめとする周囲の大人たちに「うまいね~」「できたね!」「すごいすごい!!」とたくさんほめてもらうことが重要。子どものうちに成功体験をたくさん積んで、多少の困難には負けない強い心を手に入れれば、自分のことをますます好きになれるからです。
「早期教育をさせたい」と考えているママやパパは、それをさせることで、成功体験を通じてわが子の自己肯定感をはぐくむことができるか、という視点で選んでみてはいかがでしょうか。
「子どもがもともと持っている長所を伸ばすことが最高の子育て」。私はそう考えています。
聞き手/東裕美、ひよこクラブ編集部
昭和・平成と令和では子育て環境も育児の考え方もずいぶん変わっています。ママとパパが「うちはこう育てる」と決めたら、そのことをばあば・じいじに理解してもらうことが大切。そして、一緒に赤ちゃんの成長を見守ってもらいましょう。
6月25日に発売された高橋先生の著書

「子どものチカラを信じましょう 小児科医のぼくが伝えたい 子育ての悩み解決法」(マガジンハウス)には、「『最高の子育て』とは何か」のヒントが詰まっています。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い