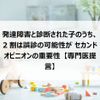「食べこぼしが多い」「片づけが苦手」それって、しつけの問題ではなく発達障害かも?!

食事のときいつも食べこぼしが多い、お片づけがうまくできない、ボタンがはめられない…など、子どもが極端に不器用だと感じたら…もしかするとそれは発達障害の一つ、発達性協調運動障害(以下DCD)かもしれません。青山学院大学教授で小児精神科医の古荘純一先生に話を聞きました。
お片づけができない、遊具で遊べないのもDCDの症状の一つ
――DCDとは、どのような障害のことですか?
古荘先生(以下敬称略) 生まれつきの脳の機能障害により起こる運動機能にかかわる発達障害です。自閉スペクトラム症(以下、ASD)、注意欠陥・多動性障害(以下、ADHD)、学習障害(以下、LD)などは広く知られていますが、日本ではまだ独立した発達障害として注目されていません。
DCDは、身体機能に問題がないにもかかわらず、運動を組み合わせることができない障害です。運動が極端に苦手だったり、人並み外れて不器用だったりするのが特徴です。有病率は学童期の子どもの5〜6%。保育園の20人クラスに1人はいるということになり、珍しくありません。また、ASDやADHDと合併して見られることも多い障害です。
これまでは、ハサミが使えない、ボール遊びが苦手などの特徴がある子は、過保護な育て方や運動不足が原因だと思われてしまいがちでしたが、実は、だれのせいでもない生まれつきの障害である可能性があるのです。
――DCDの子は、どんな運動が苦手なのでしょうか?
古荘 協調運動とは、手と足、見る・指を動かすなど別々の動作を1つにまとめること。DCDの子は縄跳びやスキップ、ボールを蹴って走るなどの協調運動が苦手なことがあります。お片づけも協調運動の一つ。私たちが何気なく行っている「箱の中におもちゃをしまう」という動作や、「ボールを棚に戻す」という動作も、DCDの子にとっては難しく、すごく時間がかかってしまいます。
DCDの症状は人によってさまざまですが、以下のような動作ができない、すごく時間がかかるな、と気づいたら、DCDの可能性があります。
・指先を使うのが苦手(箸やハサミを使えない、お絵描きで線がなぞれない、ひもを結べない)
・のりを使うと手がベトベトになる
・スプーンやコップなどがうまく使えない
・着替えが遅い
・三輪車に乗るのが下手
・公園などの遊具で遊べない
――DCDの兆候は何歳くらいからわかるのでしょうか?
古荘 だいたい2才を過ぎるころになると、定型発達の子どもとの差が出てくるため、特徴が目立ってくるでしょう。言葉はしっかりしゃべるのに食べこぼしが多いとか、お片づけしなさいと言われる指示はよくわかっているのに、毎回すごく時間がかかってしまうなら、注意してみる必要があるでしょう。
できないのはしつけや努力不足ではない。その子自身の楽しみ方を見つけてあげよう
――子どもがDCDかもしれない、と感じたら、親は子どもの苦手な運動をどのように教えればいいでしょうか?
古荘 目標を低く設定し、子どもが達成感を味わいやすい形でやってみる方法があります。ひもを結ぶのが苦手なら、そのプロセスのどの部分ができないか、まずは観察してみる。ひもを重ねる、輪をくぐらせるなどが苦手なら親がやってあげ、最後にひもの両端をぎゅっと引っ張るところだけ子どもにやらせてみるというやり方も。
DCDの不器用さは成長とともに自然に治るものではなく、ほうっておいても改善しません。ただ、自分でやり方がわかり、一度習得するとできるようになっていきます。
サッカーをやるなら、最初からボールを蹴るのではなく、まずはボールを手に持ってゴールに運んでみる。ゴールにボールを入れることができれば、楽しい成功体験になります。DCDの子はもともと体を動かすことが嫌いなわけではありません。大切なのは、その子なりに運動を楽しめること。
「こうやるんだよ」と大人が一方的に教えると、できないときに運動嫌いや苦手意識につながりかねません。その子ができることや楽しめることに注目して、その子のルールで一緒に遊んであげるといいでしょう。
――子どもをほかの子と比べて落ち込んでしまったり、できないことにあせってしまったりする親もいると思いますが…
古荘 集団生活に入る年齢になると、ほかの子との発達の違いを気にしてしまう人もいるかもしれません。何度教えてもうまくいかない、忙しいときに時間がかかってしまうと、イライラすることもあるでしょう。でも、基本的に子どもは親や先生にほめられたいから、なんにでも一生懸命です。DCDの子は、ほかの子よりもできないことがあることは自分でもよくわかっています。それなのにしかられたり責められたりし続ければ自信ややる気を失ってしまいます。
まずは、子どもに不器用さや運動の苦手さがあるのは、決して親のしつけ方や本人の努力不足ではないと知っておくことが重要です。その子なりのがんばりをほめ、成長を喜んであげましょう。どうしても生活に支障が出るなら、客観的な視点でDCDの可能性を考え、保健センターなどの支援者に相談してみるといいかもしれません。
お話・監修/古荘純一先生 取材・文/早川奈緒子、ひよこクラブ編集部
親が「ほかの子と同じように」「できないと恥ずかしい」と、子どもの苦手なことを強制することは、自信を奪い、苦手意識を深めてしまいます。ほかに楽しめる運動を見つけながら、子どものペースでゆっくり成長できるようサポートしてあげましょう。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い