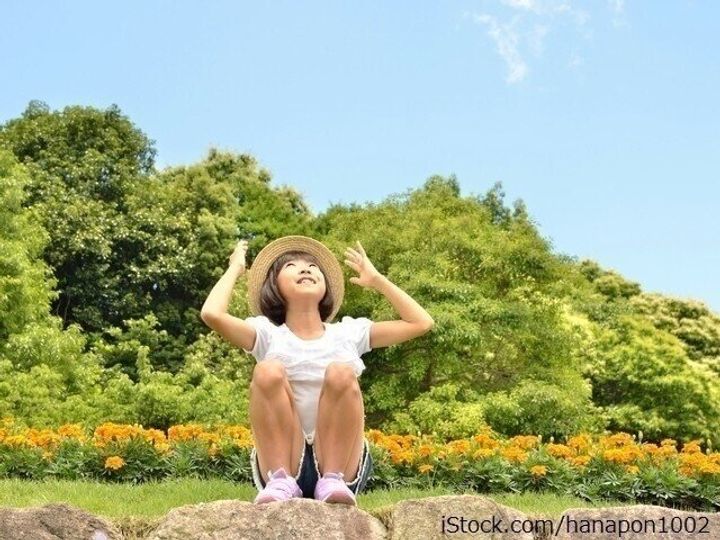【医師監修】ADHD(注意欠陥多動性障害)の赤ちゃんの行動特性(症状)と診断方法、サポートの仕方
ADHD(注意欠陥多動性障害)は、発達障害の一つであり、自己抑制がうまくできない障害です。注意力が散漫で、落ち着きがなく、衝動を抑えることが難しいことが特徴で、生活上でのさまざまな困難を抱えがちです。小中学生の3〜5%にADHDがあると考えられており、3〜5対1の割合で男の子に多く見られます。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の特徴は? 赤ちゃんのときにどんなサインが?
ADHD(注意欠陥多動性障害)は、注意力不足、落ち着きのなさ、衝動的な言動を抑制することの難しさを特徴とする発達障害です。不注意・多動性・衝動性の三つの特徴の現れ方はその人によって異なります。
ADHDの三つのタイプ
◎不注意型
「不注意」の特性が強く現れるタイプで、女の子に多い。気が散りやすく物事に集中できない。おとなしい子が多く、ADHDであることに気づかれにくい。
◎多動性・衝動性型
「多動性」「衝動性」が強く現れるタイプ。男の子に多い。授業中に立ち歩いたり、おしゃべりがやめられなかったり、ちょっとしたことでかんしゃくをお懲りたりするため、学校などで叱られることが多くなりがち。
◎混合発現型
「不注意」「多動性」「衝動性」の三つの特徴のすべてが見られるタイプ。ADHDの8割がこのタイプに属する。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の赤ちゃんはどんなサインを出す?
ADHDの行動特性である不注意、多動性は2歳くらいから現れていることが多くあります。しかし、落ち着きのなさや注意不足は、幼児期の子どもにはよく見られるものです。そのため、子どもが家庭での家族との関係の中だけで生活しているうちは、ほかの子どもと比較する機会も少ないため、その子の多動性や不注意が特異なレベルのものなのかどうかを保護者が判断することは難しいでしょう。特に赤ちゃんのうちにADHDに気づくことは困難です。
しかし、保育園や幼稚園に入園し、集団生活を送るようになると、集団の中で先生の指示に従ったり、集団行動をしたりといった場面で「ほかの子にはできるのに、この子にはできない」といったことが目立つようになります。ADHDがあることに最初に気づくのは、幼稚園や保育園、小学校の先生であることが珍しくありません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)は乳幼児期での発見が難しい
ADHDの行動特性は、子ども自身が自分の言動をうまくコントロールしなければならない状況に身を置くようになって、初めて周囲の人に気づかれるレベルで現れます。自分をセルフコントロールしなくても特に大きな問題のない環境、つまり1日中家族とだけ生活している状態の赤ちゃんのときに、ADHDが発見されることはほとんどありません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の子どもの特徴 入園後に顕著になる行動特性
「不注意」「多動性」「衝動性」の三つの特徴は、生まれつきの脳の機能の特異性によるものですから、本来、乳幼児のころから現れてはいます。しかし、実際に周囲がその特性に気がつくようになるのは、幼稚園や保育園、小学校に入学してからがほとんどです。ADHDの子どもには、園や学校などでの集団生活の中で以下のような行動特性が見られます。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の子どもの特徴の例
・忘れ物が多い、約束を忘れる
学校から宿題が出ていることを忘れたり、家でやった宿題を忘れたりすることがよくあります。学校からの配布物、家庭からの提出物もよく忘れます。また、友だちとの約束、クラスの中での係の仕事などもよく忘れることがあります。
・集中できない、注意力が散漫になる
物事に集中することが苦手です。宿題や課題づくりなどを最後までやり抜くことが難しいことがあります。窓の外の風景など、ほかの教室からの声などに気を取られてしまい、授業にも集中できないため、成績が下がってしまう場合があります。
・落ち着きがない
身体の一部をいつも動かしていたり、立ち上がって歩き始めたりする子がいます。じっと静かにしていなければいけない場所で、おしゃべりがやめられないこともあります。
・思いついたらすぐに行動に移してしまう
授業中、「挙手して、指名されてから発言する」といったルールを守ることができず、思いついたら許可なくすぐに発言してしまいます。友だちからイヤなことをされたとき、すぐに手を上げてしまうなど、行動を抑制することが苦手です。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の原因は? 赤ちゃんへの接し方、育て方との関係は?
ADHDの脳の動きを調べると、集中力の維持や感情の抑制といった機能を司る「前頭前野」が円滑に活動していないことなど、脳のいくつかの部位の活動が活発ではないことが確認されています。また、脳内の情報伝達を担う神経伝達物質の一つである「ドーパミン」の働きが低下している人もいます。
このような脳の機能上の特異性がなぜ発生するのか、ADHDの原因はまだはっきりとはわかっていません。しかし、脳そのものに外傷や病変があるから発生するといったものではなく、脳機能に関係する複数の遺伝子のかかわりが原因になっていると考えられています。ADHDは、親やきょうだいにADHDの人がいると、子どももADHDの発症率が高くなる(家族性がある)ことがわかっています。このことからも、ADHDの原因には脳機能にかかわる遺伝子の変異があると考えられます。生まれつきの脳の機能の偏りが原因で特有の行動特性が現れるわけですから、ADHDは、親の育て方や接し方、生まれ育った環境などが原因で起きるものではありません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の診断方法 赤ちゃんのうちに診断できる?
ADHDかどうかを診断するときに重要になってくるのは、子どもの日常生活での行動の特徴です。保護者から見て、ほかの子どもとのかかわりの中できになったこと、学校や園での生活の中での様子などを小児科医や児童精神科医に話し、さらに必要に応じて心理テストなどを行いながら判断します。学校の通知表や園からの連絡帳なども重要な資料になります。
ADHDの診断では、「不注意」「多動性」「衝動性」の三つの特徴につながる症状項目のどの程度あるかだけでなく、そうした行動特性が2か所以上の生活場面(例えば、保育園と家庭)で現れていること、その行動特性が6ヶ月以上続いていることが診断要件となります。したがって、家庭でだけ行動特性が見られる、担任の先生が替わってから急に現れるようになったといった場合は、ADHDとは診断されないことになります。つまり、幼児期では、「不注意」「多動性」「衝動性」は環境の変化などによってしばしば見られるものであるわけです。したがって、入園、入学前の小さな子どもがADHDかどうかを判断するのは実際には難しいといえるでしょう。ただ、子どもと接する中で気になることが出てきた場合は、かかりつけの小児科医や地域の保健センターに相談したり、児童相談センターなどの相談窓口を利用したりするとよいでしょう。ADHDであるかどうか診断はまだ先であったとしても、子育てをしている中での保護者が感じる不安や困り感を軽減できるような子どもへの接し方などを、アドバイスしてもらえるかもしれません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の治療、ADHDの子への対応方法
ADHDの原因となっている脳機能の特異性を薬や手術で根本的に治すことはできませんが、薬物療法で症状を改善し、並行して、行動療法を行って適切な行動がとれるように練習をしていくことで、社会適応力が身に付いていきます。
ADHDでは効果を発揮するお薬がある
コンサータ(一般名メチルフェニデート)やストラテラ(一般名アトモキセチン)、インチュニブ(一般名グアンファシン)という薬の服用によって、ADHDの多動性や衝動性を一時的に抑えることができます。服薬したADHDの人の8割に集中力が増す、考えてから行動できるようになるといった効果があることがわかっています。医師が必要と認めた場合、こうした薬が処方される場合があります。
ADHDでは行動療法が有効
薬は日常の困り感を軽減する上では有効ですが、薬の効き目が切れるともとの行動特性が現れます。薬の力を借りて症状の改善を図りながら、薬を服用しなくても感情や行動をセルフコントロールできるようになるため、行動療法を並行して行っていきます。行動療法の基本は、不適応行動を本人が自覚し、適切な行動へと変えていくことです。子どもが適切な行動をとったときにはごほうびを与え、おおいにほめることで、子どもがほめてもらえるような行動をしようとするようになります。行動療法は医師や臨床心理士などの専門家にその子の特性を踏まえて、その子に合ったプログラムをつくってもらうことになります。
ADHDでは、家庭や学校の環境改善も重要
ADHDの子どもが課題や作業に集中しやすい環境をつくることも重要です。学習机の周りには学習に関係のないものを置かない、宿題をやるときにはテレビを消して静かにするといったことで子どもは集中しやすくなります。また、教室でも、外の景色などに気を取られないため、最前列の真ん中付近の席にすることで授業に集中しやすくなります。
子どもの困り感を減らす支援が必要
ADHD(注意欠陥多動性障害)であると診断された場合は、医療・療育の専門家の支援を受けながら、その子の日常生活での困り感を減らすためのサポートを行うことになります。一方、ADHDの診断基準を満たさず、ADHDではないと診断された場合でも、子どもが家庭や学校で困り感を抱えているのであれば、それを放置することなく、何が原因で「不注意」「多動性」「衝動性」の三つの特徴が現れているのかを探り、保護者や学校、園の先生などと連携して、その原因を解決していくことが求められます。いちばん大切なのは、ADHDかどうかの診断結果ではなく、子どもが生活しやすくなるような支援を考えることです。
(取材・文/たまひよ編集部)
初回公開日 2017/8/18
育児中におススメのアプリ
アプリ「まいにちのたまひよ」

妊娠日数・生後日数に合わせて専門家のアドバイスを毎日お届け。同じ出産月のママ同士で情報交換したり、励ましあったりできる「ルーム」や、写真だけでは伝わらない”できごと”を簡単に記録できる「成長きろく」も大人気!
ダウンロード(無料)育児中におススメの本
最新! 初めての育児新百科 (ベネッセ・ムック たまひよブックス たまひよ新百科シリーズ)
大人気「新百科シリーズ」の「育児新百科」がリニューアル!
新生児から3歳まで、月齢別に毎日の赤ちゃんの成長の様子とママ&パパができることを徹底紹介。
毎日のお世話を基本からていねいに解説。
新生児期からのお世話も写真でよくわかる! 月齢別に、体・心の成長とかかわりかたを掲載。
ワンオペおふろの手順など、ママ・パパの「困った!」を具体的なテクで解決。
予防接種や乳幼児健診、事故・けがの予防と対策、病気の受診の目安などもわかりやすく紹介しています。
切り取って使える、「赤ちゃんの月齢別 発育・発達見通し表」つき。



 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い