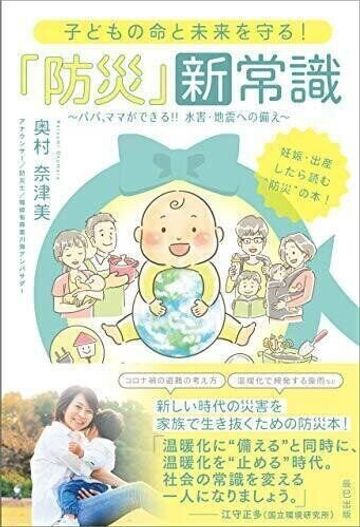1児の母・防災アナウンサーが伝える「防災グッズをそろえる前に必ず確認してほしいこと」
2023年2月6日、トルコ南部のシリア国境付近で起きた、トルコ・シリア大地震。東日本大震災以降、世界でも最悪の地震災害となっています。「地震国」日本に住む私たちにとっても、決してひとごとではないのではないでしょうか。2011年3月11日に起きた東日本大震災から、12年、日本でもし災害が起こったとき、家族や子どもの命を守るために、親としてどのように備えればいいのでしょうか。3歳の男の子のママである防災アナウンサーの奥村奈津美さんに話を聞きました。
日本は、世界一クラスで自然災害の多い国
――日本は世界的に見ても自然災害が多い国なのでしょうか?
奥村さん(以下敬称略) 地震については、世界で起きている地震のほぼ1割、さらに大地震に関しては2割が日本周辺で発生していると言われています。
また、ドイツのジャーマンウォッチというシンクタンクの報告書『世界気候リスク指数2020』で、2018年に気候変動による影響を最も受けた国は日本であると発表されました。気候変動の影響で豪雨や土砂災害、酷暑による熱中症、台風などの気象災害が多く発生している、この変化を感じている人は少なくないでしょう。
異常気象というと遠い外国の話のように聞こえるかもしれませんが、実は私たちの日本は、世界一といっていいほど自然災害の多い国なのです。だからこそ、日々の暮らしが防災につながるようなライフスタイルに見直していくことが大事ですし、災害時要配慮者と言われる妊婦・乳幼児がいる家庭は、いざというときのために備えておくことが大切です。
防災グッズを買う前にハザードマップを見てほしい
――子育て世帯が災害に備える上で、いちばん気をつけるべきはどんなことですか?
奥村 防災グッズをそろえる前にまず必ず見てほしいのは、住んでいる地域のハザードマップです。
ハザードマップとは、自然災害による被害を予測し、その被害の範囲を地図に表したものです。「洪水」「内水」「高潮」「津波」「土砂災害」「火山」などの種類があります。
洪水ハザードマップには、洪水発生時に、家のどの高さまで水が浸水するのかが色分けされてわかるようになっています。避難所の場所や、避難時に通れなくなる場所も把握できます。
もし自宅がある場所が洪水時に家屋倒壊等氾濫想定区域や、寝室が浸水する想定、土砂災害警戒区域など危険な場所だとわかれば、何をそろえるかよりもどう避難するか、何を持っていくか、を考える必要があります。逆に想定のない地域なら、在宅避難用の準備をすることができます。
私は令和3年7月3日に伊豆山土砂災害が起きた熱海にも、約1週間後に調査に行きましたが、土砂災害があったのはハザードマップで土砂災害警戒区域として危険性が示された地域でした。
――災害が起きた時に、避難をする必要がある地区なのかを知っておくことが、命を守ることにつながるんですね。
奥村 そうです。防災対策の最も大事な要は、地域のリスクを知ることです。どれだけ防災グッズをそろえても、津波で流されるエリアや、土砂災害のエリアに住んでいたら、それが全部使えない状態になってしまいます。
また、地震に備える場合は、住んでいる家が耐震基準を満たしているかどうかを最低限知っておいてほしいです。1981年6月より前に建てられた家は、大きな地震が起きると倒壊する恐れがあるので、リノベーション物件などに住んでいる人は、住居が建てられた時期を確認しておきましょう。
危険な地域に住んでいたら、避難場所候補をいくつか準備しよう
――危険な地域に住んでいるとわかったら、どんなタイミングでどこへ避難をすればいいのでしょうか。
奥村 台風や豪雨などの水害時、乳幼児や妊産婦がいる家庭は、自治体から発表される「警戒レベル3・高齢者等避難」で避難しましょう。乳幼児がいると夜泣きをしたり、避難所で騒いでしまうかも、と心配であれば、避難所以外に、リスクのない場所に暮らす親せきや友人、ホテルなどの選択肢を考えておくのもいいですよ。台風など事前に予測できるものなら、進路外の地域にプチ旅行という気持ちで広域避難する手も。頼れる場所がない、という場合は、車中泊という方法もあります。ハザードマップで安全な場所に早めに移動しておくと、荷物も持っていくことができます。
不安に思ったら、避難をしてみることをおすすめします。空振り避難となったとしても、避難をしてみて初めて本当に必要なものがわかることもあります。避難所に行って、「椅子があったほうがよかった」「マットがあったらよかった」とわかったという人もいました。
また、感染リスクが心配な場合もあります。自宅が安全な場所だとわかっていれば、避難指示が出ても在宅避難をして問題ない、という通知は政府からも出ています。避難所運営ガイドラインでは、在宅避難者にも物資などを支援するようになっています。妊婦や乳幼児がいる家庭はなおさら、できるだけ安全な場所で過ごすようにしましょう。
母乳育児とミルク育児で備えが違う。2週間分は用意して
――では実際、乳幼児や妊婦がいる家庭で備えるべきもの、子どもと一緒に避難をする時に持つべきものはどんなものでしょうか?
奥村 普段持ち歩いているママバッグには、子どもたちに欠かせないものが入っていますよね。紙おむつ、おしりふき、ゴミ袋、ウェットティッシュ、おやつなどはどれも災害時に役立ちます。普段から少し多めに入れておき、お出かけから帰宅したら補充しておくといいでしょう。
とくに、母乳かミルク授乳かによって必要なものが違います。母乳なら授乳ケープ、ミルク授乳なら3日分の個別包装の粉ミルクや液体ミルクと、紙コップがあると安心です。災害時は哺乳びんを消毒するのが難しいため、コップ授乳を練習しておくのもいいと思います。
また、ミルク授乳の場合に家庭で備えておきたいのは、2週間分の粉ミルクと水、調乳用のお湯を沸かすカセットコンロ、カセットボンベです。液体ミルクを備える場合は高温にならない場所に保管しましょう。
農林水産省が推奨する乳幼児、アレルギーがある子の備え(※)は2週間分。つまり、それだけ物資が届かない可能性があるということ。子どもが普段口にする食べ物や飲み物、肌にあう紙おむつなど、最低でも2週間分は準備し、ローリングストックしておくといいと思います。避難する場合は、それを非常持ち出し袋に入れて持ち出せるといいですね。また、子どもの靴は支援物資で届きにくいので、避難する時に靴を履かせるのを忘れないようにしましょう。履かせる時間のない時は非常持ち出し袋に入れることを忘れずに。
災害時に備えるべきものは、人によってかなり違います。自分の家族はどんなものが必要か、一度考えてみてほしいと思います。
住んでいる地域、家の構造、家族構成などで備えが変わるからカスタマイズを
――自分の家族にはどんなものが必要か、考えるきっかけはどこから始めばいいでしょうか?
奥村 防災の難しさは、住んでいる地域、家の構造、家族の構成など、その人によって必要な備えが変わってくるところです。防災講座などではそれぞれの環境に合わせた対策が必要なことを伝えていますが、自分の家仕様にカスタマイズすることはなかなか大変です。2023年3月1日、私が監修に携わったパーソナル防災サービス『PASOBO』ができました。 リスク診断するだけではなく、そのリスクに応じての行動アドバイス、さらにその人、その家族に必要な防災商品まで提案する防災コンシェルジュのような機能も備わっています。しかも自分の必要な防災グッズが1分でわかるんです。このようなサービスも利用してほしいと思います。
お話・監修・写真提供/奥村奈津美さん 取材・文/早川奈緒子、たまひよONLINE編集部
今後日本は、地球温暖化によって豪雨災害等のさらなる頻発化・激甚化が予測され、また大震災に見舞われる確率も高いといわれます。「子どもたちを守るためには、親の判断や親の知恵が命の分かれ目になります。また、子どもたちが生きる未来のため、防災だけでなく地球環境にも意識を向けていくことが必要」と奥村さんは言います。
●この記事は、再監修のうえ、内容を一部更新しました(2023年2月)
奥村奈津美さん(おくむらなつみ)
PROFILE
NHK「おはよう日本」「あさイチ」などテレビ·ラジオをはじめ、雑誌·新聞など様々なメディアで「おうち防災」の専門家として出演。1982年東京生まれ。広島、仙台で地方局アナウンサーとして活動。その後、東京に戻りフリアナウンサーに。TBS『はなまるマーケット』で「はなまるアナ」(リポーター)を務めるほか、NHK『ニュースウオッチ9』など報道番組を長年担当。東日本大震災を仙台のアナウンサーとして経験。以来10年以上、全国の被災地を訪れ、取材や支援ボランティアに力を入れる。防災士、福祉防災認定コーチ、防災教育推進協会講師、防災住宅研究所 理事、東京都防災コーディネーター、中野区防災リーダーとして防災啓発活動に携わるとともに、環境省 森里川海プロジェクトアンバサダーとして「防災×気候変動」をテーマに取材、発信中。
子どもの命と未来を守る! 「防災」新常識 パパ、ママができる!!水害・地震への備え
コロナ禍の避難の考え方・温暖化で頻発する豪雨など、新しい時代の災害を家族で生き抜くための“防災本"。妊娠・出産したら読む防災の本です。


 SHOP
SHOP 内祝い
内祝い